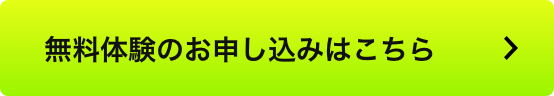オンラインゲームなどをしていると「ナーフ」という言葉を耳にすることがあります。皆さんはどういった意味の言葉かご存知でしょうか。
この記事ではゲーム用語として用いられるナーフについて分かりやすく解説します。合わせて、デバフとの違いやシステム運営がナーフする理由、ナーフがユーザーに与える影響についても紹介しています。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事のコンテンツ
ゲーム用語のナーフって何のこと?

ゲームで用いられる「ナーフ」は、運営の行うアップデートにおいてキャラクターや武器、アイテムなどのステータスや効果が下方修正(弱体化)されることを表す言葉です。
対戦型のゲームで見られることが多いですが、まれにMMORPGやシュミレーションゲームなどでもナーフは行われています。
また、ネットスラングとしてナーフというゲーム用語が広く知られるようになったことから、以前よりも弱体化したもの、劣化したものに対して「ナーフ」という言葉が使われるようになりました。
ナーフの語源
ナーフの語源はアメリカの玩具会社Hasbroが販売しているガントイ「Nerf(ナーフ)」から生まれたと言われています。Nerfは世界中の子ども達から人気を集めるガントイで、スポンジでできた銃弾を実際に発射することも可能です。近年、安全にサバゲ―を楽しみたい初心者の間で「ナーフサバゲー」なども人気を集めています。
ある時、ゲームで運営によるバランス調整が行われ銃型の武器が弱体化してしまいました。その際にネット上に書き込まれた「弱体化してしまって、おもちゃのNerfのようだ」と言った愚痴が注目を集め、世界中で使われるネットスラングになったと言われています。
ナーフとデバフの違い
同じ弱体化という意味を持つゲーム用語に「デバフ(debuff)」があります。
ナーフは運営のシステムアップデートによって実装された弱体化です。そのため、弱体化したステータスや効果は、再びアップデートによって仕様が変更されない限り解消されることはありません。つまり、永続的な弱体化と言えます。
一方、デバフはアイテムや魔法など、ゲーム内でプレイヤーが発動させ、かつ持続効果に限りがある弱体化です。状態異常と同意義であり、場合によっては魔法やアイテムで回復させ弱体化状態を解除することも可能でしょう。
ナーフとデバフの違いは、永続的弱体化と一時的弱体化の違いと言えます。
デバフに関しては下記でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
デバフとは?意味や効果、バフとの違いを初心者にもわかりやすく解説
ナーフの反対は「アッパー」「ビーフアップ」
ナーフが弱体化であるなら、反対に強化されることを何というかご存知でしょうか。
一般的にシステアップデートによるキャラクターや武器・アイテムの強化を「アッパー(upper)」や「ビーフ アップ(beef up)」と呼びます。日本ではあまり馴染みのない表現ですが、海外では頻繁に用いられているフレーズです。
アッパーは上昇する、という意味を持つ言葉で、言葉のニュアンスから「強化」と表現する際に用いられています。一方、beef upは本来「筋肉を強くする」のような意味を持ちますが、キャラクターのステータス上昇をイメージさせることからナーフの反対語として用いられるようになりました。
ゲーム運営会社がナーフをするのはなぜ?

弱体化と聞くと、ユーザーにとっては喜ぶことができませんよね。しかし、ナーフは適切な意味を持って行われています。続いては、運営がナーフする理由について解説します。
理由1.キャラクターや武器のパワーバランスを修正したいから
ゲームシステムを構築する際に、多くのプログラマーは均等なパワーバランスを目指します。圧倒的に強いキャラクターや武器が存在してしまっては、ゲームに勝ちたい人は皆同じキャラクターや武器を選んでしまうし、全員が同じキャラクターでプレイしてしまうと多様な遊び方ができなくなり、ゲームとしての魅力を損なってしまうからです。
しかし、近年1つのタイトルに用いられるキャラクターの数は増加傾向にあり、使用できる武器も多種多様になっています。なかには、組み合わせによってプログラマーの予想以上のステータスや攻撃力を手に入れてしまうこともあるでしょう。
こういった想定以上に強すぎるキャラクターや武器の存在を「OP(オーバーパワー)」と言います。OPはゲームの均等性を損なってしまうため、ナーフしてバランスを調整する必要があるのです。
理由2.環境によってキャラクターや武器の使用率が偏ってしまっているから
SNSや動画配信によってゲームの情報を簡単に入手できるようになり、多くの人が「環境」を意識するようになりました。
環境とは、「これを使えばゲームで有利」というキャラクターや武器の組み合わせのことで、該当する対象を「環境デッキ」「環境武器」「環境キャラ」などと呼ぶこともあります。環境には流行りもあり、廃れては新たな環境が生まれるというサイクルを繰り返しています。
環境によって武器やキャラクターの使用率に偏りが発生してしまうと、ゲームは均等性を損ない本来の楽しみ方ができなくなってしまうでしょう。そのため、人気に偏りが出るのを防ぐため、環境武器や環境キャラクターをナーフすることがあるのです。
ナーフによって環境が崩されることで、ユーザーは新たな環境探しに躍起になり、ユーザーの稼働率が増えてゲームが盛り上がります。
理由3.ユーザーの動向を見ながらバランス調整する必要があるから
近年のオンライン対戦ゲームでは、定期的なアップデートが必要不可欠と言われています。今や、ネット回線を用いたゲームは主流となり、次から次へと新作が発表されます。そのため、完璧に全ての内容を作り込んでから配信を始めるのではなく、大まかな形が完成したら配信を始め、ユーザーの動向などを見守りながらシステムを調整していく形式が一般的です。
ユーザーの動きやキャラクター・武器などの使用率、アイテムの活用方法など、さまざまなデータを確認しながら均等性や公平性を保ちゲームを盛り上げるためにバランス調整を行います。
スタートをざっくりと作っている分、ビーフアップもナーフも多くなってしまうのは仕方のないことでしょう。しかし、こういったユーザーの動向を盛り込んだアップデートを行うことで、よりユーザーの好みを反映したゲームに育っていきます。
理由4.難易度が高すぎたから
ナーフは主にFPS、TPS、MOBA、格闘ジャンルなど、対人戦のゲームで見られることが多いです。しかし、稀にMMORPGやシュミレーションゲームなどでもナーフが行われることがあります。
その理由は、NCPが想定以上に強すぎて、プレイヤーがゲームを楽しめていないからです。あまりに強すぎるNCPに長期間足止めをくらうと、ユーザーはゲーム離れを起こしてしまう可能性が高いです。
そのため、クエストのクリア率などを調査し、あまりにNCPの設定が強すぎる場合には、アップデートでナーフされることがあります。
ナーフの使用例
ネットスラングやゲーム用語として用いられるナーフは「~される」と用いられることが多いです。ゲームでは運営の意思で行われ、ユーザーはナーフを受け入れる以外の選択肢がないため、受動的な表現となるのでしょう。
主に、以下のように使われることが多いです。
- ナーフキャラなのに、まだ使ってるの?
- ガチャでようやく引き当てたのに、直後にナーフされた。信じられない。
- やった!あの武器がナーフされた!
- 今回のアップデートはナーフが多いな。
- このアイテムは強すぎる。きっと次のアップデートでナーフされるよ。
ナーフされた武器やキャラクターを「ナーフ武器」「ナーフキャラ」などと呼ぶケースもあるようです。また、Vtuberなどが自身のアバターに関して「ナーフされた!」などというケースもありますが、これはアバターの動きが悪くなったり、スタイルが悪くなったりするのに対して、「ボーン(骨組み)を減らされた」ということをナーフ(弱体化)に例えて揶揄しています。
ナーフがプレイヤーに与える影響

ナーフはゲームの均等性と公平性を保つため、運営にとって避けては通れないものです。正当であり、その後のプレイに良い影響を与えれば評価されますが、ナーフしたことでゲームが盛り下がれば批判されたりユーザー離れが起きたりしてしまう諸刃の剣とも言えるでしょう。
一方で、ナーフされることでユーザーにはさまざまな影響があります。ナーフされることで良い点も悪い点もあるでしょう。最後に、ナーフがプレイヤーに与える影響について解説します。
ナーフが与える良い影響
サーフされることで、以下の点をメリットに感じるユーザーもいます。
環境が破壊される
勝ち筋を抑えやすい流行りの武器やキャラクターである環境系がナーフされることで、マンネリ化したプレイから脱出できるようになります。「いつマッチングしても相手は同じ武器ばかりを使ってきてうんざりしている」と、環境に否定的なユーザーも少なくありません。そんなユーザーにとってナーフは待望のアップデートと言えるでしょう。
一時的にランク戦を勝ち上がりやすくなる
ある武器がナーフされると、多くの人は違う武器に変更します。その際、新たな武器を使いこなすまでは時間が必要でしょう。人気の武器がナーフされることで、一時的に多数のプレイヤーのスキルが低下し、ナーフ対象外の武器を使っていたプレイヤーが有利な状況になることがあります。特に環境武器などがナーフされた際には、ランクマッチで勝ち上がりやすく、昇格するプレイヤーも多く見られます。
しかし、新武器に慣れてこれば自前のスキル勝負や戦略勝負になってくるため、優位性はあくまで一時的と言えるでしょう。
ナーフで受ける悪い影響
ユーザーのなかには、ナーフされるデメリットを以下のようにとらえる人もいます。
銃などの武器の変更を余儀なくされる
自分が普段使っている武器がナーフされた場合、武器の変更を余儀なくされるでしょう。もちろん、ナーフされたからといって対象の武器を使ってはいけない訳ではありません。しかし、下方修正の度合いによっては明らかに戦力が減退してしまったり、使用感が変わってしまったりするケースもあります。
武器の変更を余儀なくされることで、新しい武器の選定や練習が必要になります。それすらもゲームの楽しさと納得できる場合はよいですが、敗北が続いてしまうとゲームに嫌気がさしてしまうこともあるでしょう。
チーム戦での連携がとりにくくなる
ナーフをきっかけに武器やキャラクターを変更するユーザーは珍しくありません。チーム戦などで戦うゲームタイトルの場合、仲間が新たな武器やキャラクターに慣れるまでの間、連携がとりにくくなることもあります。
そのため、自分自身の使用キャラクターや武器に限らず、仲間の使用用キャラクター・武器がナーフ対象となっていないかチェックする人も少なくありません。
課金が無駄になる可能性がある
ゲームによっては課金して獲得したキャラクターがナーフによって弱体化してしまうケースも稀に見られます。ガチャなどでようやく引き当てたキャラクターがナーフされてしまうと、がっかりしてしまいますよね。こういったケースでは運営に対する不信感を訴えるユーザーも少なくありません。
ナーフは予測できる?運営の動きと兆候から読み解く

「ナーフされそうなキャラや武器は、実はある程度「予測可能」です。
特に、過去のナーフ傾向・運営の発言・テスト環境の変化には注目すべきポイントが存在します。ここでは、ナーフ予測のために押さえておくべき3つの視点を紹介します。
過去の傾向から見るナーフされやすい要素
ナーフされる対象には、明確な共通点があります。もっとも多いのは「使用率が極端に高く、勝率も高い」状態です。
これらはゲームバランスを崩す要因とみなされやすく、放置されるとユーザー体験が偏るからです。また、プロシーンで一強状態のキャラや武器は、競技性に支障が出るためナーフ候補となりがちです。
さらに、SNSやフォーラムで「強すぎる」「壊れてる」などの不満が頻出している場合、運営側も注視していることが多く、調整対象となる可能性が高まります。
公式の発言やパッチノートで予兆を察知
ナーフは突然行われるわけではありません。開発者コメントや公式ブログ、パッチノートの「次回調整予定」などの文言から、ある程度の予兆を読み取ることが可能です。
たとえば、「一部のキャラに関しては現在注視しています」や「テスト環境でのデータ収集中です」といった記述は、近い将来ナーフが入る前兆です。
また、公開テスト環境(PTR)で一時的に弱体化されている場合、本実装前の試験的ナーフと考えられます。公式発信には常に目を通しておきましょう。
ナーフ予測が活きるのはどんなとき?
ナーフの予測は、プレイヤーの戦略に大きく役立ちます。たとえば、大会やランクシーズン切り替え前に「次に何が弱くなるのか」を把握していれば、練習キャラや使う武器の再検討が可能になります。
また、課金して手に入れるキャラ・武器がナーフされそうなら、先にリスクを察知して投資判断ができます。さらに、ナーフ直後の混乱時にスムーズに立ち回るためにも、事前に代替戦術や次の強キャラ候補を用意しておくと有利です。
ナーフは違法?法的リスクと景品表示法との関係とは

ナーフをめぐって「課金して手に入れたのに弱くされた」「これって詐欺じゃないの?」と疑問を抱くユーザーも少なくありません。
果たして、ゲーム運営が行うナーフは法的に問題があるのでしょうか?ここでは、違法性の有無や景品表示法との関係について詳しく解説します。
ナーフは基本的に違法ではない
結論から言えば、ナーフ自体は基本的に違法ではありません。
多くのオンラインゲームでは、利用規約に「ゲーム内コンテンツの性能や仕様は、運営側の判断で予告なく変更されることがある」と明記されています。
つまり、キャラクターや武器の性能を調整する権利は運営にあり、ユーザーはその条件に同意した上でプレイしているため、ナーフが即座に違法とされることはないのです。これはゲームバランスを保つための調整であり、運営の裁量内の行為として正当とみなされるのが一般的です。
景品表示法に違反する可能性があるケース
とはいえ、ナーフのやり方や事前の宣伝方法によっては、例外的に「景品表示法違反」に該当する可能性もあります。
たとえば「このキャラは最強!勝ちたければ課金しよう!」といった強調表現で販売された直後に弱体化された場合、購入者に誤解を与えたと判断される恐れがあります。
これは「優良誤認表示」に当たり、過去には一部のソーシャルゲームで消費者庁から行政指導が入った例も存在します。特に課金を誘導するタイミングでのナーフには注意が必要です。
参照:消費者庁・景品表示法
ユーザーが取れる対応・救済手段について
ナーフによって大きな不利益を被ったと感じた場合、まずは運営に対して問い合わせフォームなどから意見や要望を伝えるのが基本的な対応です。
納得できない表現や、強さを誇張した広告に疑問がある場合は、消費者庁や国民生活センターに相談するという手段もあります。ただし、実際に法的処置が取られるケースはごくまれで、多くは運営側の裁量とされます。とはいえ、ユーザーの声がナーフ調整の方向性に影響を与えることもあるため、意見発信には一定の価値があります。
ナーフに関するよくある質問(FAQ)
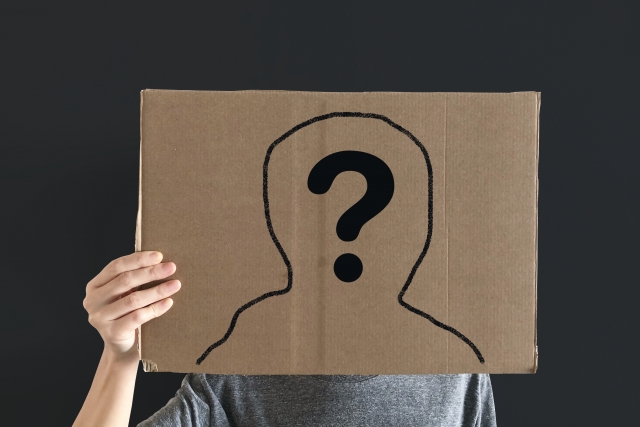
ナーフについて調べていると、「そもそもナーフされたキャラって使えるの?」「課金アイテムが弱体化されたらどうなるの?」など、気になる点がいくつも出てきます。ここでは、よくある3つの質問に対してわかりやすくお答えします。
Q1:ナーフされたキャラや武器はもう使い物にならない?
ナーフされた=完全に使えない、というわけではありません。確かに一部の性能は落ちますが、プレイスタイルや立ち回り次第では十分に活躍できるケースもあります。
むしろ、極端な強さが調整されたことでバランスが取れ、周囲との相性が改善されることも。環境に合わせた再評価をすることで、新たな使い道が見つかる可能性もあります。
Q2:課金して手に入れたキャラがナーフされた…返金できる?
原則として、返金対応はされないことが多いです。多くのゲームでは「ゲーム内アイテムの性能変更は運営の裁量」と利用規約に明記されており、それに同意したうえでのプレイと見なされます。
ただし、一部の大規模ナーフや誤表記による購入で返金対応された事例もあるため、不満がある場合は一度運営に問い合わせてみる価値はあります。
Q3:ナーフを止めさせる方法はある?ユーザーの声は届く?
ナーフの決定は運営側のバランス調整方針によるもので、直接止めることはできません。しかし、プレイヤーのフィードバックが次回以降のパッチや調整に影響を与えることはあります。
SNSや公式フォーラム、アンケートなどで意見を表明することは、運営にとって重要な指標の一つとなるため、冷静かつ建設的な形での発信は決して無駄ではありません。
ナーフに左右されないスキルを身に付けるならアフラスの無料体験へ!
システムアップデートによって弱体化されてしまう「ナーフ」について解説してきました。自分が使っている武器やキャラクターがナーフされてしまうとガッカリしてしまいますが、ゲームの公平性や均等性を保つために必要なことです。
「仕方ない」と諦め、新たな武器やキャラクターを選ぶのがよいでしょう。
ナーフされたとしても、武器やキャラクターのステータス差を上回るスキルやアイテム効果を跳ねのける戦略があれば、ゲームでは勝ち続けることができます。敢えて、ナーフされた武器を使って上位ランカーに勝負を挑むのもよいでしょう。
ナーフされたからといってゲームを諦めず、新たな武器やキャラを選んだり、スキルを磨いてナーフ状態の武器のまま戦ったりと、自分なりの楽しみ方を模索してみてください。
AFRAS(アフラス)はゲームスキルを高めたい人のためのゲーミングスクールです。eスポーツプレイヤーの講師によるマンツーマン授業で、自分の求める内容の指導が受けられます。ナーフされた武器でも勝てるほど圧倒的なスキルを獲得したい人は、ぜひチェックしてみてください。