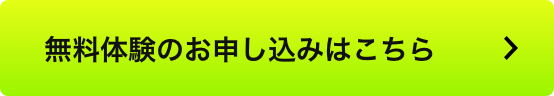「ゲームでよく聞くヘイトってどういう意味?」
「RPGやMMORPGでヘイト管理って何をするの?」
このように感じたことはありませんか?
本記事では、ゲームにおけるヘイトの意味や語源をわかりやすく解説しています。さらにRPG・MMORPG・MOBA・FPSなどジャンルごとの具体的な使い方も例文とともに紹介します。誤解しやすい感情的な嫌悪とは違うゲーム用語の正しい理解ができますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
ゲームで使うヘイトとは何のこと?

ゲーム内のヘイトとは、敵から特定のキャラクターが攻撃対象と認識される状態を意味します。RPGやMMORPGなどのジャンルでは、ヘイト値が高いキャラクターに敵の攻撃が集中する仕組みが一般的です。パーティーの中で防御力やHPが高いキャラクターに攻撃を集めることで、他の味方が安全に行動できる環境を作ることができます。
この行動は「ヘイトコントロール」と呼ばれ、戦闘の戦略を左右します。特に強力な敵と戦う際には、役割分担や協力が重要になります。戦術のひとつとして理解しておきましょう。
ヘイトの意味
ヘイトのゲーム内での意味は、敵に狙われやすくなる状態や数値を指します。攻撃や回復など特定の行動をするとヘイト値が上がり、そのキャラクターに敵のターゲットが集中します。例えば、味方の回復役が敵から狙われた場合、タンク役がヘイトを稼ぐことで攻撃対象を自分に向けることができます。
これにより、パーティー全体の安定した戦闘が実現します。敵から狙われる仕組みを理解しておくことは、特に協力プレイでは欠かせません。まずはゲーム内でヘイトの動きを意識してみてください。
ヘイトの語源は「hate」
ヘイトという言葉の語源は英語の「hate」で、「憎む」「嫌う」という意味を持ちます。日常会話では「I hate onion.(私は玉ねぎが嫌い)」のように使われます。また、ヘイトスピーチやヘイトクライムといった言葉も存在します。これらは人種や宗教などへの偏見や憎悪に基づく発言や犯罪行為を指します。
一方で、ゲームにおけるヘイトは敵の注意を引きつける行動として使われています。現実の社会問題と混同せず、ゲーム内の用語として正しく理解しておくことが大切です。
初心者こそ知っておきたい、ヘイトを理解するメリット

ヘイトを理解することは、単なるゲーム用語の知識にとどまりません。プレイそのものの上達や仲間との円滑な連携、さらには社会的な文脈における言葉の正しい使い分けにも役立ちます。ここでは、特に初心者が知っておくことで得られる3つの大きなメリットを解説します。
ゲームの上達に直結する
RPGやMMORPGなどでは、ヘイトの仕組みを理解しているかどうかで立ち回りが大きく変わります。タンクが敵の攻撃を引きつけ、アタッカーやヒーラーが安全に行動できるのは、ヘイト管理が機能しているからです。
仕組みを知らずに行動すると、思わぬタイミングで敵のターゲットが移り、パーティが全滅することも。初心者が早い段階でヘイトを理解することで、効率的に成長でき、勝率アップにもつながります。
ゲームの上達に関しては下記でより詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
ゲームの上達が早い人の特徴を解説!ゲームセンスを鍛えるには?
コミュニケーションのすれ違いを防ぐ
オンラインゲームでは「タゲ取って!」「ヘイト稼いで!」といった言葉が頻繁に飛び交います。
ヘイトの意味を知らないと指示を理解できず、パーティ全体の行動が乱れてしまうこともあります。逆に理解していれば、仲間との意思疎通がスムーズになり、協力プレイが格段にやりやすくなります。
初心者が用語を正しく把握しておくことは、円滑なコミュニケーションを築き、信頼されるプレイヤーになるための第一歩といえるでしょう。
社会的文脈でも混乱を避けられる
「ヘイト」という言葉はゲームだけでなく、現実社会では「ヘイトスピーチ」「ヘイトクライム」など差別や偏見に関連して使われることも多いです。
このため、文脈によって意味が大きく異なります。ゲームにおける専門用語としてのヘイトを正しく理解していれば、会話やSNSで誤解を招くリスクを減らせます。初心者のうちに両方の使い方を知っておくことは、オンラインでもオフラインでもトラブルを避けるために役立ちます。
ジャンル別で見るゲーム内の「ヘイト」

ヘイトの仕組みは、ゲームのジャンルによって役割や重要度が大きく異なります。RPGやMMORPGでは戦闘システムの核となり、MOBAやFPSでは戦略的な立ち回りに影響します。ここでは代表的なジャンルごとに、ヘイトがどのように機能するのかを解説していきます。
RPGにおけるヘイト
RPGでは、ターン制バトルの中で「どのキャラが敵から狙われるか」を決める要素としてヘイトが機能します。タンク役が挑発スキルでヘイトを稼ぎ、攻撃役や回復役を守るのが定石です。
初心者は「強い攻撃をすると敵がこちらを狙いやすい」という基本を理解することで、無駄な戦闘不能を防ぎ、安定した攻略が可能になります。
MMORPGにおけるヘイト
MMORPGでは、リアルタイムで複数プレイヤーが協力するため、ヘイト管理は最重要要素のひとつです。タンクが敵視を集め続ける一方で、DPSが火力を出しすぎるとタゲが移ってしまうこともあります。
ヒーラーも回復量でヘイトを稼いでしまうため、全員がヘイトを意識して役割を果たす必要があります。理解していないとパーティ全滅につながるため、初心者こそ早く身につけたい知識です。
MOBAにおけるヘイト
MOBAでは、RPGやMMORPGのような「敵視値」としてのヘイトは明示されませんが、敵プレイヤーから狙われやすい状況=事実上のヘイトが存在します。
たとえば体力が減ったキャラや高火力を出せるキャラは集中攻撃を受けやすいです。チーム内で狙われやすさをコントロールし、味方を守る立ち回りを意識することが勝敗を分けます。
FPSにおけるヘイト
FPSではヘイトという数値概念はないものの、プレイヤーの位置取りや行動で「敵の意識を引きつける」ことができます。
例えば囮役が大胆に動き、敵の視線や攻撃を引きつけている間に、仲間が背後から攻め込むといった戦術が典型例です。ヘイトの考え方を応用することで、単純な撃ち合い以上の戦略性を発揮できるのが特徴です。
アクションゲームにおけるヘイト
アクションゲーム、とくにボス戦がある作品では、プレイヤーの攻撃パターンや行動に応じて敵AIがターゲットを切り替えます。
特定の攻撃を誘発することで仲間を守ったり、安全地帯を作ったりするのは、まさにヘイトコントロールの応用です。初心者でも「自分が敵の注意を引きつけている」という意識を持つと、立ち回りが一段階上達します。
ジャンル別ヘイトの特徴一覧
| ジャンル | ヘイトの特徴 | 例文・使い方 |
|---|---|---|
| RPG | ターン制バトルで「誰が狙われるか」を決める要素。タンクが挑発で引き受ける。 | 「タンクがヘイトを稼いで!」 |
| MMORPG | リアルタイム戦闘で最重要。タンク・DPS・ヒーラー全員が管理を意識する必要がある。 | 「回復でヘイト上がったから注意!」 |
| MOBA | 数値としては存在しないが、狙われやすさ=事実上のヘイト。集中攻撃されやすい役割がある。 | 「後衛キャラが狙われやすいから守って!」 |
| FPS | 数値管理はないが、囮役が敵の意識を引きつけるなど戦術的に応用される。 | 「自分が突っ込むからカバーして!」 |
| アクションゲーム | 敵AIがプレイヤー行動に応じてターゲットを切り替える。攻撃誘発で仲間を守る戦術も。 | 「ボスのヘイト取って動きを誘導する!」 |
ゲームのジャンル別!ヘイトの使い方を例文で解説

ゲームで使われる「ヘイト」という言葉は、ジャンルによって少しずつ意味や使われ方が異なります。特にRPG、MMORPG、MOBA、FPSでは、ヘイトの概念が戦術やプレイスタイルに影響を与えます。
これから紹介する3つのジャンルでは、プレイヤー同士や敵キャラクターとの関係性の中でヘイトがどのように働くのかそれぞれ例文を用いて解説します。自分がよくプレイするゲームジャンルでのヘイトの理解に役立ててください。
RPGでのヘイトの使い方
RPGでのヘイトの使い方の例文を3つ紹介します。
- 「このスキルで一気にヘイト稼いだから、回復頼む!」
- 「主人公の防御力を上げて、ヘイト集めさせよう」
- 「ヘイト管理失敗して、魔法使いが狙われた…」
「このスキルで一気にヘイト稼いだから、回復頼む!」
RPGではタンクや前衛のキャラクターが敵からの攻撃を引き受ける役割を担います。強力な挑発スキルや高威力の攻撃を使うことで、敵のヘイトが急上昇します。このセリフは、前衛がヘイトを集めた直後に後衛へ回復を要請する場面を表しています。パーティー全体の連携が問われる瞬間ともいえるでしょう。うまく連携が取れれば、戦闘を有利に進めることができます。
「主人公の防御力を上げて、ヘイト集めさせよう」
主人公やタンク役のキャラクターに防御強化スキルをかけることで、安全にヘイトを集められます。この方法は、敵の攻撃を耐えられるキャラクターを狙わせるために使われます。回復役や魔法使いといった防御力の低いキャラクターへの被害を防ぐことができます。戦術の基本として覚えておくと、多くのRPGで役立つでしょう。
「ヘイト管理失敗して、魔法使いが狙われた…」
ヘイト管理に失敗すると、本来狙われるべきでない後衛キャラクターが敵に狙われることがあります。このセリフは、魔法使いなどの低防御キャラクターが攻撃を受けてしまった状況を示しています。こうした事態を防ぐためには、タンク役が常にヘイトを高く保つことが必要です。事前の役割分担や立ち回りが重要になるでしょう。
MMORPGでのヘイトの使い方
MMORPGでのヘイトの使い方の例文を3つ紹介します。
- 「タンクがちゃんとヘイト取ってるから、遠距離職は安心して攻撃して」
- 「ヒーラーが回復しすぎて、ヘイト上がってるから注意ね」
- 「このボス、範囲攻撃でヘイトリセットするから気をつけて」
「タンクがちゃんとヘイト取ってるから、遠距離職は安心して攻撃して」
MMORPGでは、パーティー内のタンク役が敵からの攻撃を引き受ける役割を担います。このセリフは、タンクが十分にヘイトを稼いでいるため、後衛の遠距離攻撃職が安全に攻撃に集中できる状況を表しています。遠距離職はタンクが敵の注意を集めている間にダメージを与えるのが基本です。パーティー全体の連携とタンクのヘイト管理が勝敗を左右します。
「ヒーラーが回復しすぎて、ヘイト上がってるから注意ね」
ヒーラーが頻繁に味方を回復すると、敵に狙われるリスクが高まります。このセリフは、ヒーラーが必要以上に回復を行い、敵のターゲットになりかけている状況を指しています。MMORPGでは回復行動もヘイトの増加につながるため、ヒーラーは回復のタイミングを慎重に選ぶことが必要です。タンク役はこうした事態を防ぐため、常に敵の注意を自分に向ける努力が求められます。ヒーラーとタンクの連携が重要と言えるでしょう。
「このボス、範囲攻撃でヘイトリセットするから気をつけて」
一部のMMORPGのボスは、特定のスキルでヘイト値をリセットすることがあります。このセリフは、ボスの範囲攻撃によってパーティー全体のヘイトがリセットされる場面での注意喚起です。ヘイトリセット後はタンク以外のキャラクターが狙われやすくなります。そのため、タンクは素早く再度ヘイトを稼ぐ必要があります。
MOBAやFPSでのヘイトの使い方
MOBAやFPSでのヘイトの使い方の例文を3つ紹介します。
- 「序盤から目立ちすぎて敵のヘイト買ってるわ…」
- 「味方タンクが前に出て、相手のヘイト引いてくれた」
- 「このスナイパー、毎回俺ばっか狙ってくる。完全にヘイト集めてる」
「序盤から目立ちすぎて敵のヘイト買ってるわ…」
MOBAやFPSでは、目立つ行動や連続キルをすると敵から強く警戒されることがあります。このセリフは、序盤から積極的に前に出たり、派手なプレイをしたプレイヤーが敵チームから執拗に狙われている状況です。ヘイトを集めすぎると集中攻撃の対象になるリスクが高まるため、時には控えめな行動やポジション取りを工夫することで生存率を高められるでしょう。状況判断と冷静な立ち回りが求められます。
「味方タンクが前に出て、相手のヘイト引いてくれた」
MOBAでは、タンクキャラクターが前線に立ち敵の攻撃を引き受けることで味方の負担を減らす役割を担います。このセリフは、味方タンクがうまく相手の注意を引き、チームの攻撃チャンスを作った場面を指しています。タンクが適切にヘイトを集めれば、後衛は安全に立ち回ることができ、試合ではタンクと後衛の連携が勝利の鍵になるでしょう。
「このスナイパー、毎回俺ばっか狙ってくる。完全にヘイト集めてる」
FPSでは、敵のスナイパーが特定プレイヤーを狙い続けるケースが見られます。このセリフは、試合の流れを変える強力なプレイヤーが敵に狙われやすい状況を示しています。集中攻撃を受けていると感じたら、安全なポジション取りや味方との連携を意識しましょう。チーム全体で対処することが重要です。
ヘイトがよく使われるゲーム5選

ヘイトの概念は多くのゲームで重要な要素です。ここでは、特にヘイト管理やヘイトコントロールの要素が特徴的な代表的タイトルを5つ紹介します。
- FINAL FANTASY XI
- モンスターハンターシリーズ
- ドラゴンクエストX
- エバースクエスト
- オーバーウォッチシリーズ
どれもプレイヤー間での連携や戦術においてヘイトの理解が不可欠です。これから始めるゲーム選びの参考にしてみてください。
FINAL FANTASY XI
FINAL FANTASY XIは、MMORPGの草分け的存在であり、パーティープレイでのヘイト管理が重視されています。タンクが敵の注意を集め、後衛が安全に行動するための役割分担が必須です。挑発や敵視を高めるスキルの使用が戦闘の基本となるでしょう。
モンスターハンターシリーズ
モンスターハンターシリーズは、巨大なモンスターとの狩猟を仲間と協力して行うアクションゲームです。攻撃や行動によってモンスターのターゲットが変化する独自のヘイトシステムを持っています。特定のプレイヤーが狙われやすくなることで、仲間が攻撃のチャンスを得る展開もあります。連携プレイと立ち回りの工夫が狩猟成功への近道と言えます。初心者から上級者まで長く楽しめるゲームです。
ドラゴンクエストX
ドラゴンクエストXは、国産MMORPGとして多くのプレイヤーに親しまれています。プレイヤーの行動によって敵のターゲットが変わるヘイトシステムが搭載されています。タンク職が敵のヘイトを集めることで、後衛の攻撃職や回復職が安全に役割を果たせる設計です。ダンジョンやボス戦では、事前のパーティー戦略とヘイト管理のバランスが求めら、仲間との連携がゲーム攻略のカギを握ると言えるでしょう。
エバースクエスト
エバースクエストは1999年にサービスが始まり、MMORPGの基礎を築いた名作です。敵を攻撃したり味方を回復することで、プレイヤーへのヘイト値が変動する仕組みがあります。タンクキャラが挑発スキルなどを活用し敵の注意を引き続ける必要があります。敵視の奪い合いが起こらないよう、チーム全体で役割分担と連携を取ることが攻略のコツです。
オーバーウォッチシリーズ
オーバーウォッチはFPSとMOBA要素を融合させた5対5のチーム対戦ゲームです。プレイヤーはタンク、ダメージ、サポートの3つの役割に分かれ、敵の行動を抑える戦術が求められます。タンクは前線で敵の攻撃を引き受けることで味方の行動範囲を広げます。ヘイトをうまく引きつけることでチーム全体の連携が安定し、シンプルながら奥深い戦略性を持ち、多くのプレイヤーに楽しまれているゲームです。
ヘイトを管理、操作する方法

ゲーム内でのヘイトは、ただ理解するだけでなく、どう扱うかが勝敗に直結します。
特にRPGやMMORPGでは、タンク・DPS・ヒーラーそれぞれが役割を果たすために、ヘイトの調整が欠かせません。ここでは、代表的なヘイト管理の方法を解説します。
挑発やヘイト上昇スキルを使う
タンクは「挑発」や「敵視上昇」系のスキルを駆使して、敵の攻撃を自分に集中させます。
これにより仲間が安全に火力を出したり回復したりできる環境を作れるのが大きな役割です。初心者でもスキル説明に「敵視を集める」とあれば、それがヘイト管理に直結するスキルだと理解しましょう。
火力を出しすぎないように調整する
DPSは大ダメージを与えることで一気にヘイトを稼いでしまうリスクがあります。
特にタンクがヘイトを固定する前に全力攻撃すると、敵が自分に向かってしまい、結果的にパーティ全体の危機を招きます。ヘイトバーや敵の挙動を見ながら、出力をコントロールすることが重要です。
回復量にも注意を払う
ヒーラーは攻撃していなくても、回復行動だけで大きくヘイトを稼ぎます。味方を一気に回復すると敵がこちらに向かってくるケースも多いです。
ヒールを分散したり、タンクが挑発を使ったタイミングに合わせることで、ヘイトが自分に集中するリスクを減らせます。
ヘイトリセットや分散を利用する
一部のゲームでは、特定のスキルや行動でヘイトをリセットしたり、分散できる仕組みがあります。
例えば「ステルス」「デバフ解除」などが該当します。こうしたスキルを有効に使うと、危険な状況を切り抜けたり、戦況を立て直すことが可能になります。
ヘイトの意味を誤解しないために理解しておくべきこと

ヘイトの誤解しやすいポイントを5つ解説します。
- 感情的な「嫌悪」とは異なる
- プレイヤーの行動で数値的に変動する
- 必ずしも「一番ダメージを与えた人」が狙われるとは限らない
- ゲームジャンルによって意味合いや使われ方が異なる
- プレイヤー同士の「人間関係」とは関係ない
感情的な「嫌悪」とは異なる
ゲーム内のヘイトは「敵からの注目度」や「ターゲット対象の優先順位」を意味します。一方で、英語のhateは憎しみや嫌悪という感情を表します。この違いを理解しておくことが重要です。ゲーム内でのヘイトは純粋な数値や行動による結果です。誤解せず戦闘時の戦略の一部として認識してください。
プレイヤーの行動で数値的に変動する
ゲームでは攻撃や回復といった行動によってヘイトの数値が上下します。例えば、タンクが挑発スキルを使用すれば敵の攻撃が集中します。回復役のプレイヤーも味方を回復することでヘイトを上昇させる場合があります。行動に応じて数値が変動する点がヘイトの特徴です。事前にヘイトの仕組みを把握しておくと安心でしょう。
必ずしも「一番ダメージを与えた人」が狙われるとは限らない
ヘイトは単純にダメージ量だけで決まるわけではありません。挑発スキルや特定のバフ・デバフでも変化します。つまり、火力職が多くのダメージを出していても、タンクがうまくヘイトを引きつけていれば狙われないこともあります。この点を理解することがパーティー戦闘では重要です。
ゲームジャンルによって意味合いや使われ方が異なる
MMORPGではヘイトは敵からの攻撃優先度を意味します。一方、MOBAやFPSでは敵チームが警戒して集中攻撃を仕掛ける対象になる行動を指すこともあります。同じ言葉でもゲームの種類によって役割やニュアンスが変わるため、自分がプレイしているタイトルの意味を知る必要があるでしょう。
プレイヤー同士の「人間関係」とは関係ない
ゲーム内でのヘイトはシステムによって自動的に決定される数値であり、プレイヤー同士のリアルな人間関係や感情とは無関係です。あくまで戦闘バランスを保つための仕組みとして存在します。過度に気にする必要はなく、安心して自分の役割を全うしましょう。
ゲームにおけるヘイトに関するQ&A

ゲームにおけるヘイトに関するQ&Aを11個紹介します。
Q:ヘイトってどういう意味?
A:ゲーム内のヘイトとは、敵から特定のキャラクターが攻撃対象と認識される状態を意味します。攻撃や回復などの行動で数値が増減します。タンクは意図的にヘイトを集めてパーティーを守る役割を担います。理解しておくと戦闘が楽になります。
Q:ヘイトを集めるメリットは?
A:タンクや前衛キャラが敵のヘイトを集めることで、味方の後衛やサポート職が安全に行動できます。敵の攻撃対象をコントロールすることでパーティーの安定感が増します。
Q:APEXで使われるヘイトとは?
A:APEXでは敵チームから意識的に集中攻撃やマークされることを「ヘイトを買う」と表現します。例えば連続キルや高い火力を出すプレイヤーは狙われやすくなります。敵からヘイトを集めると行動が制限される場合もあります。
Q:スプラトゥーンで使われるヘイトとは?
A:スプラトゥーンでは敵チームの注目や攻撃対象として狙われる状態を「ヘイトを集める」と言います。目立つ行動や相手陣地への積極的な侵入が原因です。ヘイトを利用して味方を援護する戦術も存在しています。
Q:桃鉄で使われるヘイトとは?
A:桃鉄では、プレイヤー同士の対戦で1人が資産や順位で大きくリードしているとヘイトを集めやすくなります。他のプレイヤーが妨害行動を集中させる状況を指します。ゲーム内では心理戦としての要素も強く働くでしょう。
Q:エバーテイルで使われるヘイトとは?
A:エバーテイルでは特定のキャラクターに敵の攻撃を集中させるための仕組みとしてヘイトがあります。タンクや前衛キャラにヘイトを集め、後衛のサポートキャラを守ります。ターン制バトルでの立ち回りに欠かせない概念です。
Q:ヘイトを下げる方法はある?
A:ゲームによっては「ヘイト減少スキル」や「インビジビリティ(透明化)」などの手段が用意されています。これを使うことで敵のターゲットから外れることが可能です。
Q:DPS職がヘイトを集めてしまったらどうすればいい?
A:火力職(DPS)が過度に攻撃してヘイトを集めた場合は、一時的に攻撃を控えるようにしましょう。また、タンクに敵視を戻してもらうまで立ち回りを調整します。無理に攻め続けると戦闘不能になるリスクがあります。
Q:MMORPGで「タンクはヘイト管理が大事」と言われるのはなぜ?
A:タンクはパーティーの盾役として敵の攻撃を自分に集中させる必要があります。タンクがヘイトを集めきれないと後衛や回復役が狙われ、全滅の原因になります。タンクのヘイトコントロールが攻略の要となるのはそのためです。
Q:ヘイトって数値で見える?
A:ゲームによっては画面上に敵視メーターやヘイトバーが表示される場合もあります。一方で可視化されないタイトルも存在します。そのため、経験や敵の行動パターンをもとに状況を判断することが求められます。
Q:ヘイトとアグロの違いは?
A:どちらも敵のターゲット選択を表す言葉ですが、MMORPGでは「ヘイト」が優先的に使用されます。一方、MOBAやFPSでは「アグロ」という表現が好まれる傾向があります。意味は似ていますが使われる場面に違いがあります。
ヘイトの理解を深めゲームスキルを伸ばしたい人はアフラスの無料体験へ!

ゲームにおけるヘイトとは、敵のターゲット選択や攻撃対象を決めるための重要な仕組みです。RPGやMMORPGではパーティー全体の戦略に影響を与えます。FPSやMOBAでも同様に、敵の集中攻撃を受けやすいプレイヤーに対して使われることがあります。ヘイトの概念を正しく理解することで、より高度な戦術やチームプレイが実現できるでしょう。
ゲームのスキルを本格的に伸ばしたいと考えている人には、eスポーツスクールのAFRAS(アフラス)をおすすめします。AFRASではプロ講師による丁寧な指導が受けられ、チームプレイや個人スキルの向上に役立つノウハウが学べます。eスポーツの世界で本気で上達を目指す人は、ぜひAFRASをチェックしてみてください。