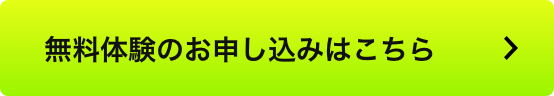昨今では、高齢者の健康維持にもテクノロジーが導入されており、高い効果を発揮しています。
代表的な例でいえば、eスポーツが高齢者の認知機能の維持・改善に効果があることから、導入する高齢者施設や自治体が現れています。
認知機能の維持・改善は高齢者施設や自治体にとって魅力的な一方で、馴染みの薄いeスポーツの導入を躊躇するケースは少なくありません。
今回はeスポーツを導入した高齢者施設や自治体の事例を紹介します。
eスポーツを新たな取り組みとして導入できれば、高齢者の健康だけでなく、豊富な選択肢を備えた施設や自治体になれます。
施設や自治体の取り組みに、eスポーツを検討している場合は、ぜひ本記事を参考にしてください。
この記事のコンテンツ
なぜいま高齢者とeスポーツが注目されているのか

近年、eスポーツは若者だけのものではなくなってきました。特に高齢者の間でも注目を集めており、各地でeスポーツを取り入れた取り組みが広がっています。
背景には少子高齢化や高齢者の孤立といった社会的課題があり、シニアeスポーツはその解決策としても期待されているのです。
ここでは、なぜ今、シニアとeスポーツの関係が社会的に注目されているのかを掘り下げていきます。
社会問題とシニアeスポーツの関係
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。
2025年には65歳以上の人口が約3,600万人に達するとされており、高齢者の健康寿命や生きがいが社会全体の課題になりつつあります。
このような中、eスポーツが高齢者の新たな「健康習慣」「社会参加の手段」として注目されているのです。
ゲームを通じて手先を使った操作や判断力を鍛えることができ、脳の活性化や認知症予防にもつながるという研究も出ています。
さらに、チームでの対戦やオンライン対話を通じて、人との交流が生まれる点も重要なポイントです。
従来の「テレビの前で座っているだけ」の生活から、能動的に関わるeスポーツは、介護予防・孤立防止・QOL(生活の質)向上にまで寄与するとして、行政や医療機関からの関心も高まっているのです。
世代を超えた新しい交流ツールとしての可能性
eスポーツがもたらすのは、健康面の効果だけではありません。それは、高齢者と若い世代を結ぶ架け橋としての可能性です。
たとえば、孫と一緒にゲームをプレイする祖父母、同じタイトルで競い合う親子、オンライン対戦で全国の仲間とつながるシニアなど、世代を超えた新しい交流の形がeスポーツを通じて生まれています。
実際、シニア向けのeスポーツ大会や施設では、若者がコーチ役として参加することもあり、一方通行ではない学び合いの関係が築かれている事例も増えています。
「デジタルは若者だけのもの」という思い込みを取り払うことで、高齢者が社会の一員として自信を持ち、若者も尊敬の気持ちを育む。eスポーツは、そんな双方向の価値を生み出すツールになり得るのです。
eスポーツを高齢者がおこなう効果

高齢者施設や自治体へのeスポーツ導入には明確な効果・メリットがあるため、導入事例は増えています。
本章ではeスポーツを高齢者がおこなう効果を解説します。
認知機能の維持・改善の健康的メリットがある
指先の細かい運動や注意力が必要な行動には、認知機能の維持・改善に効果があり、eスポーツは両方が満たせるアクティビティです。
実際に奈良県磯城郡川西町で、70歳前後の男女にeスポーツを週に1回実施してもらい、3カ月間続けたところ、以下の効果が確認されています。
- 軽度認知障害の疑いのあった6名中5名が回復
- 転倒リスクの値が改善
- 要介護・要支援リスクの値が改善
高齢者にeスポーツを楽しんでもらうことは相応のハードルがありませんが、上記のようにeスポーツ導入には確かな効果があります。
参考:eスポーツがシニア世代のフレイル予防に実証実験で見えてきた可能性
メンタルヘルスの改善
eスポーツを通じて、他者との交流や感情の起伏が生じるため、メンタルヘルスの改善にもつながります。
普段は交流の持てない相手や共通の話題が作りにくい家族とeスポーツを通じた交流ができるため、孤独感の解消や自己肯定感の向上が期待できます。
eスポーツには勝ち負けがあり、嬉しいや悔しいなど高齢者が普段の生活では生まれにくい感情の起伏が起きるため、活力や自信の源になります。
さまざまな効果から60歳以上限定のeスポーツ施設・教室がある
認知機能やメンタルヘルスへの効果があるため、昨今では60歳以上限定のeスポーツ施設・教室が生まれています。
兵庫県神戸市にある「ISR e-Sports」は、全国で初めてのシニア専用のeスポーツ施設です。
1日3部制・1部あたりの利用料金は平日1,000円と気軽に利用しやすい環境が整っています。
またゲームだけでなく、クールダウンタイムでは会員同士のコミュニケーションが取れる場も設けられており、憩いの場になっています。
参考:ISR e-Sports
eスポーツを取り入れた高齢者施設・自治体の導入事例

本章ではeスポーツを取り入れた高齢者施設・自治体の導入事例を解説します。
施設や自治体がどのような効果を期待して導入を目指したのか、実際の効果や導入時の課題が知れば、導入時の参考になります。
三重大学病院
三重県にある三重大学病院の認知症センターでは、適切な認知症の予防策としてeスポーツを取り入れています。
eスポーツを通して、人との触れ合いや一体感を感じることが脳への刺激となり、認知症への予防となるため、導入しています。
人生で初めてeスポーツをする方もいますが、周囲の方と一緒に取り組むことでプレイへのハードルが下がっているようです。
参考:eスポーツで楽しく認知機能の改善を目指す「脳活っ塾」 スタート!─認知症センターの新しい取り組み─
静岡県沼津市
医療法人友愛会は、静岡県沼津市にある医療施設や介護施設、老人ホームにレクリエーションのマンネリ化防止と認知症の予防を目的にeスポーツを導入しています。
各施設の利用者は、最初は「難しい」や「人前でゲームをするのが恥ずかしい」との声が出ていましたが、次第に楽しさを覚えて取り組んでいます。
複数の職員の参加が必須となるため、人員配置などを導入時の課題と挙げています。
参考:高齢者施設にeスポーツを導入することで見えてきた課題とメリット。地域連携のきっかけにも!-eスポーツ-
奈良県磯城郡川西町
奈良県磯城郡川西町では、シニア世代の運動実施率の低さを課題と捉えており、改善策の一環として、eスポーツを取り入れています。
14名の方に対して、3ヶ月間のeスポーツ教室を実施した結果、身体機能と認知機能の改善に効果があるとの効果が測定されました。
同町では中長期的にeスポーツを活用した事業を実施して、効果の検証を検討しています。
参考:奈良県川西町でのeスポーツを活用したフレイル予防事業において事業評価を実施
群馬県草津市
群馬県草津市でも他の県と同様に、認知機能やメンタルヘルスの改善を目的にeスポーツを導入しています。
eスポーツを活用したイベントの開催頻度は高くはありませんが、参加した高齢者からは軒並み高評価を得ているイベントです。
イベントに参加した方の7割が今後もeスポーツをしてみたいと回答しているため、同市では今後もeスポーツを活用した取り組みがあると考えてよいでしょう。
参考:令和6年度eスポーツ事業を紹介します!
埼玉県加須市
埼玉県加須市では、認知症やフレイルの予防にeスポーツが役立つのか検証をおこなっています。
同市の取り組みでは、平成国際大の教授の指導を受けながらおこなっており、参加者からは好反応が得られています。
同市と大学が検証した結果、eスポーツには高齢者の反応速度や認知機能の改善に効果があることが判明しました。
参考:「ぷよぷよ」が反応速度や認知機能を向上、埼玉・加須市でシニアのeスポーツ体験教室
eスポーツを高齢者施設・自治体に導入する際のポイント

施設や自治体にeスポーツを導入する場合、ゲーム機材を用意するだけではイベントは開けません。
ポイントを押さえて導入を進めなければ、継続的にeスポーツの利用したイベントを開催することを難しいでしょう。
本章ではeスポーツを高齢者施設・自治体に導入する際のポイントを解説します。
職員のゲームリテラシーを確認する
高齢者にeスポーツを楽しんでもらうためには、主催側の職員が一定のレベルでゲームを扱えなくてはいけません。
職員がゲームの操作に苦戦しているようでは、高齢者に楽しんで遊んでもらうことが難しくなるためです。
まずは職員が日頃からどの程度ゲームに触れているか、遊んでいるゲームはどのようなゲームかをヒアリングしましょう。
職員が導入を検討しているゲームを日頃から触れている場合には、特にテストプレイの時間を大きく取る必要はありません。
一方で職員がゲームに全く触れていない場合には、テストプレイの時間を多くとる、ゲームリテラシーの高い職員と配置換えをするなど対策が必要です。
定着に向けて体制を整える
eスポーツの活用した催しを定期的に開催するために、体制を整えることは重要です。
具体的には、eスポーツのイベントに対応できる職員のシフト調整、イベント時の担当を固定してより習熟度を高めてもらうなど組織内の体制を整えます。
eスポーツの活用したイベントを単発で開催することはできても、定期的に開催するのは簡単ではありません。
対応できる職員のスケジュール調整や高齢者に継続して楽しんでもらう工夫を凝らすのが難しいため、単発開催になりがちになります。
利用者の適切な目標管理をおこなう
eスポーツを継続する中で、勘の良い高齢者は上達を繰り返すため、同じレベルを設定していると飽きが生まれます。
高齢者のチャレンジ精神を刺激しつつ、飽きさせないバランスの良い目標設定が、長くeスポーツを楽しんでもらう秘訣になります。
高い得点や高難易度の他にも、異なるモードへのチャレンジや縛りプレイも高齢者に飽きさせないアプローチとなるでしょう。
eスポーツに興味を示さない利用者への配慮を怠らない
eスポーツに興味を持ってチャレンジする方もいれば、eスポーツに興味を示さない方もいます。
イベント中は、eスポーツに興味のない方が置いてけぼりにならないように配慮しましょう。
たとえば、eスポーツを楽しまなくとも一緒に利用者を応援する、近くの利用者と会話のきっかけを作るなど疎外感を生まないようにします。
eスポーツのイベントをしている時間帯が、eスポーツに興味のない方にとって、つまらない時間帯にならないようにしましょう。
高齢者におすすめのeスポーツゲームとは?

eスポーツというと「反射神経が必要で難しそう」「若者向け」というイメージを持たれがちですが、実は高齢者でも安心して楽しめるタイトルが数多く存在します。ここでは、身体的負担が少なく、楽しみながら脳を使える、高齢者に特におすすめのeスポーツゲームを4つのジャンル別にご紹介します。
直感で遊べる!リズム・音楽ゲーム【例:太鼓の達人】
リズムに合わせてボタンを叩くだけの音楽ゲームは、複雑な操作が不要で、初めての人でも入りやすいジャンルです。
「太鼓の達人」は、音に合わせてドン・カッと打つだけというシンプルなルールで、反射神経だけでなく、音感やリズム感も鍛えられる点が特徴です。実際に、介護施設や高齢者向けのeスポーツ体験会でも導入されることが多く、自然と笑顔になるゲームとして人気があります。
頭を使って勝負!パズル・対戦型思考ゲーム【例:ぷよぷよ】
eスポーツは“戦う”だけではありません。思考力や先読み力を駆使する「ぷよぷよ」などのパズルゲームも立派なeスポーツジャンルです。
ブロックを積んで連鎖を狙うルールは、シンプルながら奥深く、脳のトレーニングにも最適。反射神経よりも計画性や集中力が問われるため、高齢者にとっても親しみやすいゲームです。
家族と一緒に盛り上がれる!パーティーゲーム【例:マリオカート】
「孫と一緒にゲームがしたい」というニーズに応えるなら、パーティーゲームやレースゲームがぴったりです。特に「マリオカート」などは、カジュアルに遊べる上に、操作が簡単で視覚的にも楽しいので、家族間のコミュニケーションツールとしても活躍します。
負けても楽しい、わかりやすい、という点でストレスが少なく、初めてのeスポーツ体験にもおすすめです。
体を動かして健康維持!フィットネス型ゲーム【例:リングフィットアドベンチャー】
eスポーツの中には、体を使ってプレイする「アクティブゲーム」もあります。「リングフィットアドベンチャー」や「Fit Boxing」などは、軽い運動とゲーム性が組み合わさったフィットネス系タイトル。
高齢者でも無理のない範囲でプレイでき、運動不足の解消やリハビリとしての活用事例も増えています。ゲーム感覚で身体を動かせるのは、楽しみながら継続できるという点で非常に効果的です。
eスポーツを高齢者施設・自治体に導入する手順
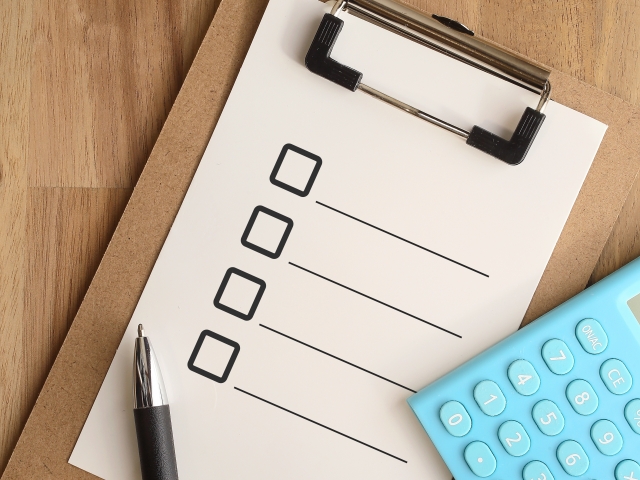
eスポーツを高齢者施設や自治体に導入するメリットは理解できた一方で、どのように導入を進めればよいのかわからない方は多いでしょう。
本章ではeスポーツを高齢者施設・自治体に導入するための手順を解説します。
職員への教育・資格取得を推進する
eスポーツを活用したイベントは職員が主催のため、職員への教育からスタートします。
eスポーツを活用することで、具体的にどのようなメリットが得られるのか、ゲームをする上で気をつけることなどを確認しましょう。 昨今ではレクリエーション担当やイベント企画スタッフを対象にした以下の資格があり、eスポーツの安全な導入方法や機材の基礎知識が学べます。
- 健康ゲーム指導士
- eスポーツ実務検定
本格的な実施に合わせて、資格取得を奨励するのもよいでしょう。
eスポーツの種類を決める
eスポーツと一言でいっても多種多様にあるため、どのタイトルに取り組むかを決めましょう。
施設の規模や参加者の健康状態、興味の対象、お子さん・お孫さんの有無などを勘案しながら、決めることが求められます。
たとえば、施設の規模が大きく、参加者の健康状態が良ければ、リングフィット・アドベンチャーやNintendo Switch Sportsなどがよいでしょう。
反対に施設の規模が小さく、運動が難しい参加者が多い場合には世界のアソビ大全51や太鼓の達人など、手軽に遊べるタイトルがおすすめです。
取り組むタイトルにより、必要な機材や準備も変わることから、早めに決めた方がよいでしょう。
必要機材の導入をおこなう
eスポーツの種類が決まったら、必要なハードやコントローラーを購入します。
イベントを開催する部屋にモニターがない場合は、プロジェクターに移すのもよいでしょう。
必要となる機材は主に以下になります。
- ゲーム機の本体
- コントローラー
- モニターorプロジェクター
- プロジェクターの投影機
- ゲーム機の本体とモニターorプロジェクターをつなぐケーブル
スケジュールの作成
eスポーツを活用したイベントには対応する職員の調整が必要になるため、スケジュールを作成しましょう。
資格を持っている職員やゲームリテラシーの高い職員が参加できるように調整します。
まずは週1回のスケジュールを組んでみて、参加する利用者数や利用者からのニーズにあわせて変えていきます。
職員だけでプレ開催する
機材やスケジュール作成ができたら、まずは職員だけでイベントを開催してみましょう。
開催してみると、段取りの問題やゲームが起動するまで何をするか、ルール説明の仕方など具体的な課題が見えてきます。
課題は解決策を提示し合いながら、本番に向けて精度を高めていきます。
eスポーツを高齢者施設・自治体に導入する際の注意点

eスポーツの導入はメリットが多く魅力的な一方で、導入には思わぬ注意点があります。
本章ではeスポーツを高齢者施設・自治体に導入する際の注意点を解説します。
ゲームの利用にゲーム会社の許諾が必要になるケースがある
施設や自治体でのゲームの利用は私的利用とは異なり、商用利用と捉えられる可能性があります。
ゲームを商用利用する場合には、ゲーム会社・発売元の許諾が必要な場合があります。
昨今では、ゲームイベントやゲーム配信など商用利用が目立つため、各ゲーム会社や発売元が商用利用に関するガイドラインを発表しています。
利用するゲームのガイドラインを確認して、必要に応じてゲーム会社の許諾を取るようにしましょう。
高齢者のeスポーツに関するよくある質問(FAQ)

高齢者がeスポーツを始めるにあたっては、「本当にできるの?」「機材は?」「一人でも大丈夫?」など、さまざまな疑問があるかもしれません。ここでは、実際によく寄せられる3つの質問とその答えをまとめました。不安を解消し、第一歩を踏み出すための参考にしてください。
Q1:ゲーム初心者でも本当にeスポーツを楽しめますか?
はい、大丈夫です。高齢者向けに選ばれたeスポーツゲームは、操作がシンプルで直感的に遊べるものが中心です。最初はスタッフや家族のサポートを受けながらでも問題ありません。大切なのは「勝ち負け」よりも「楽しむこと」なので、経験や年齢に関係なく始められます。
Q2:視力や反応速度に不安がある場合でも大丈夫?
もちろんです。eスポーツには反射神経を問われないパズルや思考型のゲーム、リズムゲームなども多数あります。また、画面の拡大設定や音量調整、入力スピードの調整などアクセシビリティへの配慮が進んでおり、無理なくプレイできます。
Q3:自宅でもeスポーツを始められますか?
はい、家庭用ゲーム機(Nintendo SwitchやPlayStationなど)やPCがあれば、自宅でも十分に楽しめます。最近ではオンラインでつながる「シニア向けeスポーツクラブ」や、無料体験できるプログラムも増えているため、最初の一歩としてもおすすめです。ネット環境が不安な場合は、まずはオフラインで遊べるゲームから始めるのも良いでしょう。
eスポーツに挑戦したいシニアの方はアフラスの無料体験へ!
今回はeスポーツを導入した高齢者施設や自治体の事例を紹介しました。
高齢者がeスポーツに取り組む健康的なメリットは大きく、高齢者施設や自治体でeスポーツ導入の動きが広がっています。
eスポーツスクールのAFRAS(アフラス)では、シニアの方も生徒として通っています。マンツーマン指導で、孫とプレイできるようになりたい方、認知症予防をされたい方など、様々な方が通っています。
eスポーツに興味があるシニアの方は、ぜひAFRASをチェックしてみてください。