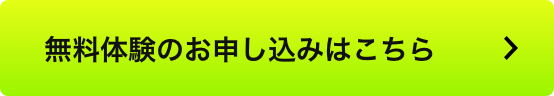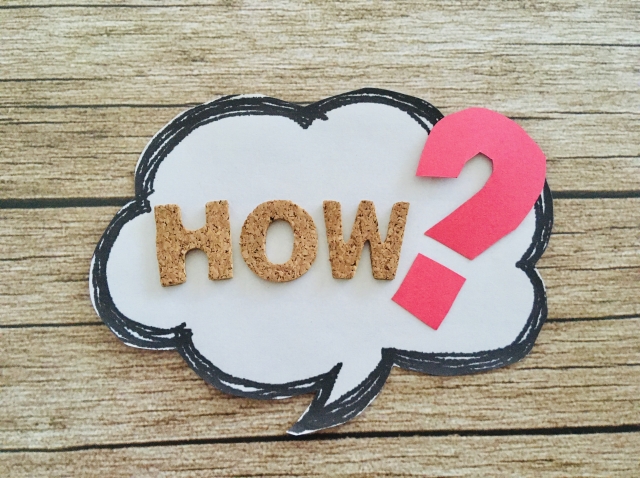ゲームをしていると、さまざまな専門用語を耳にする機会があります。MMORPGやFPS、ハクスラ系のタイトルで近年よく聞かれるのが「DPS」という言葉です。
DPSは、ゲームジャンルによってさまざまな意味を持つため「結局どういう意味の言葉なの?」と混乱してしまう人もいるでしょう。
今回はDPSの基本的な意味やジャンル別の意味を詳しく解説します。合わせて、ゲームをより楽しむために知っておくべきゲーム用語も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事のコンテンツ
ゲームにおけるDPSとは何のこと?

ゲーム用語として用いられる「DPS」はDamage Per Secondの略称です。1秒あたりに与えるダメージを表す言葉として使われます。
つまりDPS値100の武器には、1秒間に100ダメージを与える性能があるということです。ただし、DPSの表示方法はゲームタイトルによって異なることがあり、2秒間に200ダメージを与える武器も10秒間に1000ダメージを与える武器もDPS値は100として表されることがある点に注意しておきましょう。
DPSはゲームにおいて効率的に攻撃できる武器を知るため、火力を表す指数として使われています。
ゲームジャンル別のDPSの意味

一般的には攻撃力を表す指数として用いられるDPSですが、ゲームジャンルによっては異なる意味で使われることもあります。ゲームジャンルごとのDPSの意味を知っておかなければ、思わぬ勘違いや会話の行き違いが生まれてしまうこともあるため注意しましょう。
【VALORANT・APEX・FORTNITEなど】FPS、TPSにおけるDPSの意味
FPSやTPSにおけるDPSは、武器の性能を表す指標として表されることが多いです。
異なる武器を同じ条件で使用した場合に、1秒間に与えられるダメージを表しているため、多くの人はDPS値の高い武器を選ぶ傾向にあるでしょう。これらの指標によって武器の強さをランキング付けしていることもあり、FPSにおいて重要な指標です。
ただし、DPS値が高ければ良い武器かといえば、そうとも言いきれません。FPSにおけるDPS値の重要度については記事の後半で解説します。
【FF14・ラグナロクオンライン・原神など】MMORPG・ハクスラにおけるDPSの意味
FPSでは武器の攻撃性能を表す指標として用いられるDPSですが、MMORPG(多人数参加型のオンラインRPG)やハスクラ(ハック&スラッシュゲーム)などのジャンルにおいては、異なる意味を持つことがあります。
職業(ロール)を意味するDPS
MMORPGやハスクラ系のタイトルでは、ゲーム内における役割を「職業(ロール)」と呼ぶことがあります。ヒーラーやアタッカーなど、さまざまな職業があり、どの職業を選ぶかによって求められる役割が変わるということです。
多人数でパーティを組んでゲームを進めるMMORPGでは、特に顕著に見られ、パーティで目的を達成するために職業に徹することを求められるシーンも少なくありません。
MMORPGやハスクラでは、相手に与える相対的ダメージ量が高い職業をDPSとして表すことがあります。特定の職業(ロール)のみが扱える武器や魔法、スキルなどを踏まえ、同条件で戦闘を行った際に相手に与える相対的ダメージ量をもってDPSとして示していることが多いです。
ただし、職業(ロール)によっては後方支援に特化したものも存在するため、DPS職だからといって、必ずしも有用であるとは限りません。
PT(パーティー)効率を意味するDPS
MMORPGやハスクラなどのジャンルでは、個人ではなくパーティー全体の総合的な相手に与える相対的ダメージ量をDPSとして表すこともあります。多人数でパーティーを組んで目的達成を目指すMMORPGでは、パーティーのDPSも非常に重要な指標のひとつです。
しかし、DPSが高いだけのパーティーでは、特殊な魔法攻撃に弱かったり、弱体化魔法などを扱う敵に苦戦したりすることもあるでしょう。後方支援とのバランスを考えて、DPSも含めたパーティー構成を考えることが重要です。
【Dota2・League of Legendsなど】MOBAにおけるDPS
MOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)におけるDPSは、最も相手に与えるダメージ量が高いキャラクターを表すことがあります。「DPSキャラクター」と呼ばれることもあり、DPSキャラクターを主軸として、攻撃陣形を組むことも珍しくありません。
戦略が勝敗の鍵を握るMOBAでは、DPSキャラクターをどこに配置するのかが非常に重要となります。DPSキャラクターの弱点である防御力の低さを他キャラクターで上手くカバーしながら、敵陣を切り開く必要があるため、戦略を考える際によく使われる言葉です。
ゲームジャンル別のDPSの重要性

ゲームジャンルによってDPSの役割や重要性は異なります。ここでは、MMORPG・MOBA・FPSという代表的な3つのジャンルに分けてみました。
- MMORPGにおけるDPS|役割分担が明確な中での火力の価値
- MOBAにおけるDPS|キャリーとしての責任と成長性
- FPSにおけるDPS|瞬間火力と立ち回りの両立がカギ
それぞれのDPSの特性やチーム内での役割を見ていきましょう。
MMORPGにおけるDPS|役割分担が明確な中での火力の価値
MMORPGでは、タンク・ヒーラー・DPSの三役が明確に分かれており、DPSは主に敵への火力を担当します。ボス戦や高難度レイドでは、DPSチェック(一定時間内に削り切る必要があるギミック)が存在することもあり、全体の火力水準がクリア成否に直結します。
また、装備やスキル回しの最適化が求められるジャンルでもあり、「どれだけ効率よくダメージを出せるか」がそのまま貢献度となるのが特徴です。
MOBAにおけるDPS|キャリーとしての責任と成長性
MOBA系ゲーム(例:LoLやDota2)では、DPS職はゲームが進むにつれて火力が大きく成長する「キャリー」役として扱われることが多いです。序盤はサポートやタンクに守られながら育成し、中盤以降でチームを勝利に導く役割を果たします。
そのため、ポジショニングや装備選択、タイミング判断が極めて重要。一度ミスするとゲームの流れを一気に崩してしまうリスクもあるため、責任感のある役割ともいえます。
FPSにおけるDPS|瞬間火力と立ち回りの両立がカギ
FPSでは、明確に「DPS職」が設定されているわけではありませんが、使用する武器や役割によって実質的にDPSが求められるポジションが存在します。
例えばApex Legendsでは、前線を張る突撃役(レイスやオクタンなど)が瞬間的な火力を出す立場になります。重要なのは「いかに被弾を抑えつつ、高火力を叩き込むか」。エイム力はもちろん、立ち回りの上手さと瞬間的な判断力がDPSの価値を左右します。
DPSを高めるための5つのポイント|初心者が火力を伸ばすコツ

「どうやったらもっとDPSを出せるの?」と悩んでいる方は多いはず。DPSは武器やキャラの性能だけでなく、プレイヤーの動き方ひとつで大きく変化します。ここでは、初心者でもすぐに意識できる「DPSを高めるためのコツ」を5つ紹介します。
- スキル回しを最適化する
- 攻撃チャンスを逃さない立ち回り
- バフ・デバフを活用する
- 被弾を減らして攻撃時間を確保する
- パーティ全体の流れを意識する
どれも意識次第で確実に改善できる要素なので、ぜひ参考にしてみてください。
スキル回しを最適化する
DPSを伸ばすうえで最も基本かつ重要なのが、「スキル回し」です。どのスキルをどの順番で、どんなタイミングで使うかによって、秒間ダメージは大きく変わります。
クールダウンが終わっているのにスキルを温存したり、効果的なバフスキルを使い忘れたりすると、DPSは一気に低下します。まずは自分のキャラのスキル構成をしっかり理解し、最も効率的な順番とタイミングでスキルを発動できるよう意識しましょう。DPS職なら、常に何かしらの攻撃が出ている状態を保てるのが理想です。
攻撃チャンスを逃さない立ち回り
DPSを出せるタイミングというのは、戦闘中ずっと続いているわけではありません。敵の攻撃が激しい場面では回避や防御を優先せざるを得ないこともありますが、それ以外の“安全なタイミング”にしっかりと手数を稼げるかが重要です。
「まだ攻撃できたのに距離を取っていた」「無意味に回避を連発していた」など、小さな判断ミスの積み重ねがDPSの差につながります。無駄な動きを減らし、敵の行動パターンを覚えることで、攻撃チャンスを的確に掴めるようになります。
バフ・デバフを活用する
ゲームによっては、味方の火力を上げる「バフ」や、敵の防御力を下げる“デバフ”がDPSに大きな影響を与えることがあります。自分で使えるバフスキルを活用するのはもちろん、パーティメンバーの支援に合わせて大技をぶつけるシナジーの意識も大切です。
また、敵に対して防御ダウン系のデバフを継続的に維持するだけでも、全体のDPSが底上げされます。バフやデバフは見逃されがちな要素ですが、しっかり使いこなせば手数を増やさずにDPSを上げる強力な手段となります。
被弾を減らして攻撃時間を確保する
DPSを高く保つには、「どれだけ攻撃し続けられるか」が重要です。そのためには、敵の攻撃を避ける・受けないこともDPS向上の鍵となります。
無理に攻撃して被弾し、回復行動やダウンで手数が減れば、トータルDPSは大きく落ち込みます。被弾しない=攻撃を続けられるということ。これは単純なようで非常に大事なポイントです。
敵のモーションを見て先回りで動く、カメラ視点を調整して周囲を常に把握しておくなど、丁寧な操作がDPSの安定につながります。
パーティ全体の流れを意識する
ソロプレイでは自己完結できても、パーティ戦では「DPSを出しやすい状況を仲間と一緒に作る」ことが必要です。
タンクが敵の向きを固定してくれているときに側面攻撃を狙う、ヒーラーがバフをかけたタイミングで大技を叩き込むなど、連携がうまく取れるとDPSが劇的に向上します。
また、敵のデバフを味方と交代で維持したり、無駄なヘイトを取らないように調整することも、結果的に火力アップに貢献します。自分の数字だけでなく、パーティ全体の流れを読むことが、真のDPS職に必要なスキルです。
DPSはプレイヤー環境でも変わる?ハード面の重要性に注目

DPSはスキル回しや操作精度などプレイヤーの実力によって左右されますが、実はそれを支える操作環境=ハード面も非常に重要な要素です。
マウスやモニター、ネット回線、さらには椅子やデスクの高さに至るまで、あらゆる要素がDPSに間接的な影響を与えています。
- マウス・キーボードの応答速度で差が出る
- 高リフレッシュモニターがDPSを変える理由
- ネット回線が不安定だとDPSは伸びない
- 姿勢・椅子・デスク環境も集中力とDPSに直結
ここでは、DPSを安定して出すために意識したい上記のハード面のポイントを紹介します。
マウス・キーボードの応答速度で差が出る
DPSは“攻撃の手数”が鍵です。そのため、攻撃ボタンやスキル発動を担当するマウスやキーボードの性能は非常に重要。反応の遅いデバイスや押し心地の悪いキーを使っていると、わずかな遅れや押し間違いが生じやすくなり、結果的にDPSを落としてしまいます。
とくにFPSやアクション性の高いゲームでは、ワンテンポ遅れるだけで勝敗が変わることも。クリック感やキー配置、無線・有線の選択など、自分の手に合った操作デバイスを選ぶことがDPS安定の第一歩です。
高リフレッシュモニターがDPSを変える理由
ゲームの映像が滑らかに表示されるかどうかは、モニターのリフレッシュレートによって決まります。60Hzのモニターでは1秒間に60コマ表示されますが、144Hzや240Hzのモニターでは動きがより細かく描写され、**敵の動作や攻撃エフェクトを早く・正確に捉えることができます。**この違いは攻撃のタイミングや回避の判断に直結し、結果として手数や生存率が増える=DPSが伸びるという結果につながります。特にAIMが重要なゲームでは、滑らかな描写が大きな差を生みます。
ネット回線が不安定だとDPSは伸びない
どんなに上手く操作していても、ラグや回線落ちが起きればDPSどころではありません。オンラインゲームでは、回線の安定性やPing値(遅延)が攻撃・回避の反応速度に大きく影響します。
Wi-Fiよりも有線接続の方が安定しやすく、プレイ中のラグも抑えられます。また、他の家族が動画を見たりアップロードしていたりする場合、それだけでも回線が重くなりDPSに影響が出ることも。DPS職としてパフォーマンスを安定させるなら、通信環境の見直しは必須です。
姿勢・椅子・デスク環境も集中力とDPSに直結
意外と見落とされがちですが、姿勢や座り心地の良し悪しもDPSに影響します。猫背になったり、視線が合わなかったりすると、長時間の集中が途切れやすく、操作ミスや判断ミスが増えます。
ゲーミングチェアやモニターアームを活用して、自分にとって疲れにくい姿勢を作ることは、パフォーマンス維持の大きな支えになります。また、デスクの高さやマウスの置き場にもこだわると、操作の正確さや反応速度が向上し、自然とDPSも安定して高くなっていきます。
DPSに影響するハード一覧表
| 項目 | 影響内容 |
|---|---|
| マウス・キーボード・コントローラー | 操作性・反応速度に直結。ラグや押しにくさでミス増加=DPS低下 |
| モニター(リフレッシュレート) | 敵の動きやエフェクトがなめらかに見えることで、判断力がUP |
| ゲーミングチェア・デスクの高さ | 長時間プレイの集中力や姿勢に関与。疲労によるDPS低下を防ぐ |
| ネット回線(Ping・安定性) | 遅延やラグでスキル入力がずれたり、敵の攻撃を見逃すことも |
| PCスペック/FPS安定性 | 画面がカクつくと反応できず、精密な操作が困難=DPSに直結 |
環境については下記で詳しく解説していますので、そちらもぜひご覧ください。
小学生のためのゲーミングPC入門ガイド!初めてのグラフィックボード選びとeスポーツへの第一歩
DPSを理解することで得られるメリット

DPSという概念を深く理解することで、ゲームプレイにおいて得られるメリットは多岐にわたります。
たとえば、
- 役割理解が深まり、PTプレイで貢献できる
- 自分のダメージ効率を可視化できる
- 戦闘中の判断力・立ち回りが向上する
- 他職との相性や戦略の理解が広がる
といった点が挙げられます。以下では、それぞれのメリットを詳しく解説していきます。
役割理解が深まり、PTプレイで貢献できる
DPSを正しく理解することは、チーム戦における自分の「役割」を明確にする第一歩です。単に火力を出せば良いのではなく、いつ・どこで・どの相手に最大ダメージを与えるかを判断することが、パーティ全体の勝率向上につながります。
DPSが敵を効率よく削ることで、タンクやヒーラーの負担も軽減され、全体の戦術がスムーズに機能します。役割を理解し、自分の行動に責任を持つことで、チームの中で信頼されるプレイヤーになれるでしょう。
自分のダメージ効率を可視化できる
DPSの数値は、自分が1秒あたりにどれだけのダメージを出しているかを示す明確な指標です。これにより、スキルの使い方や装備の選択、スキル回しの効率などが数値として見えるようになります。
例えば、同じキャラでもスキルの順番を変えるだけでDPSが大きく変わることがあります。ダメージ効率を定量的に把握できることで、自分のプレイを客観的に見直し、改善につなげられるのが大きなメリットです。
戦闘中の判断力・立ち回りが向上する
高DPSを出すには、単純な火力だけでなく、的確な立ち位置やタイミングの判断が必要です。例えば、攻撃を避けつつも常に火力を出し続けるためには、状況判断力と冷静な操作が求められます。
DPSの概念を理解してプレイすることで、自然と「いつ攻撃すべきか」「どこに位置取るべきか」を意識するようになり、戦闘中の立ち回りが格段に向上します。これはPvPでもPvEでも通じる大切なスキルです。
他職との相性や戦略の理解が広がる
DPSを知ることは、他の役割――例えばタンクやヒーラーの視点を理解するうえでも重要です。たとえば、タンクが敵のヘイトを集める間に、DPSが後方から火力を出すのが基本の構図。DPSとしてどう動けばタンクが安定し、ヒーラーの負担を減らせるかを考えられるようになります。
結果として、パーティ全体の戦略性が向上し、他職へのリスペクトも芽生えます。職業ごとの強みや連携の重要性を実感することで、より奥深いゲーム体験ができるでしょう。
【例文】DPSの使い方
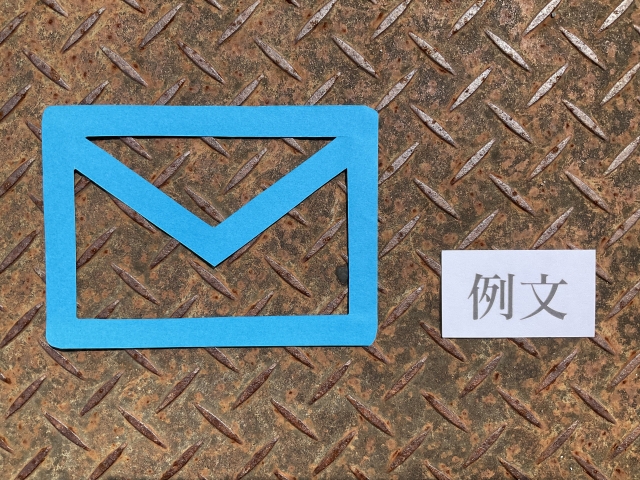
ゲーム用語として用いられるDPSですが、以下のように使われることが多いです。
「Aの武器のDPSは200、Bの武器はDPS100だから、Aの武器の方がDPS効率が高い」
(Aの武器が1秒間に与えられるダメージは200、Bの武器が1秒間に与えられるダメージは100であるため、Aの武器の方が攻撃時の火力が高いという意味)
「パーティーのDPS効率を重視したいならAの職業が良い」
(パーティー(チーム)の相対的ダメージ量の高さを優先して職業を選びたいのであれば、攻撃の火力が強いAの職業を選ぶと良いという意味)
「前衛はタンク、後衛は近接系DPSでパーティーの組もう」
(前衛には守備に特化したタンクという職業のキャラクターを配置し、後衛には近接系の職業でDPS値の高いキャラクターを配置したパーティー(チーム)を作ろうという意味)
DPSは使う対象やシーンによって異なる意味を持つことを理解しておきましょう。
DPSが高ければゲームは有利なのか?

DPSについて理解してくると「取り敢えずDPS値の高い武器やDPS職業を選んでおけばゲームを有利に進められる」と勘違いしてしまう人も少なくありません。
これらの考え方について完全に間違いであるとは言いませんが、ゲームシステムはそこまで単純にできている訳ではないことも事実です。
続いては、ゲームにおけるDPSの考え方について紹介します。
「武器のDPSが高い=強い」という訳ではない
FPSやTPSにおいて、武器のDPSは重要な指標のひとつです。火力の高い武器を使うほど、相手に与えるダメージは大きくなりますし、少ない攻撃で早く相手のダメージを奪うことはFPS・TPSにおいて特に重要なことでしょう。
しかし、DPSが高いからといって、その攻撃は必中ではないことを念頭に置いておく必要があります。いくら1秒間に与える攻撃力が高くても、攻撃が当たらなければ相手にダメージを与えることができないのです。
例えば、2秒に1発の攻撃ができ10秒に1000のダメージを与えられる武器があったとします。この場合、DPSは100ですが、1撃が与えるダメージは200です。エイムスキルが高く、1撃必中できるのであれば攻撃の効率が高いと言えるでしょう。一方、エイムスキルが低く2秒に1度しかできない攻撃を当てられないとなると、相手にダメージを与えることはできません。
エイムスキルが低いのであれば、同じDPS100の武器でも0.1秒で10のダメージを与えながら地道に相手のダメージを削れる武器の方が効率的だと言えます。素早く攻撃の手数を増やすことでジワジワと相手を追い詰めることも可能です。
FPSやTPSにおいて、DPSはあくまで1秒間の攻撃力を示しているだけであり、必ず与えられるダメージ数値ではないことを理解しておきましょう。、自分自身のスキルと照らし合わせたうえで検討することが重要です。
DPS効率の高さと数値の高さは比例しないことがある
MMORPGやハスクラ系のジャンルにおいてパーティのDPS効率は重要です。しかし、DPS効率を高めようとするあまりに、パーティー内にDPS職ばかりを置いてしまっては、かえって効率を下げてしまうこともあるでしょう。
DPS職を配置することでパーティーの火力は底上げされます。しかし、火力ばかりが強くても守備力が弱ければ相手を倒す前に、自陣が全滅してしまう可能性もあるでしょう。
守備力の高いキャラクターや有効攻撃が可能な属性の職業、補助系職業などを敢えて加えることで、DPSが最大化することも珍しくありません。
DPSのよくある勘違い|「数値だけ」を信じるのは危険!

DPSについて調べていると、「高ければ強い」「低ければ使えない」といったイメージを持ってしまいがちです。しかし実際には、DPSはプレイヤーのスキルや状況によって大きく変動する「実測値」です。ここでは、DPSにまつわるよくある勘違いを4つ紹介します。
- 勘違い①:DPSは武器やキャラの固定値
- 勘違い②:DPSが高ければ勝てる
- 勘違い③:DPSが出ないのは武器のせい
- 勘違い④:サポート職にはDPSは関係ない
それぞれ詳しく解説していきましょう。
勘違い①:DPSは武器やキャラの固定値
「この武器のDPSは○○」「このキャラはDPSが低い」といった言い方を耳にすることがありますが、DPSは「設定値」ではなく「結果値」です。
正確には「この武器は高DPSを出しやすい性能を持つ」「このキャラは理論上高いDPSを出せる」という意味であり、実際にその数値が出るかどうかはプレイヤー次第。
同じ武器を使っても、操作やタイミングによってDPSは大きく変わります。したがって、DPSは性能そのものではなく、「実際のプレイ結果」として出るものだと認識することが大切です。
勘違い②:DPSが高ければ勝てる
DPSが高いことはもちろん強さの一要素ですが、それだけで勝てるとは限りません。たとえば、攻撃ばかりに集中して回避を怠ると、被弾が増えてダウンしたり、パーティ全体に迷惑をかけることになります。
また、敵との相性や戦場の状況によっては、安全に立ち回ることを優先すべき場面も多いです。DPSは「火力」という面では目安になりますが、ゲームで勝利するためには、立ち回り、連携、状況判断といった総合的なスキルが不可欠です。
勘違い③:DPSが出ないのは武器のせい
「この武器、思ったよりDPS出ないんだけど…」という声はよく聞きますが、原因が武器の性能にあるとは限りません。
むしろ、プレイヤーの操作ミスやタイミングのズレによって、火力を十分に発揮できていないケースの方が多いです。たとえば、クールダウンの管理を怠って強スキルの回転が落ちていたり、無駄な回避行動で手数が減っていたり。
武器のポテンシャルを引き出せるかどうかは、自分の使い方にかかっています。DPSが低いと感じたら、まずは自分の動きを見直すのが上達の近道です。
勘違い④:サポート職にはDPSは関係ない
ヒーラーやバッファーといったサポート職は、DPSとは無縁だと考えられがちですが、実はそうとも言い切れません。
DPS職の火力を最大限に引き出すには、バフのタイミング、回復の維持、敵のデバフ管理など、サポート側の働きが極めて重要になります。さらに、自身も隙を見て攻撃に参加することで、全体のダメージ量に貢献できることも。
DPSは「数字の競い合い」ではなく、「パーティ全体でどれだけダメージを稼げるか」という視点が重要です。サポート職こそ、DPSに深く関わる存在と言えるでしょう。
知っておくべきゲーム用語

今回はDPSについて詳しく紹介しましたが、他にも知っておくとよいさまざまなゲーム用語があります。最後に、さまざまなジャンルで頻繁に使われるメジャーなゲーム用語を紹介します。
HPS
HPS(Heals Per Second)の略称。1秒あたりのダメージ回復量。サポートキャラクターがその能力によって味方を回復させるパーティーの回復効率を示す。
DOT
DOT(Damage Over Time)の略称。一定時間において継続的に与えられる攻撃ダメージの量。毒・炎上・氷結など、継続的にダメージを負う状態異常攻撃によるダメージを示す。
バフ・デバフ
ステータスを向上させる効果を「バフ」、ステータスを弱体化させる効果を「デバフ」という。アイテムの効果や魔法効果、武器効果などに用いられることか多い。
バフ・デバフについては下記で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
デバフとは?意味や効果、バフとの違いを初心者にもわかりやすく解説
ヘイト
敵キャラクターに敵対心を持たれる数。防御職などがヘイトを集めることで、攻撃職がアクションしやすい状況を作りやすくなる。MMORPGなどで使われることが多いゲーム用語。
ナーフ
システムアップデートによって武器が弱体化してしまう現象を指す。ゲームバランスを保つために、アップデートによって武器の性能を弱体化させることはFPS、TPSなどでよく見られる。
ナーフについては下記で詳しく解説しています。併せて是非ご覧ください。
ゲーム用語のナーフ(Nerf)とは?デバフとの違いや実装される理由なども詳しく紹介
DPSについてよくある質問(FAQ)
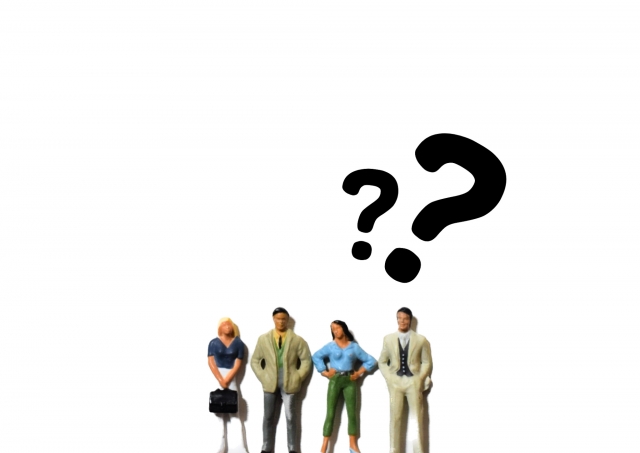
DPSについて調べていると、初心者を中心にさまざまな疑問が浮かぶことがあります。ここでは、特に多く寄せられる質問に対して、わかりやすく回答していきます。
Q:DPSが高い=強いというわけではないの?
必ずしもDPSが高いからといって、そのキャラクターやプレイヤーが「強い」とは限りません。高DPSを出せる環境が整っているか、サポートやタンクとの連携がうまくいっているかなど、状況によってDPSは大きく変動します。また、火力だけでなく、生存力・判断力・チーム貢献度なども重要な評価ポイントとなるため、単純な数値だけで強さを判断するのは早計です。
Q:初心者におすすめのDPSキャラは?
ゲームによって異なりますが、初心者には操作がシンプルで火力を出しやすいDPSキャラがおすすめです。たとえばMMORPGであれば遠距離魔法職、FPSなら反動の少ない武器を持つ中距離タイプなどが該当します。複雑なコンボや瞬時の判断を求められないキャラから始めることで、立ち回りや火力の出し方に徐々に慣れていけるでしょう。
Q:DPSは英語圏でも通じる略語?
はい、DPS(Damage Per Second)は英語圏でも広く通じる略語です。海外のゲーマーや攻略サイトでも「DPS」という表現は一般的に使われており、国際的なゲーム用語のひとつといえます。ただし、文脈によっては「DPS=火力職」なのか「ダメージ効率の単位」なのかを明確にする必要があります。略語として通じても、使い方の違いには注意が必要です。
ゲーム用語の意味を理解して円滑にコミュニケーションをとろう
ゲーム用語への理解が求められる理由として、オンラインゲームの爆発的人気が挙げられます。ボイスチャットなどでコミュニケーションを取りながら行うオンラインゲームでは、伝えた言葉を正しく理解してもらえなければ、意思疎通ができずプレイに影響を及ぼしてしまうことでしょう。
ゲーム用語の意味を正しく理解しておけば、円滑なコミュニケーションが可能になります。ぜひ、今回紹介したゲーム用語を覚えて、よりゲームを楽しんでください。
AFRAS(アフラス)はゲームを学べるeスポーツスクールです。本気でeスポーツをしたい人からゲーム初心者まで、レベルに合った指導を受けられます。塾や大人の習い事のように、ゲームを学び、その魅力を体感してみませんか?ゲームを学びたい方は、ぜひアフラスの無料体験レッスンにお越しください!