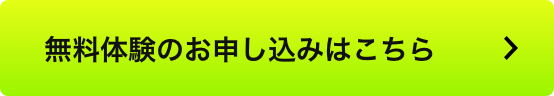かつて「ゲームは若者のもの」と思われていた時代は、もう過去の話です。
近年、eスポーツを楽しむ高齢者が全国で増えており、注目を集めています。自治体や介護施設がシニア向けeスポーツイベントを開催するケースも多く、「太鼓の達人」や「ぷよぷよ」といったゲームで盛り上がる様子はテレビやSNSでも話題になっています。
「なぜ高齢者がeスポーツに?」と不思議に思うかもしれません。しかし、eスポーツには認知機能の活性化や介護予防効果、さらには孤立の解消や生きがいづくりにもつながる可能性があるのです。
この記事では、eスポーツが高齢者にもたらすメリットや実際の取り組み事例、おすすめゲーム、導入時の注意点までをわかりやすく解説します。高齢者の新たな趣味・交流のカタチとして広がるeスポーツの魅力を、ぜひ一緒に探ってみましょう。
参照:東京市町村自治調査会・地域課題の解決に向けたeスポーツの可能性に関する調査研究報告書
この記事のコンテンツ
なぜ高齢者のeスポーツが注目されているのか?

「eスポーツ」と聞くと、若者が競技性の高いゲームで腕を競い合う姿を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし近年では、そのイメージが大きく変わりつつあります。eスポーツを楽しむ高齢者が増加し、全国の介護施設や地域イベントでもシニアeスポーツが取り入れられるようになっています。
この動きが注目されている背景には、高齢化社会の進行や健康寿命延伸への取り組み、デジタル技術の進化といった複数の要因が関係しています。ここでは、なぜ今「高齢者とeスポーツ」が注目されているのかを深掘りしていきましょう。
高齢者の間でeスポーツが普及し始めた背景
日本では高齢化が急速に進み、65歳以上の人口は全体の約3割を占めるまでになりました。この中で注目されているのが、「身体的な負担が少なく、かつ知的・社会的刺激が得られるアクティビティ」としてのeスポーツの可能性です。
さらに、スマートフォンやタブレットの普及により、高齢者がデジタルに触れる機会が増えたことも後押しになっています。かつてはゲームに馴染みのなかった世代が、孫と遊ぶことをきっかけにゲームに触れ、そこから本格的なeスポーツ体験へとステップアップするケースも増えています。
また、地方自治体や企業、NPO団体が主導する「ねんりんピック」や「eスポーツ大会」などのイベントも増え、高齢者が気軽に参加できる場が整いつつあるのも、大きな要因の一つです。
高齢者にとってのeスポーツの魅力とは
高齢者にとってのeスポーツの魅力は、単なる「暇つぶし」や「娯楽」にとどまりません。第一に挙げられるのは、頭と体を同時に使うことで脳を活性化させる効果が期待できる点です。たとえば「ぷよぷよ」や「太鼓の達人」などのゲームは、集中力・判断力・リズム感などを自然に鍛えることができます。
また、仲間と楽しむ要素も重要です。個人で黙々とプレイするだけでなく、チームで協力したり、対戦したりするゲーム体験は、自然と笑顔や会話を生み、孤独感の解消や社会参加の促進にもつながります。
加えて、ゲームの中で「上達する喜び」や「大会で結果を出す達成感」を味わえることも、日常生活にハリをもたらす要因となっています。まさにeスポーツは、高齢者の生活の質(QOL)を高める新しいツールとして期待されているのです。
高齢者にeスポーツがもたらす驚きの効果とは?

eスポーツは単なる娯楽にとどまらず、高齢者の心身に良い影響を与えるツールとしても注目されています。最新の研究や実証実験からは下記の効果が報告されています。
ここでは、それぞれの効果について具体的な事例やデータを交えながら紹介していきます。
- 認知機能の改善効果
- 介護予防やうつ予防にも効果的
- 高齢者の社会的孤立を防ぐ
認知機能の改善効果
eスポーツが高齢者の注意力や判断力、記憶力の維持・改善に効果があるとする報告が複数存在します。たとえば、宮城県仙台市が実施した実証実験では、レーシングゲーム「グランツーリスモ」を使った高齢者向けのプログラムにより、注意分割能力(複数の情報に同時に注意を向ける能力)に改善傾向が見られたと報告されています。
こうした成果は、単なる体験型イベントにとどまらず、ゲームが脳機能を維持・向上させるツールとして有効である可能性を示しています。
参考:朝日新聞デジタル「高齢者がeスポーツで脳活性化 仙台で実証実験」
介護予防やうつ予防にも効果的
eスポーツには身体的な負担が少ない一方で、脳や心に刺激を与える特性があります。操作を覚える楽しさや、勝敗による感情の起伏が、脳の活性化だけでなく、日常の意欲向上にもつながっています。
奈良県川西町での取り組みでは、eスポーツに継続的に参加した高齢者のうち、軽度認知障害(MCI)の疑いがあった方の症状が改善したという結果も報告されています
さらに、eスポーツは「勝ちたい」「続けたい」といった目標志向の行動を引き出すことができるため、うつや無気力状態の予防にもつながると考えられています。
高齢者の社会的孤立を防ぐ
高齢者にとって、社会とのつながりを持ち続けることは非常に重要です。eスポーツは、対戦形式や協力プレイなどを通じて、自然なコミュニケーションの場を提供します。
たとえば、eスポーツ施設「REDEE」が高齢者施設で行ったイベントでは、最高95歳の参加者も交えてゲームを楽しみ、スタッフや他の利用者と積極的に会話する姿が見られたそうです
このような体験は、社会的孤立の予防だけでなく、自尊心の回復や心の安定にも寄与します。また、孫や子どもとの共通の話題ができることで、世代間交流にもつながるという副次的なメリットも見逃せません。
参考:毎日新聞「高齢者がeスポーツ 生きがい作り、認知症予防に」
実際にeスポーツを取り入れている高齢者施設・自治体事例

高齢者とeスポーツの組み合わせは、もはや一部の試みではありません。
現在、全国各地の自治体や福祉施設が積極的に取り入れており、その成果や反響もメディアを通じて注目を集めています。
ここでは、特にユニークで先進的な4つの取り組みをご紹介します。
横浜市富岡東地域ケアプラザ
神奈川県横浜市の「富岡東地域ケアプラザ」では、地域の高齢者向けにeスポーツを活用した健康促進イベントを定期的に開催しています。
使用するのは、Nintendo Switchのボウリングやリズム系ゲームなどで、ゲームを通じた体の動きや集中力の向上が期待されており、参加者からは「身体が軽くなった」「気持ちが前向きになった」といった声が上がっています。
名古屋市緑生涯学習センター
名古屋市の緑生涯学習センターでは、シニア向けにeスポーツを体験できる講座を実施しています。
初心者でも取り組みやすいように、職員が操作のサポートを行いながら、楽しく参加できる雰囲気づくりを重視。プレイ後には、仲間とのおしゃべりや笑顔も多く、社会的交流の場としても効果を発揮しています。
秋田県「マタギスナイパーズ」
秋田県では、地元の高齢者を中心としたeスポーツチーム「マタギスナイパーズ」が結成され、全国的にも話題を集めました。平均年齢は70歳超。メンバーはFPS(シューティングゲーム)を本格的にプレイしており、地域活性化や生きがいづくりのモデルケースとして注目されています。
この取り組みは、eスポーツが年齢に関係なくチャレンジできる文化であることを象徴しており、全国のシニア世代に勇気と希望を与えています。
参考:Yahoo!ニュース「秋田発!高齢者eスポーツチーム“マタギスナイパーズ」
参考:久保田隆二【三沢市議会議員】・高齢者のeスポーツチーム 全国初、秋田の企業が設立へ
鳥取県「ねんりんピック」
高齢者のスポーツと文化交流の祭典「ねんりんピック」にも、2023年からeスポーツが正式種目として採用されました。鳥取県ではこの全国大会に向けて、各地域でeスポーツの予選大会を開催し、60歳以上の参加者が熱戦を繰り広げました。
この取り組みは、高齢者が競技としてeスポーツに取り組む時代の到来を象徴するものとなっています。単なるレクリエーションではなく、目標に向かって取り組むことが生きがいや自己肯定感につながっているという声も多く聞かれます。
参考:鳥取市・【アンケート結果】ねんりんピックはばたけ鳥取2024鳥取市交流大会eスポーツ体験会について
高齢者におすすめのeスポーツタイトルと選び方のポイント

高齢者がeスポーツを楽しむためには、無理なく続けられるゲーム選びが何より大切です。近年は高齢者向けに開発されたタイトルや、世代を問わず楽しめる直感的なゲームも増えてきました。
ここでは、初心者でも取り組みやすく、心と体の健康に良い影響をもたらすおすすめジャンルと、その選び方のコツをご紹介します。
リズム・パズル・レーシングなど直感操作のゲームが人気
操作がシンプルで、視覚的にも分かりやすいリズムゲームやパズルゲーム、レーシングゲームは、eスポーツ初心者の高齢者にぴったりです。
具体的には下記のゲームです。
- リズムゲーム(例:太鼓の達人)
手や体を動かしながらテンポに合わせることで、運動機能の維持と脳の活性化に効果的。
- パズルゲーム(例:ぷよぷよ・テトリス)
ブロックの整理や消去を考えることで、認知機能のトレーニングに。
- レーシングゲーム(例:マリオカート)
反射神経や空間認識力を楽しく鍛えることができ、集中力アップに役立ちます。
このようなゲームはプレイしているうちに自然と笑顔が増え、楽しさと達成感の両方が得られるのが特徴です。
複雑な操作が不要なゲームを選ぶコツ
高齢者にとって、ボタン操作やルールが複雑すぎるゲームはストレスの原因になることも。だからこそ、以下のようなポイントを押さえてゲームを選ぶと安心です。
- コントローラーの操作が少ないもの
直感的に動かせるNintendo Switchなどの「モーション操作」対応ゲームはおすすめ。
- 短時間で遊べるゲーム
長時間集中する必要がないため、体力に不安がある方でも無理なく楽しめる。
- チュートリアルや説明が充実しているもの
画面に大きな文字が表示され、音声ガイドなどがあれば、初めてでも安心です。
このように、「操作のしやすさ」「遊びやすさ」「見やすさ」を意識することで、長く楽しくプレイを続けられます。
交流・対戦できるゲームはモチベーション維持に役立つ
eスポーツの大きな魅力の一つが、「人とつながること」です。高齢者が参加できるeスポーツタイトルの中でも、他の人と対戦・協力できるタイプは、社会的つながりを育み、孤立防止にもつながるとされています。
具体的には下記のゲームです。
- ボンバーマンR オンライン
シンプルな爆弾アクションながら、複数人での対戦が可能。家族や友人と盛り上がれる。
- スイカゲーム(話題のシンプル対戦パズル)
ルールが簡単で、大人も子どもも楽しめる。世代を越えた交流にも最適。
- Wii Sports / Nintendo Switch Sports
テニスやボウリングなどのゲームで、身体を動かしながら一緒に楽しめるのが魅力。
このような交流を促進するゲームは、楽しみの中に「つながり」や「仲間意識」が芽生えるため、継続意欲が高まる傾向にあります。
高齢者にeスポーツを導入する際の課題とその対策

eスポーツは高齢者にさまざまなメリットをもたらしますが、導入にはいくつかのハードルがあるのも事実です。とくに以下の3点です。
- 機器操作への不安と対策
- 継続してもらうための工夫
- 高齢者が安心して楽しめる環境整備
ここではこれらの課題に対してどのように向き合い、無理なくeスポーツを取り入れることができるのかを具体的に見ていきましょう。
機器操作への不安と対策
高齢者にとって、ゲーム機やコントローラーの操作は「難しそう」「間違えたら壊れそう」という不安の種になりがちです。
しかし、以下のような工夫でこの不安は大きく和らげることができます。
- 操作説明を動画やイラストでわかりやすく
文章だけでなく、視覚的な説明を用意することで理解度が大きくアップ。
- マンツーマンのサポート体制を整える
家族やスタッフが横について操作を一緒に体験することで、安心感が生まれる。
- ボタンが少ない、直感的な操作が可能なゲーム機を選ぶ
たとえばNintendo Switchやタブレット端末などは、高齢者にも比較的なじみやすい。
初めの一歩を「楽しい」と感じてもらえれば、次第に自分から「やってみたい」と言ってくれることも多いです。
継続してもらうための工夫
どんなに楽しくても、「三日坊主」で終わってしまってはもったいないですよね。高齢者がeスポーツを長く楽しむためには、日常のなかで“習慣化”する工夫が大切です。
- 決まった曜日・時間に開催する
生活リズムの一部として定着しやすくなる。
- スコアや成績を記録して成長を実感できるようにする
小さな達成感が継続のモチベーションに。
- 他の参加者との「つながり」を重視する
一人ではなく、誰かと一緒に楽しむことで“待ち遠しい時間”になる。
また、季節イベントやチーム戦などのゲーム外の楽しさを演出することも、継続率アップに大きく貢献します。
高齢者が安心して楽しめる環境整備
心身の負担を軽減し、安心してeスポーツを楽しんでもらうには、周囲の環境づくりがとても大切です。
- 椅子や画面の高さを調整し、無理のない姿勢でプレイできるようにする
長時間座っても疲れにくく、身体にやさしい。
- 部屋の明るさや音量、温度管理など細かな配慮
とくに視力や聴力に不安のある方への対応として重要。
- プレイ中に適度な休憩時間を挟むルールを設ける
疲れをためずに、毎回リフレッシュした状態で参加できる。
また、「失敗してもOK」という空気感も、安心感のある環境づくりには欠かせません。
「うまくできなくても、みんなで楽しめればOK!」というスタンスが、高齢者の笑顔と意欲を引き出します。
eスポーツは高齢者の未来を変える新たな文化に!

かつて「若者の遊び」と思われていたeスポーツが、今や高齢者の生活を大きく変えるツールとして注目されています。
ゲームを通じて健康を維持し、生きがいを感じ、そして人とのつながりを楽しむ。そんな新しいライフスタイルが、いま少しずつ広がりはじめています。
eスポーツは単なる趣味にとどまらず、健康促進・社会参加・幸福感の向上といった面で、高齢社会における強力な味方となる可能性を秘めています。
健康・生きがい・交流の三拍子がそろう
eスポーツには、高齢者がより豊かに暮らすための要素が自然と含まれています。
- 健康:脳を使いながら、時には体も動かし、楽しく機能維持ができる
- 生きがい:勝敗やスコアに一喜一憂する楽しさが、毎日の張り合いになる
- 交流:世代や地域を超えた人とのつながりが生まれ、孤立を防げる
これらがそろったeスポーツは、まさに高齢者にとっての“次世代の健康文化”と言えるかもしれません。
今後のeスポーツと高齢者社会の展望
今後、eスポーツは高齢者福祉や地域づくりにますます活用されていくと予想されます。
介護予防やリハビリとの連携
→ すでに介護施設でeスポーツを導入する例も増加中。今後は医療分野とも連携が進む可能性。
高齢者向け大会やイベントの拡充
→ 「ねんりんピック」や地方大会のような活動が、全国的に広がる見込み。
「高齢者eスポーツインストラクター」の育成
→ プレイヤーにとどまらず、サポートや指導役としての新しい働き方も生まれてくるかもしれません。
少子高齢化が進む日本において、「高齢者×eスポーツ」は社会全体を元気にする可能性を秘めた、次なる希望のカタチなのです。
家庭や地域でできる小さな第一歩から始めよう
eスポーツの導入は、大掛かりな準備がなくても始められます。
- 家族でテレビゲームを一緒に楽しむ
- 地域の公民館や集会所でミニゲーム大会を開く
- 高齢者向けのスマホゲームを勧めてみる
といった、身近でできる「小さな一歩」が、大きな変化のきっかけになります。
最初は「ゲームなんて無理」と言っていた方が、いつの間にか笑顔でプレイしていた——そんな光景が各地で生まれつつあります。
eスポーツが高齢者にとっての「新たな文化」として根づいていけば、未来の高齢社会はもっと明るく、もっと楽しくなるはずです。
eスポーツは高齢者の人生をもっと豊かにする新たな選択肢!アフラスの無料体験へ
高齢者がeスポーツに親しむことで得られる恩恵は、決して一過性のブームではありません。認知機能の維持や介護予防、生きがいの創出、人とのつながりといった、これからの時代に欠かせない価値が詰まっています。
地域や施設、家庭のなかで少しずつ広まりつつある「高齢者×eスポーツ」という新しい文化。これは、これからの高齢社会を支えるポジティブな選択肢として、より多くの人に広がっていくことでしょう。
eスポーツを通じて、いきいきとした毎日をはじめてみませんか?
「ゲームなんてやったことないから…」と思う方も、まずは触れてみることが第一歩です。
操作方法からルールまで丁寧に教えてくれるAFRAS(アフラス)はスキル、知略、戦法を学ぶ事ができるeスポーツスクールです。
「ゲームの世界で、新しい仲間と、新しい自分に出会える」そんな未来が、すぐそこに広がっています。