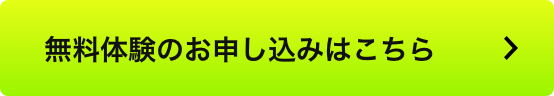近年、eスポーツは世界的な盛り上がりを見せており、世界の競技人口は約1億人を超えるとも試算されています。これはスポーツとしては異例の記録であり、世界的に競技人口が多いと言われるゴルフの競技人口は6,500万人、野球は3,500万人程です。
日本はeスポーツへの参入が世界から遅れてしまったこともあり、近年ようやくプロeスポーツ選手が「職業」として知られるようになってきました。しかし、すでに世界の先進国ではプロゴルファーやプロ野球選手のように、地位や尊敬を集める職業として認められています。
世界に大きな影響を及ぼす可能性をもつeスポーツを用いて、地方創生を図る自治体も増えてきました。eスポーツによる地方創生への影響は大きく、世界の事例と共に論文なども発表されています。
この記事では、eスポーツが地方創生に与える影響について解説します。合わせて、地方創生の成功事例についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
eスポーツとは?

eスポーツとは、Electronic Sportsの略称です。コンピューターゲームを用いて勝敗を競うスポーツであり、国際大会なども開催されています。
コンピューターゲーム機には、パソコンゲームやPlayStation、Nintendo Switchなどの家庭用ゲーム機の他、スマートフォンのアプリなども含まれるのが特徴です。
体を動かさないため「eスポーツはスポーツではない」などと言われることもありますが、ワールドカップの開催やアジア競技大会での正式種目化、2027年には国際オリンピック委員会が主催する「オリンピック・eスポーツ・ゲームズ」が開催されるなど、eスポーツをスポーツ競技として認める風潮が強まっています。
eスポーツが地方創生に活用されているって本当?

一見すると全く関係がないように思われるeスポーツと地方創生の関係。しかし、世界各国や国内でも、すでにeスポーツによるさまざまな施策が行われ大きな成果を上げています。
世界で観れば、eスポーツによる政策に成功している国としてサウジアラビアが挙げられます。国策としてeスポーツ振興を支援することで、さまざまな効果が既に得られており、世界ではeスポーツ興行の最も重要な国という位置づけを得つつあります。
また、国内においても多くの地方自治体がeスポーツを活用した施策を実施しており、さまざまな成果が報告されています。
気になる方は興味深い論文も発表されているため、チェックしてみてはいかがでしょうか。
eスポーツが地方創生に及ぼす6つの影響

続いては、eスポーツが地方創生に与える可能性の高い6つの影響について解説します。
1.経済への影響
eスポーツが地方創生に与える影響のなかで、特に注目されるのが経済効果です。eスポーツでは、他のスポーツと同じく興行収益が見込めます。
大会を行い集客に成功すれば、近隣宿泊施設や商業施設などにおいて大きな収益が期待できるでしょう。コンピューターゲームを用いるという点から「大会といっても会場でモニターを見ているだけでしょう?他のスポーツに比べて臨場感がなく、自宅からネット配信を見ているのと同じなのでは」という意見もあります。
こればかりは、実際にeスポーツの大会を観戦した人にしか理解し難いでしょうが、大きな会場で選手のプレイに興奮し歓声を上げる観客の熱気や盛り上がりは、他のスポーツと比べても引けをとりません。会場まで足を運びたいというeスポーツファンは、決して少なくないでしょう。特に、国際大会の誘致に成功すれば、世界各国から多くの観戦者が足を運びます。
実際に2025年に北海道で開催されたAPEXの世界大会は34,000人を動員しました。
また、ショッピングモールなどでもeスポーツ関連のイベントが開催されることがありますが、大人から子供まで興味を引きやすいeスポーツは、集客に効果的です。親子連れや孫に連れられてきた高齢者など、幅広い年代へのアプローチが可能なことから、多様な業種での経済効果が見込めます。
2.高齢者福祉への影響
eスポーツによる認知能力の向上効果は、世界中でさまざまな論文によって立証されつつあります。これは、子供だけでなく大人、ひいては高齢者にも当てはまると考えられるでしょう。
高齢者がeスポーツに取り組むことで、認知機能の改善や孤立防止の効果も期待されます。近年、高齢者福祉施設や自治体による高齢者向けの取り組みでもeスポーツを活用する事例が増えており、今後も高齢者福祉へのeスポーツ活用は増加していくでしょう。
3.地域交流への影響
eスポーツと聞くと、ターゲット層がZ世代(1996年生まれ~2012年生まれ位の人々)と思われがちです。確かに、競技人口はデジタルネイティブとされるZ世代の割合が高く、若年層の選手が世界で活躍していることも事実です。
しかし、地方創生に活用する場合はこれに限りません。Z世代を主軸として若年層、高齢層などへのアプローチも可能なため、通常なら生まれにくい世代間の交流も深める効果が期待できるでしょう。
高齢者のなかには、eスポーツの取り組みに参加したことで、孫との交流が増えたという声も聞かれるようです。違う年代との交流が深まることで、地域のなかでも交流を持てる幅が大きく広がるでしょう。地域交流が深まることは、地域への愛着形成や孤立防止などに高い効果が期待できます。
特に、高齢化が進む地域では、地域の伝承や管理が高齢者だけで完結しがちです。eスポーツを通じて世代間の交流を図ることで、地方自治などに参加する若年層の増加を促す効果も期待できるでしょう。
4.若年層への影響
eスポーツの若年層に対する人気の高さを活用すれば、地方都市に若者を呼び込むことも可能でしょう。特に、高齢化が進む地域では、若年層の取り込みが大きな課題のひとつとなります。
自治体が主導となってeスポーツを活用した取り組みを行うことで、都市から地方へと若者を呼び込む効果が期待できます。
5.観光への影響
観光業からもeスポーツの有用性は注目されており、地域資源をeスポーツにかけ合わせることで新たな観光資源を創出する事例も聞かれます。地域産業を活かしたeスポーツイベントを開催し観光地を作ることも可能ですし、季節によって観光客が増減するようなスキー場や海水浴場などで、オフシーズンに季節を関係なく楽しめるeスポーツ関連イベントを開催して観光客を呼び込むこともできるでしょう。
6.地方企業への影響
eスポーツは地方企業のブランディング化や新規事業の創出にも大きな影響が見込まれます。敢えて、地域企業を主軸にしてeスポーツイベントを開催することで、新たな事業の創出や企業のブランディング化が可能となるでしょう。
地方企業のブランディング化や新規事業の創出は、雇用の拡大など、地方の発展に大きく関係する重要な課題です。
eスポーツによる地方創生の成功事例

すでに日本国内でもeスポーツを地方創生に活用する動きが見られます。続いては、実際に行われたeスポーツによる地方創生の成功事例についてみていきましょう。
青森県の事例
青森県 七戸町民文化祭では、数年前からeスポーツブースを開設し人気を博しています。比較的高齢者世代の来場が多いイベントという事もあり、体感的に楽しめる「太鼓の達人」や「ぷよぷよ」などのタイトルを起用しており、幅広い年代の人がeスポーツを体験しました。
同イベントでは「太鼓の達人」公式公認大会を青森県内で初開催するなど、ファンの集客にも成功しています。
茨城県の事例
茨城県では、県を上げて国内初となる国体(国民スポーツ大会)の文化プログラムにeスポーツを採用する取り組みを行いました。「全国都道府県対応eスポーツ選手権 2019 IBARAKI」として開催された同大会は、大きな盛り上がりを見せ、以降は毎年開催地を変えて行われています。
小学生から高齢者まで、幅広い年代が都道府県代表選手としてステージに立てるようイベント設計を行い、世代間交流や地域経済の活性化などの効果が見られます。
埼玉県の事例
埼玉県では、所沢市、春日部市、熊谷市の3自治体が合同で「SAITAMA e-sports リンクフェス 2025 Spring」を開催しました。競技タイトルとして「Fortnite」「eFootball」「バーチャルサイクリング」を起用し、複数の会場を生中継で繋いで同時開催する、珍しい手法にも注目されています。
特に、Fortniteとバーチャルサイクリングでは、川越や秩父を再現したオリジナルマップを作成し、地域の魅力発信などを行っています。
群馬県の事例
群馬県では、県内に本工場を構えるSUBARUと連携して人気のカーレーシングタイトル「GRAN TURISMO SPORT」で競技する「Gunma Tomo eSports CUP」を開催。同イベントはSUBARU工場内で開催されました。同イベントでは、就労継続支援B型事業所が協力し、自治体と民間企業、障害者福祉施設が関わった珍しい例と言えるでしょう。
自治体と民間企業との地域連携を高め、障害者福祉にも貢献した事例です。
全国の空家問題を解消する「ゲーミングハウス事業」にも注目

地方創生を目指す自治体で多く聞かれるのが人口の減少に伴う空家問題です。そんな空家をリノベーションし、eスポーツ仕様にしたゲーミングハウスを賃貸として提供する事業も注目を集めています。
インターネットがあれば全国のどこからでもプレイ可能なeスポーツの特性を活かし、空家をゲーマー仕様にすることで、若年層に対する訴求が可能です。
また、環境を良くすることでプロチームの誘致なども行いやすくなるでしょう。空家問題とeスポーツ活用の両方をクリアできる施策として、多くの自治体が注目しています。
eスポーツの地方創生に挑戦するならアフラスへ!
大都市には快適な環境が整いやすく、その分人口も増えやすいのは当たり前です。大きな会社ができれば雇用が充実し、就労のために多くの人が移住してきます。
その分、地方では経済が低迷し人口の流出が止められず、徐々に若年層が減り高齢者ばかりの自治体になってしまいます。そんな地方の状況を改善するためにも、eスポーツは無限の可能性をもつ施策と言えるでしょう。
ゲームができる環境さえあれば、身体能力や年齢に関わらずフェアに競うことができるeスポーツは、高齢化が進む日本にとって最適なスポーツとも言えます。ぜひ、eスポーツの可能性を再確認し、地方創生に役立ててみてください。
AFRAS(アフラス)はeスポーツについて学べるゲーミングスクールです。地方創生にeスポーツを活用したいと思っていても、eスポーツに対する正確な知識がなければ難しいでしょう。安易に施策に盛り込めば、返って高齢者層などからの反発を受けてしまう可能性も高いです。
プロのeスポーツ講師に指導を受けて、eスポーツを実際に体験することで、リアルな魅力を発信できるようになります。eスポーツを学んでみたいという方は、ぜひAFRASをご検討ください。