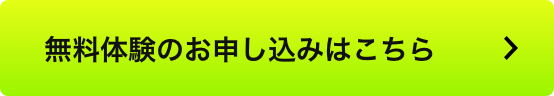近年、Z世代を中心にプレイ人口が増加しているeスポーツ。コンピューターゲームを用いることから「ただゲームで遊んでいるだけでは?」なんと思われる方もいるでしょう。
しかし、eスポーツをスポーツとして取り組むことで、プレイヤーの意識は変わり、今や教育機関などでも部活動として取り組むケースが増えています。
そんなeスポーツが、不登校に悩む子供や引きこもりになってしまっている人に対する支援の一環として活用されていることをご存じでしょうか。
この記事では、eスポーツが不登校・引きこもり支援に活用される理由や実情、注意点などを詳しく解説します。
- 子どもが不登校で悩んでいる保護者
- 家族の引きこもりを改善したいと考えている人
- これからeスポーツによる不登校・引きこもり支援を受けることを検討している人
上記に当てはまる方は、ぜひ記事を最後まで読んでみてください。
この記事のコンテンツ
eスポーツが不登校・引きこもり支援に活用されている

さまざまな理由で学生が学校へ登校できない・しない状況に陥る「不登校」。文部科学省は令和6年10月時点で、全国の不登校児童数が小・中学校で約34万6,000人、高校で約6万9,000人にのぼると発表しました。
また、KHJ全国ひきこもり家族連合会は、2023年4月に発表した声明にて、全国の引きこもり人口を推計146万人としています。失業や休職をきっかけに引きこもりになってしまったという人も多く、全体の約7割の人は「今の自分を変えたい」と考えているなど、引きこもりを改善したいという意思はあっても、なかなか上手くいかないという実情が大きな話題となりました。
そんな不登校や引きこもりの人の社会復帰支援の一環としてeスポーツが活用されていることをご存じでしょうか。コンピューターゲームを用いて勝敗を競うeスポーツを通して、社会復帰を目指す取り組みが全国で広がっています。
参照:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知):文部科学省/「ひきこもり」全国推計146万人 50人に1人 内閣府調査を受けたKHJの見解 – 特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会
eスポーツが不登校・引きこもり支援に効果的と考えられる理由

不登校や引きこもりの支援にeスポーツが活用されるのには、いくつかの理由があります。続いては、eスポーツが不登校や引きこもり支援に役立つと考えられる理由を解説します。
外出の動機付けになるから
eスポーツはコンピューターゲームを用いて行うスポーツのため、自宅でも行えます。しかし、支援に用いる場合は外部の施設などにeスポーツ環境を整えたうえで取り組みを行うケースがほとんどです。
特に、チームプレイが求められるタイトルでは、オンラインでコミュニケーションをとるよりも実際に同じ空間でプレイした方がスムーズなコミュニケーションがとれる場合も少なくありません。
「今日はeスポーツの日だから行こうかな」という子供や「同じゲーム好きの人なのであれば、交流しても苦痛や負担が少ない」という人も少なくありません。自分の好きな分野であり、同じ趣味を持つ人が集まる環境だからこそ、外出の動機付けになると考えられます。
協調性と社会性を育むから
eスポーツは、ソロプレイ(1人プレイ)のタイトルもあれば、チームプレイのタイトルもあります。しかし、多くの場合メジャーなeスポーツタイトルとして採用されているのはチームプレイのものです。
3~5人ほどでチームを組んで勝敗を競うタイトルが多く、チームメイトと適切なコミュニケーションをとれなければ勝利を掴むことはできないでしょう。
そこで、相手の思考を想像したり自分の意志を伝えたりする必要が出てくるため、自然と協調性や社会性が育まれます。もちろん、当人達は「eスポーツで勝ちたいから」という理由で取り組んでいるため、学びに対して強制される感覚や精神的な負担は抑えられるでしょう。
不登校児や引きこもりの人の多くは、社会性や協調性に対する自信が損なわれてしまい、他人との交流を忌避する傾向にあります。eスポーツを通して、まずは同じ趣味を持つ人との交流を持てば、「自分は他人との交流ができる」という成功体験を育むことができるでしょう。
デジタルスキルが向上するから
eスポーツ支援は、ゲームを普段しない人にとっても、デジタル機器に触れるという経験を与えてくれます。
特に、近年のeスポーツはパソコンゲームが主流になりつつあります。インターネットリテラシーやシステムを学ぶことで、自然とデジタルスキルを向上させていく効果も期待できるでしょう。
なかには、eスポーツの取り組みをきっかけに、自分自身でパソコンを組むことに挑戦したり、自作ゲームの設計に取り組んだりするケースもあります。eスポーツを通してデジタル製品に触れることで、他のデジタルシステムへも柔軟に対応できるようになる人は、少なくありません。
現在のデジタル社会のなかで、社会復帰の取り組みをしながら自然にデジタルスキルを獲得できる点も、eスポーツが支援に活用される理由のひとつと言えるでしょう。
将来の選択肢が広がるから
支援で取り組んだeスポーツをきっかけに、将来の夢を見つける人も多くいます。eスポーツには、プロeスポーツプレイヤーだけでなく、チーム運営やイベント運営、ゲームタイトルの開発など、さまざまな職業が関係しています。
そこで、eスポーツをきっかけにeスポーツ業界で働きたいと思う人は少なくないのです。
近年はeスポーツについて専門的に学べるeスポーツ専門学校などもあり、進路を決める一助になるケースもあります。
今話題の「eスポーツを扱うフリースクール」ってどうなの?

不登校のお子様がいる家庭では、できる限りスムーズに登校を再開できるようフリースクールの利用を検討しているケースも少なくないでしょう。家庭に引きこもってしまうと、生活リズムが崩れたり他人とのコミュニケーションに苦手意識が芽生えてしまったりすることもあるため、できる限り社会との繋がりを持ち続けてほしいという保護者様が多いです。
そこでeスポーツを扱うフリースクールを検討しているという声も多く聞かれますが、実際はどのような活動を行っているのか分からないという人も少なくないでしょう。
続いては、話題のeスポーツを扱うフリースクールについて紹介します。
フリースクールとは
フリースクールとは、不登校児童を対象に設けられた民間の教育機関です。民間団体のほか、NPO法人や企業などが運営していることもあり、多くは有料のサービスです。
教育プログラムは独自カリキュラムを採用しており、学校と連携されているフリースクールの場合、参加することで正式な出席日数として認めてもらえる施設もあります。
学校の人間関係に馴染むのが難しかったり、学校のカリキュラムや学習ペースが合わない子供などが、個別学習やプロジェクト型学習などで授業を受けられるケースもあり、不登校児童の受け皿として注目されています。
「eスポーツのあるフリースクールなら通ってくれるかもしれない」は危険
不登校のお子様のなかには、フリースクールに通うことも嫌がるケースが多くみられ、保護者の方は「eスポーツのフリースクールなら通ってくれるかもしれない」と期待されることもあるでしょう。しかし、実際に大手相談サイトなどで、子供をフリースクールに通わせている方からは以下のような意見が挙げられています。
- 「子供がフリースクールでゲームばっかりしている。これでは家に居るのと変わらないのでは?」
- 「勉強が一日3時間位と子供から聞いているが、それで学校教育に追いつけるの?」
- 「フリースクールで嫌な思いをした。子供が余計に外に出ることを嫌がるようになってしまった」
もちろん、フリースクールにいったことで社会復帰し、学校への登校を再開させたり進学できたりした人もいるでしょう。特に、出席日数については進路にも大きく影響するため、「今後のことを考えて出席日数を補填できるフリースクールに通ってほしい」と考える保護者様も多いです。
一方で、フリースクールでいくら出席日数を確保しても、内申点がつかず、学力も上がらず、希望する進路を諦めるお子様は少なくはありません。出席日数を確保することを考えるなら保健室登校をしたり、学力を補うのであれば個別指導の塾や家庭教師を利用したりした方がよいという意見もあります。
フリースクールで勉強とeスポーツを両立させることは、不可能ではないでしょう。しかし、実現させるためには適切なカリキュラムとフリースクール運営のノウハウが必要不可欠です。
「eスポーツがある所なら子供もフリースクールに通ってくれるかも。フリースクールに通えば勉強の遅れも取り戻せて登校再開しやすいかも」といった安易な希望で選ぶのは危険と言わざるを得ません。
eスポーツスクール自体、日本では新規分野に当たります。近年、ようやくeスポーツ分野が発展してきて、当スクールも含め業界がようやく独自のノウハウを確立してきたところです。学校教育と両立させるノウハウが既に完成しているフリースクールが全国に何校あるのか?疑問と言わざるを得ないのが現状でしょう。
学業とeスポーツを混同すると幅広い分野を学ぶ機会を失うリスクも
子どもに「勉強とeスポーツどっちをする?」という選択肢を与えた場合、熱中すればするほど、子供はeスポーツを選ぶでしょう。もちろん、勉強をしたくないという理由の子供も同様です。
そうして勉強の時間を損なっていったときに、子供達に残るのはeスポーツしかありません。「eスポーツ選手になりたい」という子供もいるでしょうが、プロとして生活できるほどの収入を得られるのはほんの一握りだけというのが現実です。
「できる限りeスポーツに関わる職業につきたい」という希望があったとしても、学歴によっては目指すことすら困難になることもあるでしょう。
eスポーツは、年齢性別を問わず、誰でも平等に競い合えるという点で、非常に福祉との相性がよく支援に活用されるスポーツです。しかし、支援を受けた先のことを考えるのであれば、不登校児童にとってeスポーツと学業を別に考えるという選択肢も持っておいた方がよいのではないでしょうか。
学業は個別指導塾や家庭教師などのプロフェッショナルに任せ、eスポーツは別で指導を受けて社会性やコミュニケーション能力を高める方法を選ぶ方も近年増えてきています。
eスポーツをすると余計に引きこもらない?活用の際の注意点
多くの保護者様が不登校や引きこもり支援としてeスポーツを提案された際に不安に思うのが「不登校や引きこもりが悪化してしまわないか」という点です。
ゲームというと、家で1人でプレイするイメージが強いため、このような不安を感じるのも仕方のないことでしょう。現に、誤ったeスポーツの取り組み方をしてしまい、不登校や引きこもりが悪化してしまうケースもないとは言い切れません。
eスポーツを不登校や引きこもり支援に活用する際には、以下の2つのポイントを押さえることが何より重要です。
ゲーム依存への注意が必要
ゲーム依存はWHOによって国際疾病分類に位置付けられ、現在は「ゲーム行動障害」として精神疾患の一種と分類されます。日常生活に支障をきたすほどゲームに没頭してしまい、社会生活や健康に悪影響を与えてしまう病気です。
ゲーム行動障害は、ストレスや自己肯定感の低さ、孤立などの心理的要因などが発症に影響すると考えられており、不登校児や引きこもりの人は特にリスクが高いと言えるでしょう。
だからといって、ゲームを取り上げ、現状を何も変えないままでは不登校や引きこもりの改善には繋がりません。eスポーツを与えっぱなしにするのではなく、適切なコントロール能力の育成をセットが考える必要があります。
すでに不登校や引きこもりの状態でゲームに依存気味の場合は特に、ゲーム依存について適切な知識を持つ人に指導を受け、適切なコントロール能力を育成する環境でプレイさせる方が望ましい結果を得られる可能性が高まるでしょう。
「家から出る」に重点を置く
eスポーツはオンライン環境と機器が揃っていれば、自宅でも取り組むことができます。しかし、それでは不登校や引きこもりの改善効果は見込めないでしょう。あくまで、「現実世界での他者との関わりを持つ」ということが重要です。
最初はオンラインで他人との交流を持っても構いません。しかし、そこから徐々に関係性を現実世界に広げられる環境が必要です。あくまで「家から出る」「社会に参加する」「現実世界でのコミュニケーションをとる」ことを目的とした環境作りが欠かせないでしょう。
不登校や引きこもり支援にAFRAS(アフラス)が選ばれる理由

AFRAS(アフラス)は塾のように通えるゲーミングスクールです。フリースクールではありませんが、不登校や引きこもりの改善に利用される方もいらっしゃいます。最後に、eスポーツに対応できるフリースクールを差し置いて、AFRASが選ばれる理由を紹介します。
プレイ時間はあくまで「練習時間」メリハリをつけたゲーム指導が人気
AFRASでは、マンツーマン指導によってゲーム技術を高め、受講者の掲げる目標を達成することに重点を置いています。そのため、ゲームをプレイしている時間は、自由時間や遊びの時間ではなく「練習時間」です。
プレイ中に指導した点は次回、改善してプレイするよう指導しますし、戦略やロジックを重視することの大切さなども指導します。ただ「楽しかった」で終わるのではなく、「もっと上手くなるにはどうすればいいのか?」という問題解決を主軸に置いた思考を構築できるのが、プロ講師がマンツーマンで指導するAFRASの強みです。
対面指導だから家を出る動機付けになる
AFRASでは家でのオンライン授業を行っていないため、原則として受講者は来校して指導を受けます。家に籠りきりになりやすい不登校児や引きこもりの人にとって、外出する動機付けになりやすいでしょう。
最初は保護者が送迎していたものの、徐々に公共交通機関を使って自分自身で来校するようになるお子様も多いです。
外出することで、社会のコミュニティに触れ、不登校や引きこもりの孤立化を防ぐ効果も期待できます。
チームを組んだり大会出場を目指したりできる
AFRASでは、年に数回独自の大会を開催しています。マンツーマン授業に慣れてきたら、同じ構内でチームを作り、大会に参加するのもよいでしょう。
まずは、講師とマンツーマンのコミュニケーションを充実させ、徐々に同年代や全く知らない人へとコミュニケーションの幅を広げていくことができます。同じ受講生であれば身分などもAFRASで把握しているため、オンライン上で背景の不明瞭な人物とコミュニケーションをとるより安全です。
人との関わりを段階的に育めるのも、AFRASが不登校や引きこもり支援に活用される理由のひとつです。
アフラスの無料体験レッスンを気軽に活用しよう!
今回は不登校や引きこもり支援にeスポーツが活用されている現状について解説してきました。
不登校や引きこもりは、本人だけでなく家族も辛い気持ちや不安な気持ちを抱えていることが多いです。まずは、そんな現状から一歩踏み出すために、eスポーツの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
AFRASでは、随時体験会を開催しています。お子様同伴でも、まずは保護者様だけでも構いません。まずは、お気軽に体験会にいらしてみてください。