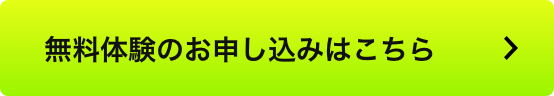サッカーや野球、体操など体を動かす習い事や、ピアノや習字のように教養を伸ばす習い事など、子どもの習い事にはさまざまな種類があります。
近年、そんな習い事のなかでも急激に勢いを増しているのがeスポーツです。
子ども達の大好きなゲームを通して学びを得るeスポーツ教室は、小学生に特に人気があります。また、本気でeスポーツをしたい中学生や高校生のなかにもスキルアップを目指してゲーミングスクールに通うという人が増えてきました。
今回は、習い事としてのeスポーツについて紹介します。eスポーツの習い事で得られる学びやメリット、小学生向けのeスポーツ教室の特徴についても解説します。
eスポーツ教室に子どもを通わせようか悩んでいる親御さんは、ぜひ参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
eスポーツってどんなスポーツ?

eスポーツとは、Electronic Sports(エレクトロニックスポーツ)の略称です。コンピューターゲームを用いて勝敗を競う競技を指します。主にパソコン、ゲームハード、スマホ、タブレットなどのプラットフォームを用いたゲームで競い、一般的にプレイされているタイトルを用いることも多くあります。
広く知られているゲームであれば「ぷよぷよ」「ストリートファイター」「鉄拳」などのタイトルです。これらのタイトルでは、世界大会なども行われています。
ゲームを用いていることから「eスポーツはスポーツではない」という意見もありますが、高度なスキルと知略を駆使し、場合によっては仲間と連携して戦うため、日々自己研鑽を詰むeスポーツプレイヤーは、紛れもないアスリートと言えるでしょう。
2026年に日本(名古屋)で開催されるアジア選手権大会でも正式種目に決定しており、今後ますますeスポーツは盛り上がりが期待されています。
参照:「eスポーツアジア大会」eスポーツがアジア大会で正式競技に!
eスポーツの習い事ってどんな事をするの?

eスポーツを習い事として学ぶ場合、教室によってプログラムは大きく異なります。今回は、さまざまな教室で取り入れられている主な教育プログラムを紹介していきましょう。
パソコンの扱い方を学ぶ
eスポーツでは、パソコンのプラットフォームを利用してゲームを教えるケースも少なくありません。特に、小学生向けにプログラミング要素の高いゲームタイトルなどを教材として利用する教室では、必ずといって良いほど最初にパソコンの扱い方を教えます。
これからの時代、パソコンに全く触れずに完結する仕事はほとんどありません。さまざまなシーンでパソコンを使用する機会があるため、子どものうちからパソコンの扱いに慣れておく事は重要です。小学校でもパソコンを利用する授業を行うことを考えると、予習にもなるでしょう。
パソコンの立ち上げ方やシャットダウンの仕方、キーボード入力の方法など、基本的な操作が正しく身につきます。
目標を立てる取り組み方を学ぶ
eスポーツは1人で黙々とやり込むシュミレーションゲームやRPGなどと違い、eスポーツは対人で競います。そのため、トライ&エラーを繰り返しながら上達していくスポーツです。
単純なスキルよりも知略や戦略を必要とされるシーンも非常に多く、上位ランカーの選手の多くがPDCAサイクルを意識したトレーニングを積んでいることでも有名です。
PDCAサイクルとはビジネス用語で、今ある問題を解決するための考え方を表します。
- P=Plan(計画)
- D=Do(実行)
- C=Check(評価)
- A=Action(改善)
PDCAサイクルでは上記の言葉を表しており、計画を実行し、評価のうえ改善していくことでより高い成果を得続けていることを示しています。
eスポーツでは、どのような戦略で戦うのかを計画し、実行する、どこが良くてどこが悪かったのかを評価し、良い部分を残して悪い部分を改善する、といったように、PDCAサイクルを常に回し続けながら自己研鑽を詰みます。
eスポーツを通じてPDCAサイクルを学ぶことで、子ども達は問題に直面した際の解決策の考え方を学ぶことができるでしょう。
コミュニケーションスキルを学ぶ
ゲームと聞くと1人で黙々とプレイするイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。しかし、eスポーツのなかにはチームプレイを必要とするものも少なくありません。
そこで求められるのがチームメイトとのコミュニケーションスキルです。相手の意見を尊重しつつ、自分の意見を伝える事や、相手との適切な距離感を持ってチームメイトとして接することなど、円滑な人間関係を築くためのスキルを実践的に学ぶことができるでしょう。
もちろん、なかにはソロ(1人用)でプレイするタイトルもありますが、教室に通って他人と関わりをもつなかで、さまざまなコミュニケーションスキルが身に着いていくのはeスポーツ教室ならではです。
マナーを守る
ゲームの世界では、ネットを通じて他人と繋がる事もあります。そのため、ささいなすれ違いから大問題に発展してしまったり、相手を不愉快な気持ちにさせてしまったりすることも珍しくありません。
そこで、eスポーツ教室の多くは、子どもにeスポーツを教える際にマナーを重視します。インターネット上のマナーだけでなく、現実世界のマナーも合わせて教えるケースも少なくないでしょう。
現実世界で礼儀正しく相手の気持ちを思いやれる子どもは、ネット上でもその性質が変わりません。礼儀正しく、挨拶や会話ができるよう、マナーを重視するeスポーツ教室が多い傾向にあります。
ゲーミングスキルを学ぶ
eスポーツ教室ではゲーミングスキルを学ぶ事ができます。スキル上達のコツを講師に指導してもらうことで、目覚ましくスキルアップする子どもも多くいます。
特に、中学生や高校生など本格的にeスポーツをやりたいと考えている子供にとって、eスポーツを教えて貰える環境はそう多くありません。プロ講師や現役プロゲーマ―など、実際に高いスキルを持っている人に指導してもらうことでモチベーションを高められるでしょう。
小学生向けeスポーツ教室の特徴

小学生向けのeスポーツ教室では、eスポーツよりもプログラミングの要素が高い傾向にあります。特に、Minecraft(マインクラフト)を用いたプログラミング学習を「eスポーツ」として教えている教室も多くあるため、Fortnite(フォートナイト)やApex(エーペックス)などのタイトルで競う本格的なeスポーツをしたいと言う小学生のために教室を探すのであれば注意が必要です。
本来、eスポーツはコンピューターゲームを使って競う競技です。そのため、Minecraftのようなサンドボックスビデオゲームが競技タイトルに選ばれることはありません。
「ゲーム」というくくりだけでeスポーツと表現しているケースもあるため、子供がeスポーツとしてどんな事を学びたいのが充分に聞いてあげた方がよいでしょう。
なぜ今「ゲーム」が習い事として注目されているのか?

近年、「ゲームを習い事にする」という選択肢が、子どもたちだけでなく保護者にも注目されています。
その背景には、次のような社会的変化や教育的価値が挙げられます。
- 将来の職業として「ゲーム」が現実的な選択肢に
- ゲームを通じて身につく「非認知能力」に注目
- 保護者の意識変化と社会全体のデジタルシフト
それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
将来の職業として「ゲーム」が現実的な選択肢に
ひと昔前まで「ゲームばかりして…」と叱られていた子どもたちも、今ではプロゲーマーやストリーマー、さらにはゲーム開発者といった形で“ゲームを仕事にする”未来が現実のものになっています。
eスポーツ大会の賞金やスポンサー契約、YouTubeやTwitchでの配信収入など、ゲームスキルを活かした職業が実在し、しかも高収入を得ることも可能な時代です。
そうした時代背景の中で、保護者がゲームをキャリア形成の第一歩としてとらえるようになり、「習い事として通わせてみよう」という動きが広がっているのです。
プロゲーマーに関しては以下でも詳しく解説していますので併せてご覧ください。
プロのゲーマーとは?どうすればなれる?年収やなれる年齢を解説!
ゲームを通じて身につく「非認知能力」に注目
いわゆる「勉強」だけでは測れない力——たとえば論理的思考力、瞬時の判断力、他者との協調性や集中力など——を育てることができる点において、ゲームは非常に優れた教材となり得ます。
特にチーム戦があるeスポーツ系のゲームでは、仲間との意思疎通や戦略的な動きが求められるため、学校や家庭では得にくい“実践的スキル”が自然と身につきます。このような力は「非認知能力」と呼ばれ、近年の教育界でも注目されている価値の高い能力です。
ゲームと非認知能力については行政も積極的に研究を繰り返しているなど、注目度が高まっています。
参照:文化庁・令和5年度文化芸術による子供育成推進事業に関する調査研究報告書
保護者の意識変化と社会全体のデジタルシフト
数年前まで「ゲーム=依存」「ゲーム=悪」といった偏見が根強かった日本ですが、近年はその価値を認める保護者が急増しています。
背景には、プログラミング教育の必修化やリモートワークの普及など、社会全体がデジタル前提にシフトしていることがあります。ゲームを通じてデジタルデバイスに自然に慣れることが、将来的な情報リテラシーの向上にもつながると考えられ始めているのです。
つまり、ゲームは「今を生きる子どもたちに必要な力を育てるツール」として、習い事の選択肢に加わるようになっているのです。
eスポーツを習い事にするメリット

eスポーツを習い事にするメリットにはさまざまなものがあります。
非認知能力の向上
非認知能力とは、知能検査や学力検査などでは数値化できない能力を指します。忍耐力や自己抑制力、協調性、社交性などが非認知能力の代表的なものです。
eスポーツを通して、失敗しても目標を達成するまで努力する姿勢やチームメイトを思いやる気持ち、勝利することで自己肯定感が向上することも大きなメリットと言えるでしょう。
非認知能力は「生き抜く力」とも言われている重要な能力です。eスポーツを通して非認知能力の向上効果が期待できることは、習い事として取り組む大きなメリットと言えます。
ネットリテラシーへの理解
ネットリテラシーとは、インターネット上で情報を正しく安全に扱う能力です。スマホの普及によりインターネットは急激に身近なものになり、低年齢化も進んでいます。
幼い頃からインターネットを利用している子どもは非常に多く、今後も増えていく見込みです。合わせて、判断能力の未熟な子どもがインターネット上でトラブルを起こしてしまうケースも増加傾向にあります。
原因は子供達のネットリテラシー教育が不十分な事が挙げられるでしょう。インターネットの危険性を知らず、不用意に情報発信してしまうことでトラブルに巻き込まれてしまうケースも少なくありません。
eスポーツでインターネットに触れ、講師の管理下においてさまざまなコミュニケーションをとることで、実践的にネットリテラシーを学ぶことができます。
ネットリテラシーは行政でも「興味を持ち、意識を高めるように」と啓発している重要なものです。その点を自然と学べることもメリットに挙げてよいでしょう。
eスポーツへの理解
eスポーツは現在、世界中の競技人口が1億人を超えたと言われています。スポーツとして正式に認められはじめており、プロサッカーの前座試合としてeスポーツのサッカータイトルを用いた試合が行われたという実績もあります。現実世界とeスポーツの世界が交差し始め、エンターテイメントとして各業界から注目されているのも事実です。
しかし、日本ではeスポーツへの理解が未だ進んでおらず「ただゲームをしているだけ」という人もいます。
今後、世界的に盛り上がりを見せるであろうeスポーツに幼い頃から触れておくことで、eスポーツを正しく理解できるようになるでしょう。また、家族にとっても子供がeスポーツを学ぶ姿を見守ることで、eスポーツへの偏見を薄め、その面白さや奥深さを知ることができます。
ゲームを習い事にするデメリット

ゲームを習い事として選ぶことには多くのメリットがありますが、当然ながら注意すべきデメリットも存在します。とくに、以下の3つの点は保護者が事前にしっかり理解しておくべきポイントです。
- 親世代の理解が追いつかないことも
- 依存や視力低下などの懸念
- 習わせる内容の選び方に注意が必要
それぞれの課題について詳しく解説します。
親世代の理解が追いつかないことも
ゲームに対する価値観は世代間で大きく異なります。親世代の多くは「ゲーム=遊び・娯楽」といったイメージを強く持っており、習い事として通わせることに抵抗を感じるケースも少なくありません。
子どもが楽しんで学んでいても、「本当に役に立つのか?」と不安になることがあるのは当然です。そのため、習い事としてゲームを選ぶ際は、保護者自身も情報を集め、時代の変化や教育的な価値を理解する姿勢が求められます。
依存や視力低下などの懸念
ゲームに熱中しすぎてしまうと、依存傾向が高まったり、長時間のプレイによる視力低下など、身体的・精神的な健康リスクが懸念されます。習い事であっても、「やりすぎ」や「バランスの悪さ」は子どもの生活習慣に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、スクール側が適切な時間管理や休憩の導入をしているかどうか、また家庭でもルールを設けるなど、保護者のサポートが重要になります。
習わせる内容の選び方に注意が必要
「ゲーム」といっても、そのジャンルや指導内容は教室によってさまざまです。中には単なるプレイ時間の提供に終始するような教室もあり、教育的な効果が得られないケースもあります。
また、暴力的な描写の多いタイトルを扱っている教室が子どもに適しているかどうかも慎重に判断すべきです。ゲームの習い事を選ぶ際は、指導内容・対象年齢・教育方針などを事前に確認し、信頼できる教室を見極めることが重要です。
eスポーツはオンラインで学べるスクールもある

eスポーツはオンライン上でも学べる習い事です。環境さえ整っているのであれば、オンラインで指導してくれる教室も少なくありません。
通える範囲に教室が無い場合や小学生で送迎が必要だが保護者の都合が合わないなど、習い事としてeスポーツを習わせてあげたいけれど現実的に難しいというケースもあるでしょう。
オンラインであれば、自宅にいながら指導を受けられるため教室が遠くても問題ありません。また、保護者の都合で送迎などが難しくても、家庭から習い事ができます。
ゲームの習い事に関するよくある質問(FAQ)

ゲームを習い事として始めることに興味はあるけれど、まだ不安や疑問が残るという保護者の方も多いはずです。ここでは、実際によく寄せられる質問とその答えをまとめました。始める前に気になるポイントをぜひチェックしてみてください。
Q1:ゲームの習い事って本当に将来の役に立つの?
A:はい。eスポーツ選手や配信者などの職業だけでなく、ゲームを通じて身につく思考力・判断力・協調性などは、他分野でも活かせる重要なスキルとされています。
Q2:ゲーム依存になったり、目が悪くなったりしませんか?
A:過度なプレイはリスクになりますが、習い事として適切な時間管理がされていれば問題ありません。教室選びの際は、健康面への配慮があるかも確認しましょう。
Q3:どんな年齢の子どもが通えるんですか?
A:教室によって異なりますが、多くは小学校高学年から中学生を中心に対応しています。プログラミングと組み合わせた教室は、低学年から受け入れているケースもあります。
Q4:どんなゲームを習うんですか?
A:代表的なのは『フォートナイト』や『マインクラフト』『ロブロックス』『ぷよぷよeスポーツ』など、教育的要素や競技性があるタイトルです。教室によって扱うゲームは異なるため、事前確認がおすすめです。
eスポーツの習い事ならAFRAS(アフラス)
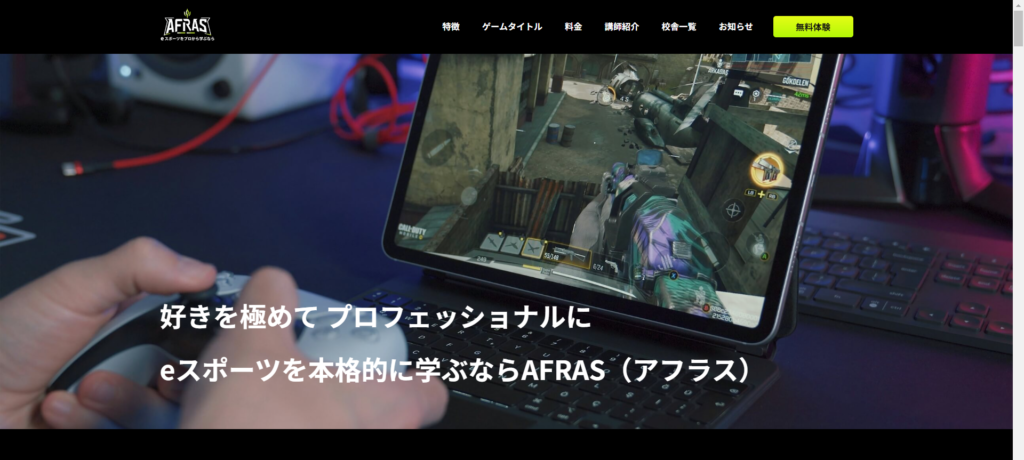
eスポーツスクールは近年、増加傾向にあります。そのため、「子供がeスポーツを習いたいと言っているけれど、どこを選べばいいのか分からない」という人もいるでしょう。
eスポーツスクールAFRAS(アフラス)は以下の条件に当てはまるeスポーツ教室を探している方におすすめです。
- 小学生・中学生・高校生・大人の通えるeスポーツ教室を探している
- プログラミングではなくeスポーツを習いたい
- オンラインで習いたい
- 教室に通いたい
- プロeスポーツプレイヤーからのマンツーマン指導を受けたい
- eスポーツスキルを磨きたい
また、eスポーツ教室を探す際には、自分のプレイしたいゲームタイトルの指導をしてくれるのかチェックすることも大切です。AFRASでは、以下のゲームタイトルを扱っています。
- Fortnite
- Apex
eスポーツを習い事にしたい方は、ぜひAFRASをチェックしてみてください。
eスポーツはおすすめの習い事
コンピューターゲームで勝敗を競うeスポーツは、まだスポーツとしての認知度もそう高くありません。
しかし、ゲームを通じて学べることがたくさんあり、野球やサッカーなどを習う事と同じように、そのスポーツの技術が上達する事と精神的な成長を促すことができます。
子供が前向きに取り組める習い事として、ぴったりと言えるでしょう。ぜひ、子供の習い事としてeスポーツを検討してみてください。