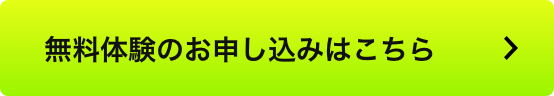自己肯定力(自己肯定感)という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。自己肯定力の高い人は社会でも華やかに活躍している人が多く、日頃から自己肯定力を高めたいと考えている人も少なくないでしょう。
今や、自己肯定力の高さは社会人として生きる強い武器となり、幼児教育から自己肯定力を高める働きかけを行うケースも多く聞かれます。
今回は、自己肯定力がどのような能力なのか、高めるための考え方や方法について詳しく紹介します。記事の後半では、大人の取り組むべき自己肯定力を高める方法の他に、子供の自己肯定力を育む方法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
自己肯定力とは?

自己肯定力とは、自分自身を肯定する能力を指します。自己肯定感と言い替えられることも多く、テストなどで数値化して評価できない非認知能力の一種と考えられています。
肯定とは、物事に対して正しく妥当であることを認めること、他の物事との違いを積極的に認めることを指す言葉です。つまり、自己肯定力とは自分自身のありのままの能力や存在を認め、他と違うことを受け入れる能力と言えるでしょう。
「自分のありのままを受け入れる」と言えば当たり前のように思えますが、実はこれが意外と難しいことなのです。
自己肯定力と自信の違い
自己肯定力のある人を「自信のある人」と捉えているケースも多く見られますが、これらは似ているようで違います。
そもそも、自信というのは過去の実績やデータ、経験などの根拠を元に、自分自身の能力を信じることです。「前に挑戦して成功したから今回も成功する筈」「自分の数値なら成功できる筈」といった考え方です。
一方、自己肯定力には根拠となるものはありません。過去の実績やデータ、経験などがなくても「自分ならやれる。失敗してもいいから挑戦してみよう」と考えられるのは、自己肯定力によるものです。
日本人は自己肯定力が低い国民性
日本人は古くから「謙虚」「謙遜」「忍耐」などを良しとする文化があり、控え目な国民性と言えます。幼い頃他人が「お宅のお子さんはとても賢いわね」と褒めるのに対して「そんな事ありませんよ。家では…」などと謙遜するやり取りを聞いた事があるという人は少なくないでしょう。
諸外国では同じシーンでも「そうでしょう?うちの子はとても賢くて優しくて…」と相手の意見を受け入れるケースが多いです。しかし、日本では「御世辞で言っているだけなのに、自慢してしまったら傲慢だと思われるかもしれない」と考えて謙遜するケースが多くありました。
ありのままの自分を身近な人に受け入れて貰えない経験を詰むと、自己肯定力は育まれにくくなります。他人と比べ、多に混ざり突出しないことを選択してきた日本人の国民性から自己肯定力は育みにくく、近年のグローバル社会では問題視されています。
自己肯定力が高い人に見られる6つの特徴

自己肯定力が高い人には以下のような特徴が見られます。
1.自分の判断基準や価値観を明確に持っている
自己肯定力の高い人は、自分自身と他人が決して混ざらないことを無意識に理解しています。そのため、ぶれない判断基準や価値観を明確に持っていることが多いです。
結果として、他人に流されにくい傾向にあります。
2.気分で態度が変わらない
自分の機嫌が悪いと周囲への態度が悪くなったり、自分が悲しいと見るからに落ち込んで見せたりする人の意図は、自分の機嫌に合わせて周囲の行動を変えさせようとする点にあります。意識的であっても無意識であっても、気分で態度を変える人は自分と他人との境界が曖昧で、他人に対して自分自身のことを理解して欲しい、共感して欲しいという気持ちが強い傾向にあるでしょう。
自己肯定力は感情でさえも自分自身のもので、怒っていても悲しんでいても、それがありのままの自分だと受け入れることができます。そのため、他人に理解や共感を求める必要がなく、周囲に対する態度が変わらない人が多いです。
3.周囲とのコミュニケーションが得意
自己肯定力の高い人は自分と他人との線引きが明確にでき、ありのままの自分を受け入れるとともに、ありのままの他人も受け入れられる人が多いです。
自分自身に対する共感や執着などを求めないため、適切な距離感でコミュニケーションをとれる人が多く、自己肯定力の高い人の傍を心地よいと感じる人も多いでしょう。
4.努力を継続するのが得意
継続して努力をすることは、身体的にも精神的にも辛いことがあります。それは確定していない未来に対して、現在の自分に負荷を課すからだと言えるでしょう。継続しても絶対に成功するとは限らない状況で努力を続けるのは簡単なことではありません。
自己肯定力の高い人は、不確定な未来でさえも受け入れることができる人が多いです。努力の先に成功があっても、失敗があっても、ありのままの自分が変わることはないと理解できているからこそ、継続して努力できる人が多く見られます。
5.失敗してもすぐに立ち直れる
幼い頃から自己肯定力を高めてきた人は、ありのままの自分を受け入れるという土台がしっかりと完成しているケースが多く、失敗を糧にすることが得意な人も多い傾向にあります。
多くの人は、失敗してしまった自分に失望してしまったり、周囲の期待に応えられなかったことに罪の意識を感じたりしてしまいます。しかし、自己肯定力の高い人は失敗した自分を受け入れることができ、自分の失敗に周囲が落胆したとしても落胆される自分自身でさえ受け入れることができる人が多いです。
自分自身が失敗してしまった理由を考え、気軽に再挑戦できることも自己肯定力が高い人の特徴と言えます。
6.主体的に行動できる
率先して主体的な行動ができない人の心理は、「周囲にどう思われるか」「自分にできる自信がない」など、ネガティブな感情を抱えていることが多いです。しかし、自己肯定力の高い人の場合、自分の価値観からその行動が必要だと思えば主体的に行動できるケースが多いでしょう。
それは、周囲に必要以上の共感を求めず、自分の揺るがない価値観を持っており、何より失敗してもありのままの自分を受け入れられるマインドがあるからこそできる行動です。
自己肯定力が低い人の特徴

自己肯定力が高い人に特徴があるように、自己肯定力が低い人にもさまざまな特徴がみられます。
- 周囲の人と自分を比較して劣等感を抱きやすい
- 不安を感じやすい
- 過度に心配してしまう
- 承認欲求が強い
- 完璧主義
なかでも、承認欲求の強さや完璧主義等の特徴は、自己肯定力の低い人によく見られる特徴です。自分自身の価値観を信じられないからこそ、他人に認められることで肯定の裏付けを欲してしまうケースや、失敗した自分を受け入れられないからこそ全てを完璧にして誰にも否定されない状況を作り出したいという願望が見受けられます。
自己肯定力が高いメリット・低いデメリット

自己肯定力が高いことで得られるメリットには、さまざまなものがあります。また
、自己肯定力が低いことによるデメリットも少なくありません。続いては、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
自己肯定力が高いメリット
自己肯定力が高いことで以下のようなメリットがあります。
- 他人に依存したり共感を求めすぎたりしないため、円滑な人間関係を築きやすい
- 自分自身の長所をよく理解しているため、特化した能力を発揮して成果を得やすい
- 自分の短所を受け入れているため、苦手な事などに直面した際には他人に助けを求められる
- 自主的に行動できるので周囲から評価されやすい
子供のうちは、自己肯定力が高いことでさまざまな挑戦をできることこそ最大のメリットと言えるでしょう。失敗を恐れずに挑戦できるため、自分に向いているものに出会える可能性が高まります。
また、大人の場合は自己肯定力が高いことで、円滑に周囲との人間関係を築けることが魅力です。社会生活を送るうえで周囲との関わり合いは避けられません。他人との適切な距離感を持てたり、素直に助けを求めたりことができることで、信頼を得やすい傾向にあります。
自己肯定力が低い人のデメリット
自己肯定力が低いことで以下のようなデメリットが考えられます。
- 失敗を怖がって挑戦できない
- 承認欲求が高すぎたり共感を求めすぎたりすることで、他人との適切な距離感を保てなくなる
- 自己肯定力が低い人同士で依存しあってしまい、お互いが成長を妨げてしまう
- 周囲からの評価を気にして他人に助けを求めることができず、問題を大きくしてしまう
子供のうちは、自己肯定力が低いと新しい挑戦を拒みやすいことが最大のデメリットと言えるでしょう。新しい事に前向きに挑戦できないことで、本来なら発揮される筈の才能や能力が開花しないこともあります。
また、人間関係も築きにくく、友達作りが苦手だったり友達ができてもすぐに喧嘩をしてしまったりするケースも少なくありません。
大人の場合、自己肯定力が低いことで最も注意すべきなのは、他人に助けを求められない点です。「こんな事もできないと思われる」「できないと言うと叱責される」と周囲の評価が下がることや指導されることを恐れて、問題があってもすぐに助けを求められないケースが少なくありません。ミスを隠してしまったり、報告を先伸ばしたりすることで問題が大きくなってしまうこともあります。
自己肯定力を高める5つの思考

大人になってから自己肯定力を高めるのであれば、日頃から思考を変える必要があるでしょう。自己肯定力を高めるマインドを身に付けることで、自然とありのままの自分を肯定できるようになると考えられます。
1.事実と印象・感情を切り分けて考える
自分自身の判断基準をぶれないようにするため、事実と印象・感情を切り分けて考える習慣をつけましょう。
例えば、自分が「良い」と評価したものに対して、多くの人が「悪い」と評価したとします。これに対して、自己肯定力の低い人は「皆が悪いと言っているから悪い」と考えることが多いでしょう。
この時、「どうして悪いと感じるのか?」を考えることが大切です。そこには、自分が良いと感じた事実と多くの人が悪いと感じた事実があります。事実だけを冷静に検証することで自分の判断基準を再度当てはめて考えることができます。
多くの人が「悪いと感じた」のは多くの人の感情です。事実を検証することで、自分の判断基準を満たしているのなら、自分自身は「良い」という評価を貫いても良いのです。一方、多くの人の事実を検証したうえで、自分自身の判断基準を満たさないことが分かったなら事実を受け止めて「やっぱり悪い」と評価しても良いでしょう。
2.自分の短所をポジティブに変換する
自分自身を肯定するうえで最も難しいのが短所に対する考え方です。短所とは、他人と比べて劣っている点や欠点、不備などを指します。
しかし、短所の裏には必ず長所も隠れています。短所をポジティブに変換することで自分の長所が見えてくるでしょう。長所が理解できれば、自分のできることが理解でき、率先した行動する機動力にもなります。
短所は以下のようにポジティブに変換してみるとよいでしょう。
- 挑戦できない→リスク管理能力が高い
- かたくるしい性格→真面目で責任感がある
- わがまま→自分の意見を臆することなく主張できる
- 主体性がない→協調性が高い
3.多くの意見を聞く
自己肯定力の高い人は、幼い頃から自己肯定力を育んできたケースが多く、柔軟に人の意見を聞き入れる能力に長けています。これまでの人生で出会ってきた多くの人の意見を聞き、さまざまな意見を持つ人がいるという実体験から、自分自身を確立できているのでしょう。
自己肯定力を高めるためには、他人の意見を聞く経験を重ねることが大切です。意見の是非に関しては別のものと考えましょう。まずは、さまざまな意見をもつ人がいて、自分の意見もそれらと同じ1つの意見でしかないことを理解することが重要です。
自分の意見を主張するために相手の意見をはねのけるのではなく、一度相手の意見を受け入れたうえで自分の意見と照らし合わせ対話を進められる習慣を身に付けましょう。
4.相手によって適切な関わり方を選択する
自己肯定力が低いと自分の求める人間関係を築きたがる傾向にあります。共感してくれる関係性、自分にとって心地よい距離感を保ってくれる関係性を求めると、同じ考えの人なら共依存に陥り、違う考えの人なら離れてしまいます。
自分自身と相手との間に適切な境界をおき、相手を理解しようとする姿勢が重要です。そのうえで、相手によって関わり方を変えることで良い関係性を築けるようになるでしょう。
自己肯定力が高まれば、相手に求めるものが減り、ありのままの相手もありのままの相手も受け入れられるようになります。求めないことと不仲なことは決して同一ではありません。お互いがストレスなく親しくできる関係性を築くことにも繋がるでしょう。
5.成功体験を重ねる
自己肯定力の低い人が自己肯定力を高めるためには、成功体験を重ねるのがよいでしょう。しかし、成功体験は「結果」だけでなく「過程」も重視してください。成功した結果だけを重ねてしまうと、自己肯定力ではなく自信が高まるだけで、失敗した際に揺らぎ、振り出しに戻ってしまいやすくなります。
求めた結果が得られれば何も言うことがありませんが、失敗したとしても努力した過程を受け入れることができれば「次はできるかもしれない」というマインドが生まれます。
【自己肯定感の土台を作る】子どもの自己肯定力はどうしたら高められる?

ここまで大人の自己肯定力について解説してきましたが、本来自己肯定力は子供の頃に作り上げられることが最適だと考えられます。保護者や友達、教師などさまざまな人との関わり合いを重ねて、揺るがない土台を作ることこそが、自己肯定力の大きな強みになるでしょう。
続いては、子供の自己肯定力を育む接し方を紹介します。
成功体験を詰ませる
子供にとっても成功体験は重要な要素です。子供は大人よりも単純に成功を喜びと捉えることができます。小さな成功体験を多く詰ませることで、失敗を恐れずに挑戦できる主体性が身につきます。
結果だけでなく過程も褒める
自己肯定力の高い子供を育てている親御さんの多くは、褒め方が上手な人が多い傾向にあります。自然に褒めることができ、なおかつ結果だけでなく過程も褒めているケースが多いです。
結果にこだわらないことで、気軽に挑戦できたり努力した自分を受け入れたりできる土台が育まれます。
子供に選択の機会を与える
親に与えられたものだけを得るよりも、自分自身で選んだ結果を得ることで自己肯定力が高まると考えられます。また、自分で選択することで主体的に取り組めたり、熱中できたりする面もあるでしょう。
失敗を受け止められるようサポートする
自己肯定力を養うために先回りして失敗を防ごうとするのは悪手です。成功体験は良い効果をもたらす一方、成功体験だけでは実績だけを詰んだ自信を育むことにしかならないでしょう。失敗から学べることも多くあります。失敗しそうになった時にも見守り、失敗を受け止められるようサポートすることが重要です。
自己肯定力を高める習い事としてeスポーツが人気

eスポーツとは、コンピューターゲームを使って勝敗を競う競技です。近年、スポーツとして認められはじめ、アジア競技会をはじめ国際的なスポーツ大会でも種目に選ばれることが増えてきました。
そんなeスポーツを、自己肯定力を高める習い事として始める子供が増えています。
eスポーツには自己肯定力を高める以下の要素が含まれています。
- 主体的に取り組める
- スモールステップを設定しやすく、成功体験を得やすい
- 目標達成した際の達成感を得やすい
eスポーツは扱うものがコンピューターゲームだからこそ、子供は主体的に取り組むことができるでしょう。また、勝敗以外にもポイント数やプレイ時間などさまざまなスモールステップを設定できるため、初心者でも成功体験を得やすいです。努力して練習を重ねた結果勝利した際には、大きな達成感や喜びを感じやすいため、子供はより夢中になってeスポーツに取り組めるようになります。
eスポーツで自己肯定力を高めよう!アフラスの無料体験へ
海外では、国民性や育児の仕方によって幼い頃から高い自己肯定力を持つ人が比較的多い傾向にあります。失敗しても立ち上がることができ、他人と自分を切り分けて考えられるため、プライベートでも仕事でも魅力的な人が多いでしょう。
そんな外国人が日本に入国してくるなかで、競争を勝ち残るために自己肯定力を身に付けたいと考える人が多くいます。ぜひ、今回紹介したマインドを参考に、自己肯定力を高めてみてください。
また、現在子供を育てている人は、小さな頃から自己肯定力を育むことで、子供がありのままの自分を認められるようになります。
AFRAS(アフラス)では、自己肯定力を高める習い事としてeスポーツを始めたい小学生。中学生、高校生におすすめのゲーミングスクールです。eスポーツを通して自己肯定力をはじめとした非認知能力や認知能力を高め、これからの時代を生き抜く能力を養うことができるでしょう。子供の習い事を検討中のかたは、ぜひAFRASをチェックしてみてください。