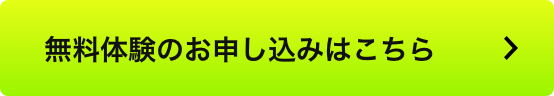ゲーム中に自分の操作がワンテンポ遅れて反映されたり、コンボがうまくつながらなかった経験はありませんか?このような“操作と反応のズレ”の正体が、まさに「ディレイ(遅延)」です。
特にFPSや格闘ゲーム(格ゲー)などの対戦型ゲームでは、このディレイが勝敗を分ける重要な要素になります。
しかし、多くの初心者プレイヤーは「ラグ」との違いや、「なぜ遅れるのか」という原因を正しく理解していないまま、ストレスを感じてしまいがちです。
この記事では、ゲームで発生する「ディレイ」について、
- 意味や仕組み
- FPS・格ゲーでの具体的な影響
- 原因と対策方法
そしてeスポーツ大会でも導入される「ディレイ配信」の役割についてもわかりやすく解説します。
ゲームをもっと楽しみたい方、eスポーツに本気で取り組みたい方にとって、「ディレイの理解=スキル向上への第一歩」です。ディレイを知りたい方はもちろん、eスポーツのスキルアップを考えている方も是非ご覧ください。
この記事のコンテンツ
そもそも「ディレイ」とは?

「ディレイ」とは、ゲームにおいてプレイヤーの入力操作が画面上に反映されるまでに発生する時間差のことを指します。日本語では「遅延」と訳されることが多く、オンラインゲームやeスポーツにおいては非常に重要な要素です。
この遅延が大きいと、例えば攻撃ボタンを押してもキャラクターの動きが遅れて表示されるなど、プレイ体験に支障をきたすことになります。特にFPS(ファーストパーソン・シューティング)や格闘ゲームのような一瞬の判断と操作が勝敗に直結するジャンルでは、ディレイが極めて深刻な影響を及ぼします。
ディレイの原因には、通信環境や使用しているデバイス、さらにはゲームソフト自体の設計など、さまざまな要因が関係しています。そのため、単に「ネットの問題」とだけ片付けられるものではありません。まずは、混同されがちな「ラグ」との違いから整理しておきましょう。
「ラグ」との違いを理解しよう
ディレイとよく混同される用語に「ラグ」があります。どちらもゲームの遅延を指す言葉ですが、厳密には意味が異なります。
ディレイは、プレイヤーの入力操作が反応として返ってくるまでの時間差、つまり「入力遅延」を指します。一方でラグは、主にネットワーク環境が原因となって起こる通信遅延やフリーズ現象のことです。
たとえば、ボタンを押してキャラクターが0.5秒後に動いた場合、それはディレイによるものです。一方で、敵の位置が突然ワープしたり、画面がカクつくような現象はラグが原因となります。
このように、両者は「遅延」という点では共通していますが、発生の仕組みや影響の出方が異なるため、それぞれ適切な対策が求められます。
ディレイが起きる主な場面とは?
ディレイは、ゲームのプレイ中にさまざまなシーンで発生します。以下は代表的な例です。
- FPSの場合:照準を合わせて撃ったはずなのに、弾が遅れて発射されてしまう。結果として敵に先制されることが多くなります。
- 格闘ゲームの場合:タイミングを計ったコンボ入力がずれ、攻撃がヒットしない。ガードの操作が間に合わずダメージを受けるといった現象もディレイによるものです。
- MOBAやRTS系のゲーム:スキルの発動やユニットの移動が意図通りに反映されないことで、戦術的なミスに繋がるケースが多く見られます。
特にeスポーツシーンにおいては、わずかなディレイが試合の勝敗を左右するため、どのような状況で発生するかを理解しておくことが極めて重要です。
FPSや格ゲーでの「ディレイ」の影響とは

ディレイはゲーム全般に影響を及ぼしますが、特に瞬間的な判断や操作が求められるジャンルにおいては、その影響がより顕著に現れます。中でもFPS(ファーストパーソン・シューティング)や格闘ゲーム(格ゲー)は、わずかな遅れが勝敗に直結することも少なくありません。
ここでは、以下の3つの観点からディレイの具体的な影響を解説します。
- FPS|撃ち負ける原因になるエイムずれ
- 格ゲー|コンボがつながらない、ガードが間に合わない
- 対戦ゲームでは命取りになるケースも
各項目を通じて、ディレイがプレイにどのような支障を与えるのかを把握しましょう。
FPS|撃ち負ける原因になるエイムずれ
FPSでは、マウスやコントローラーの操作によって照準(エイム)を合わせ、瞬時に発砲する正確さが求められます。しかし、ディレイが発生している場合、照準を合わせて撃ったつもりでも、敵の位置に弾が届かないといった現象が起こります。
これは、自分が見ている画面と、実際のゲームサーバー上での状況にズレが生じることによって起きるもので、反応が一瞬遅れるだけで撃ち負ける原因になります。特に競技性の高いFPSタイトルにおいては、数フレームのズレが勝敗を分ける場面も珍しくありません。
格ゲー|コンボがつながらない、ガードが間に合わない
格闘ゲームでは、フレーム単位での正確な入力が求められます。コンボを成立させるためには、特定の技を特定のタイミングで繋ぐ必要があり、ここにディレイが介入すると本来つながるはずの攻撃がミスになることがあります。
また、防御面でも影響は深刻です。相手の攻撃モーションを見てからガード入力をしても、ディレイのせいで間に合わず被弾してしまうといったケースは、初心者だけでなく中級者以上でも頻発します。こうした不利な状況は、実力とは関係なく敗北を招く原因になりかねません。
対戦ゲームでは命取りになるケースも
FPSや格ゲーに限らず、MOBAやRTSといった他ジャンルの対戦型ゲームでも、ディレイは重大な問題となります。たとえばスキル発動やアイテム使用のタイミングが遅れたことで、敵に先手を取られてしまうなど、状況判断と行動が直結しているゲームでは命取りになり得ます。
また、ディレイの存在がプレイヤーの判断力や反応速度の評価に影響を与えることもあります。実際には的確な操作をしていても、遅延によって失敗したように見える場面では、自己評価やチーム内での信頼にも影響を及ぼしかねません。
eスポーツのような競技性の高い世界では、このような環境要因への理解と対策が選手の評価にも関わるため、非常に重要なポイントとなります。
ゲーム以外で使われる「ディレイ」の意味と事例

ディレイという言葉はゲーム分野だけでなく、音響・DTM、映像・放送、通信・ネットワークなど、さまざまな場面で使われています。ここでは、それぞれの分野におけるディレイの意味と、具体的な活用例や発生原因について解説します。
- 音響・DTM:音を遅らせて残響や広がりを作るエフェクトとしての役割
- 映像・放送:映像や音声を意図的に遅らせる技術や安全管理のための仕組み
- 通信・ネットワーク:データ送受信の遅延やレスポンス速度に関する要素
それぞれの分野でのディレイの特徴を理解することで、より幅広い意味を正しく把握できるようになります。
音響・DTMにおけるディレイ
音響やDTM(デスクトップミュージック)の分野で使われるディレイは、入力した音を一定時間遅らせて再生し、残響や反響を生み出すエフェクトを指します。
ギターやシンセサイザーなどの演奏にディレイを加えることで、音に奥行きや立体感を持たせられるのが特徴です。主なパラメータには「ディレイタイム(遅延時間)」「フィードバック(反復回数)」「ミックス(原音との割合)」があり、これらを調整することで短い反響音から幻想的な空間音まで幅広い効果を作れます。
代表的な使い方としては、ロックやポップスでのスラップバックディレイ、ダンスミュージックでのリズミカルなエコー効果などがあります。音響分野でのディレイは、単なる遅延ではなく、楽曲の雰囲気や演奏の迫力を引き出す重要な表現手段となっています。
映像・放送におけるディレイ
映像や放送の分野で使われるディレイは、映像信号や音声信号を意図的に遅らせる技術を指します。
代表的なものは「放送ディレイ」と呼ばれるもので、生放送中に予期せぬトラブルや不適切な発言があった際に、数秒間の遅延を設けて映像や音声をカットできる仕組みです。さらに、大規模イベントやライブ配信では、カメラ映像と会場スピーカーの音声を同期させるためにディレイを設定することがあります。これにより、映像と音がズレて違和感を与える現象を防止できます。
映画制作やテレビ収録でも、特殊効果やカメラ切り替えのタイミング調整としてディレイが活用される場面は少なくありません。放送や映像分野でのディレイは、視聴者体験を損なわず、安全かつスムーズな配信を実現するための欠かせない技術です。
通信・ネットワークのディレイ
通信やネットワークの分野におけるディレイは、データが送信元から受信先に届くまでの遅延時間を意味します。
オンラインゲームやビデオ通話で操作や会話がワンテンポ遅れる現象も、この通信ディレイによるものです。発生原因は多岐にわたり、回線の混雑、サーバーの処理速度、物理的距離、無線通信の不安定さなどが挙げられます。
特にリアルタイム性が求められる分野では、この遅延が快適さや競技性に直結します。そのため、対策としては有線接続の利用、高性能ルーターや低遅延対応機器の導入、サーバーの地理的分散化などが有効です。
通信ディレイは完全にゼロにはできませんが、原因を特定し適切に改善することで、快適なオンライン体験を実現することが可能です。
ディレイの測定方法と確認のポイント

ディレイは数値化して初めて改善効果を正確に判断できます。ここでは、ゲーム・通信・音響それぞれの分野で使える測定方法を紹介します。
環境に合わせた測定手順を知っておくことで、原因特定や改善策の検証がスムーズになります。
ゲームでのディレイ測定方法
多くのオンラインゲームでは、設定画面やトレーニングモードで「入力遅延」や「Ping値」を表示できます。Ping値はサーバーとの応答速度を示し、数値が小さいほど快適です。
目安としては30ms以下が理想、50msを超えると操作遅れを感じやすくなります。測定時は複数回確認し、安定しているかどうかもチェックしましょう。
通信環境のディレイ測定方法
通信ディレイはSpeedtestなどの無料計測サイトや、パソコンのコマンドで測定できます。
Windowsでは「ping」や「tracert」、Macでは「ping」や「traceroute」を使ってサーバーまでの応答時間や経路を調べられます。回線混雑時やWi-Fi環境では数値が悪化しやすいので、時間帯を変えて計測することも重要です。
音響・DTMでのディレイ測定方法
音響やDTMでは、オーディオインターフェース付属のソフトや専用アプリでミリ秒単位のレイテンシを確認できます。
測定時はサンプリングレートやバッファサイズを設定し、その変更が遅延にどう影響するかも試してみましょう。録音時に遅延が大きい場合は、ハードウェア直結モニタリングなどのゼロディレイ機能を使うと改善できます。
ディレイ測定結果の目安表
| 分野 | 数値の目安 | 状態 | コメント |
| ゲーム(Ping値) | 0〜30ms | 快適 | 遅延をほぼ感じずプレイ可能 |
| 30〜50ms | やや遅延 | 素早い操作では違和感が出る可能性あり | |
| 50ms以上 | 注意 | 操作遅延や同期ズレが顕著に発生 | |
| 通信(レイテンシ) | 0〜50ms | 快適 | Web会議や配信でも問題なし |
| 50〜100ms | やや遅延 | 会話のテンポが崩れることがある | |
| 100ms以上 | 注意 | 通信ラグが目立ち、リアルタイム性が損なわれる | |
| 音響(レイテンシ) | 0〜5ms | 快適 | 演奏や録音で遅延を感じない |
| 5〜10ms | 許容範囲 | 一部の演奏で違和感が出る可能性あり | |
| 10ms以上 | 注意 | 演奏や録音で明らかなズレを感じる |
「ディレイ」が起きる原因とは?

ディレイは、単に「ネットの問題」と片付けられるものではなく、複数の要素が複雑に絡み合って発生する現象です。原因を正確に理解することは、適切な対策につなげるうえで極めて重要です。
ここでは、ディレイを引き起こす主な3つの要因について詳しく解説します。
- ネットワーク(回線やPing値)による影響
- PC・ゲーム機・周辺機器のスペック
- ゲーム側の遅延設定やオンライン環境
それぞれの要因がどのようにディレイを生み出すのかを把握し、今後の環境改善に役立てましょう。
ネットワーク(回線やPing値)による影響
もっとも代表的な原因のひとつが、インターネット回線の品質や接続方法の問題です。特に重要なのが「Ping値」と呼ばれる数値で、これはプレイヤーの端末とサーバー間で通信が往復するのにかかる時間を示します。
Ping値が高い、つまり通信に時間がかかる状態では、プレイヤーの操作がサーバーに届くまでに遅延が生じ、相手より一歩遅れた動きになってしまうのです。
また、無線接続(Wi-Fi)は電波干渉やルーターとの距離によって通信が不安定になりやすいため、できるだけ有線接続を利用することが推奨されます。
実際、eスポーツの発展を受け、「eスポーツでも安定する回線」を売りにしている業者が出てくるほど、回線環境は重要視されています。
参照:フレッツ光・多彩なeスポーツライフに常時接続するフレッツ光最大概ね10G 速さの裏側 | e-Sports360
PC・ゲーム機・周辺機器のスペック
ハードウェアの性能も、ディレイを引き起こす大きな要因の一つです。たとえば、CPUやグラフィックボードの性能が不足していると、ゲームの処理が追いつかず、操作が画面に反映されるまでに時間がかかることがあります。
また、使用しているモニターやキーボード、コントローラーなどの周辺機器にも“入力遅延”が存在する場合があります。特に古いモニターやテレビでは、映像処理の過程で遅延が発生しやすいため、ゲーミングモニターの使用が望ましいとされています。
快適なプレイ環境を整えるためには、ネット環境だけでなく、デバイス全体の性能を見直すことが効果的です。
ゲーム側の遅延設定やオンライン環境
意外に見落とされがちなのが、ゲームソフト自体の仕様やオンライン環境です。一部のゲームでは、入力に対して意図的にディレイを設けている設計が採用されており、これが操作感に大きな影響を与えることもあります。
また、オンライン対戦においては、対戦相手の回線状況やサーバーの混雑具合も遅延の原因になります。とくに海外サーバーと接続している場合、日本からの通信距離が長いため、Ping値が高くなる傾向があります。
このように、個人側の環境だけでなく、ゲームそのものや対戦相手の環境にも影響されるという点を理解しておくことが重要です。
ディレイ配信とは?チート対策や大会運営で使われる理由

ゲームにおける「ディレイ」は操作の遅延だけではありません。配信の世界でも「ディレイ」が重要な役割を果たしているのをご存じでしょうか。
特に近年のeスポーツシーンでは、不正行為(チート)や試合の公平性確保のために「ディレイ配信」が積極的に取り入れられています。
このセクションでは、以下の4つの観点から「ディレイ配信」について詳しく解説します。
- そもそも「ディレイ配信」とは何か
- なぜ配信にディレイを入れるのか
- eスポーツ大会でも導入されることが多い理由
- 配信者・選手の立場から見たメリットと注意点
それぞれの視点から知ることで、ディレイ配信を深く理解できるはずです。
そもそも「ディレイ配信」とは何か
ディレイ配信とは、実際のプレイから数秒〜数分遅れて配信映像を視聴者に届ける方法を指します。リアルタイムでプレイしている最中でも、視聴者が見ているのは少し前の場面という状態になります。
この遅延設定は配信ソフトやプラットフォームの機能として簡単に導入でき、配信者自身が意図的に「何秒遅らせるか」を設定できるのが特徴です。
なぜ配信にディレイを入れるのか
ディレイ配信が最も重要とされる理由は、ゴースティング(Ghosting)対策にあります。ゴースティングとは、対戦相手が配信を視聴しながらプレイヤーの位置や戦略を不正に把握し、有利に立ち回る行為です。
これは明確な不正行為であり、公平な競技を妨げる重大な問題となります。特に賞金やランキングがかかったeスポーツの試合では、このような行為が発覚すると即失格となることも珍しくありません。
しかしディレイ配信を導入することで、相手が配信を見たとしてもリアルタイムの情報を取得できなくなるため、不正の抑止力として非常に有効です。
eスポーツ大会でも導入されることが多い理由
現在のeスポーツ大会では、ほぼ標準的にディレイ配信が導入されています。これは大会運営側が選手の安全・公平性・視聴者体験すべてを守るための措置でもあります。
たとえば、会場に観客がいるオフライン大会では、配信を見ている観客が選手に情報を伝える“外部からのゴースティング”のリスクもあります。そのため、競技の本番中には数分〜10分程度の配信遅延が設けられることが多いのです。
また、運営側がトラブル発生時に映像を調整したり、不適切なシーンをカットするためのバッファとしても機能します。
配信者・選手の立場から見たメリットと注意点
ディレイ配信には、配信者や選手にとっても複数のメリットがあります。まず第一に、安心して競技に集中できる環境が得られるという点です。戦略や位置情報をリアルタイムで漏らす心配がなくなり、心理的にも落ち着いてプレイに専念できます。
また、事前に対戦相手のリサーチを受けにくくするという利点もあり、特にトーナメントなどで戦略性が高いゲームにおいては重要なポイントです。
ただし、視聴者とのインタラクションが遅れるため、チャットの反応や実況解説とのズレが生まれる点には注意が必要です。ストリーマーとして活動する場合には、この影響をどう緩和するかも考慮する必要があります。
「ディレイ」への対策方法|すぐにできる改善策

ディレイはプレイヤーの実力とは関係なく、環境によって発生するものです。そのため、根本的な原因を把握したうえで、できる範囲で改善を図ることが重要となります。
ここでは、日常的に実践できる代表的な改善策として、次の4つのポイントをご紹介します。
- 有線接続に切り替える
- ルーターやモデムを最適化する
- ゲーム設定・画質を見直す
- 周辺機器(モニター・キーボードなど)の見直し
少しの工夫でプレイ環境が大きく変わることもあります。すぐに取り入れられる対策から順に見ていきましょう。
有線接続に切り替える
もっとも効果的で手軽な対策が、無線(Wi-Fi)から有線接続に切り替えることです。Wi-Fiは周囲の電子機器や壁などの障害物の影響を受けやすく、通信の安定性に欠ける場合があるため、ラグやディレイが発生しやすい傾向にあります。
一方、有線LANは直接ルーターと接続されており、データの送受信が安定しやすいという大きな利点があります。特にFPSや格闘ゲームといった、シビアな反応速度が要求されるゲームでは、有線接続が事実上の必須条件とも言えるでしょう。
eスポーツに限らず、有線接続はwi-fi接続より安定性に優れているため、無線環境でディレイが発生する場合は有線環境を検討してみましょう。
参照:プラネックスコミュニケーションズ株式会社・Wi-Fiは便利ですが、有線LANは速さと安定性の高さが魅力
ルーターやモデムを最適化する
通信機器自体の見直しも、ディレイ改善に直結します。長年使用しているルーターやモデムは、内部処理速度が遅くなったり、最新の通信規格に対応していないことがあります。
また、複数の端末を同時に接続していると、帯域が分散されてゲームへの通信速度が不安定になることもあります。これを防ぐためには、QoS(Quality of Service)設定でゲーム通信を優先するといった工夫も効果的です。
ルーターの再起動やファームウェアの更新といった基本的なメンテナンスも、定期的に行うことで安定性が向上します。
ゲーム設定・画質を見直す
ゲームの設定項目を調整することで、ディレイの影響を軽減できる場合もあります。たとえば、高画質・高解像度設定にしていると、処理負荷が大きくなり、フレームレートや応答速度が低下する可能性があります。
特にスペックに余裕のない端末を使用している場合には、画質を中程度以下に落とし、動作の安定性を優先することが有効です。また、一部のゲームでは「入力遅延軽減モード」や「パフォーマンス優先」などの設定が用意されていることもあるため、自分のプレイスタイルに合わせた調整が可能です。
周辺機器(モニター・キーボードなど)の見直し
プレイ環境を本格的に整える場合は、モニターや入力デバイスにも注目すべきです。特にモニターは、リフレッシュレートや応答速度の数値がゲーム体験に大きな影響を与える要素のひとつです。
ゲーミングモニターであれば、リフレッシュレート144Hz以上、応答速度1ms以下の製品を選ぶことで、より滑らかな映像表示が可能となり、ディレイを体感しにくくなります。
また、キーボードやマウス、コントローラーの入力遅延(インプットラグ)も意外に見落とされがちなポイントです。反応速度の速いゲーミングデバイスを導入することで、プレイ精度の向上につながる可能性があります。
ゲームにおけるディレイの意外なメリットとは?

「ディレイ=遅延=悪」と思われがちですが、実は一部のゲームではあえて遅らせることが有効な場面も存在します。ここでは以下のようなポジティブな使い方を紹介します。
- 読み合いで相手の反応をズラせる【格闘ゲーム】
- ディレイアクションでタイミングをコントロール【MOBA・RTS系】
- PvEではむしろ“安全策”になることも【MMORPG】
- ディレイが生む“重さ”がゲーム演出に寄与することも
ディレイは戦略や設計思想次第で、プレイの奥深さを広げてくれる武器にもなるのです。
読み合いで相手の反応をズラせる【格闘ゲーム】
格闘ゲームでは「ディレイ入力(遅らせた入力)」が、駆け引きの大きな武器になります。たとえばコンボ中の一部をわざと遅らせて入力することで、相手が割り込みを狙ったり、早めにガードを解除したりといったミスを誘えるのです。
これはフェイントの一種であり、上級者同士の心理戦では極めて重要なテクニックとされています。ディレイによって相手の反応をズラし、読み合いの主導権を握ることができるのです。
格闘ゲームに関しては下記で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
eスポーツで注目される格闘ゲームの種類を紹介!歴史や魅力も徹底解説
ディレイアクションでタイミングをコントロール【MOBA・RTS系】
MOBAやRTSといった戦略系のゲームでは、ディレイを利用して相手の動きや味方のスキルとタイミングを調整することがあります。たとえば、敵の回避を読んでスキルをわざと遅らせて発動することで、かわされずに命中させる狙いが生まれます。
また、味方との同時攻撃タイミングを合わせるために、ディレイアクションを使うことで連携プレイの精度が向上するケースも。即時反応だけが正解ではない、という点に深い戦術性が見られます。
PvEではむしろ「安全策」になることも【MMORPG】
MMORPGなどのレイドコンテンツでは、早まった行動よりも敵の攻撃動作を見てからのディレイ行動が有効なケースが多くあります。たとえばヒーラーやタンク職は、敵の大技を確認してからスキルを使うことで、ミスを防ぎチーム全体の安定性を高められるのです。
また、回避行動も先読みで動くより、ワンテンポ遅れて確実に避ける方が安全な場面も。これは「落ち着いて反応すること」を推奨するゲームデザインともいえます。
PvEに関しては下記で詳しく解説しています。興味のある方は是非そちらもチェックしてみてください。
PVEとは?意味やPVPとの違い、ジャンル別の特徴をわかりやすく解説!
ディレイが生む「重さ」がゲーム演出に寄与することも
一部のアクションゲームやRPGでは、攻撃のモーション後に意図的なディレイ(硬直や反応の遅さ)が設計されています。これにより、武器の重さや攻撃の威力をリアルに表現し、プレイヤーに手応えを感じさせる演出効果を生んでいます。
たとえば「モンスターハンター」シリーズでは、ヘビィボウガンや大剣の攻撃後にディレイがあることで、武器ごとの個性と没入感が強調されるのです。つまり、ディレイは「リアリティ演出」の重要な要素でもあるのです。
ディレイを理解することは、勝率UPにもつながる!

「ディレイ」は単なるストレス要因ではなく、プレイの質や勝率に直結する重要なテーマです。とくにeスポーツのように競技性の高い環境では、ディレイへの理解と対策がプレイヤーとしての評価を左右する場面もあります。
ここでは、以下の3つの視点から「なぜディレイを知ることが重要なのか」を考えていきましょう。
- スキルではなく環境が原因のこともある
- 競技性が高いゲームほど対策が重要になる
- eスポーツでは「勝てる環境づくり」が大切
ディレイを知り、適切に対処することで、自分本来の実力を発揮しやすくなります。
スキルではなく環境が原因のこともある
ゲームにおいて思い通りの操作ができないと、つい「自分の腕が悪い」と感じてしまいがちです。しかし実際には、プレイヤーの操作スキルではなく、通信環境や機材が原因でミスが起きているケースも多くあります。
たとえば、回線が不安定だったり、モニターの応答速度が遅かったりするだけで、反応の遅れや入力ずれが発生し、結果的に敗北につながることもあります。
自分の実力を正しく把握するためには、まずプレイ環境を整えることが前提となります。技術の向上だけでなく、環境の最適化にも目を向けることで、より効果的に成長できるはずです。
競技性が高いゲームほど対策が重要になる
FPSや格闘ゲームなど、わずかな反応速度が勝敗を左右するジャンルでは、ディレイの影響が特に大きく表れます。そのため、プロやハイレベルなプレイヤーほど、通信環境・デバイスの選定に細心の注意を払っています。
たとえば、プロチームの選手は対戦時に必ず有線接続を使用し、ラグを最小限に抑えるようにしています。また、モニターやマウスなどのデバイスにもこだわり、「反応速度の遅延を限りなくゼロに近づける」ことを前提とした環境構築を行っています。競技レベルで勝ち続けるには、技術面だけでなく、環境面も同じくらい重要であることを理解する必要があります。
eスポーツでは「勝てる環境づくり」が大切
eスポーツにおいて成果を出すためには、自分のパフォーマンスを最大限に引き出せる環境を整えることが不可欠です。これはプロ選手に限らず、学生チームやアマチュア大会でも同様です。
適切な回線・機材・プレイ設定を整えることで、ミスを減らし、自分の戦術や反射神経を正しくゲームに反映させることが可能になります。また、ディレイによる誤解(例:仲間からのミス扱いなど)を防ぎ、チームの信頼関係を保つうえでも環境整備は有効です。
環境については下記で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
ディレイに関するよくある質問(FAQ)

「ディレイとは?」と検索する方の中には、日常の中で突然「なんか遅れてる…」と違和感を抱く人も多いはず。ここでは、ゲームや通信、音響の現場でよく聞かれるディレイの疑問をQ&A形式で解説します。
Q1. ディレイとラグの違いは何ですか?
A:「ディレイ」はシステム的・物理的な遅延全般を指す言葉で、入力や通信、音の反響など広い分野に使われます。
一方で「ラグ」は、主にゲームプレイ中に体感するカクつきや止まるといった現象を指す表現です。つまり、ディレイ=仕組みの遅れ/ラグ=プレイヤーが感じる遅れという認識でOKです。
Q2. FPSゲームでのディレイはなぜ起こるの?
A:FPSにおけるディレイは、ネットワーク回線の遅延(ping値)や使用デバイスの性能差などが原因で起こります。
無線接続やスペック不足のPCでは、操作と反応に微妙なズレが発生し、エイムや撃ち合いに悪影響を及ぼします。モニターの応答速度やマウスのポーリングレートも関係するため、環境全体の見直しが必要です。
Q3. 音楽でのディレイってどういう意味ですか?
A:音楽業界で「ディレイ」というと、音を意図的に遅らせて反響や残響のような効果を加えることを指します。ギターやボーカルにかけることで、奥行きのある音作りが可能になります。これは「遅れてしまう」ネガティブな意味ではなく、演出としての遅延効果です。
Q4. Zoomやオンライン通話の声の遅れもディレイ?
A:はい、あれも典型的なディレイ現象です。Zoomなどのビデオ会議アプリでは、通信回線の速度やPCスペックの影響で音声が届くのに時間がかかることがあります。
これにより、相手の声が遅れて聞こえたり、自分の発言に被って話されたりするなど、会話のテンポがズレる原因になります。
Q5. ディレイを減らすにはどうすればいい?
A:使用している機器や回線によって対策は異なりますが、基本的には以下のような方法が有効です。
- 有線接続に切り替える(Wi-Fiよりも安定)
- ゲーミングモニターを使用する(応答速度1ms以下)
- 処理能力の高いPCやルーターを導入する
- ソフト側の設定(遅延補正)を調整する
快適な操作感や音響体験のために、原因に合った対策を選ぶことが重要です。
まとめ
本記事では、ゲームプレイにおける「ディレイ」について、意味や原因、具体的な影響から改善方法までを詳しく解説してきました。
ディレイは、ネットワーク環境や使用デバイス、さらにはゲーム自体の仕様によって生じるものであり、決してプレイヤーのスキル不足だけが原因ではありません。特にFPSや格闘ゲームなど、競技性の高いジャンルにおいては、わずかな遅延が勝敗を分ける要因になることもあります。
だからこそ、プレイヤーとして成長するためには「勝てる環境」を整えることが重要です。それはネット回線やモニターといった物理的な環境だけでなく、自分のスキルを正しく学び、高めていける「身を置く場所」という意味でも同様です。
たとえば、eスポーツスクール「AFRAS」では、プロも活用する最適な環境下で、ディレイ対策の知識や実戦的なスキルを体系的に学ぶことができます。技術面だけでなく、戦略的思考・チームコミュニケーション・大会運営の知識まで幅広く学べるため、「本気で上達したい」「将来eスポーツに関わりたい」と考えている方にとっては最適な選択肢となるはずです。
eスポーツスクールのスキルアップをと考えている方は、是非一度AFRASをチェックしてみてくださいね。