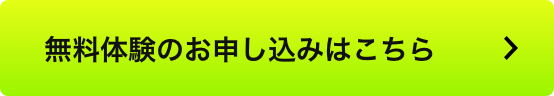ゲームをしているなかで、異常に強いプレイヤーに遭遇したことはありませんか?もしかすると、相手はチート行為をしているかもしれません。
今回は、不正に自分が有利な状況を作ることができるチートについて紹介します。チートがどのような行為なのか、なぜチート行為が禁止されているのかなどを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
ゲームにおけるチートとは何のこと?

チートとは、コンピューターゲームにおいて重大な不正行為を表す言葉です。プレイしている限り、絶対に起こりえない事象を不正に引き起こすことで、ゲームを有利にすすめる行為を指します。
チートは、主にハッキングや外部ツールなどを用いた不正行為を指し、ゲームの仕様のなかで特殊なコマンドを入力したり条件を満たすことで発動したりする「裏技」とは異なります。裏技の場合は、製作者が意図して組み込んでいるため、チート行為と認定されることはないでしょう。
また、チート行為をするプレイヤーを「チーター」と呼び、ゲーム業界全体でチーターおよびチート行為を非難し、撲滅させる動きがあります。ゲームは公平性のうえで楽しむものです。不正に改造したシステムを利用して優位に立つことは、ゲーム本来の公平性を著しく損ねてしまう非常に危険な行為です。
チートの語源

チートの語源は英語の「cheat」であると言われています。「イカサマ、不正行為、騙す」などの意味を持ち、不正を行う人そのものを指す意味でも用いられることがあります。
人間関係においても「裏切り」や「浮気」などの意味を持って使われることがあります。
近年、チートという言葉の認知が広がり「チート級に強い」「そんなに強いなんてチートじゃん」など、誉め言葉のニュアンスを含ませて気軽に使う人も少なくありません。日本人であれば、意図した通りに言葉が伝わるかもしれませんが、オンラインゲームなどで外国人とコミュニケーションをとる際には注意が必要です。チートの持つさまざまな意味を理解しておかなければならないでしょう。
安易に「チート」という言葉を使ってしまうと、思わぬトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。
チート行為の種類と分類
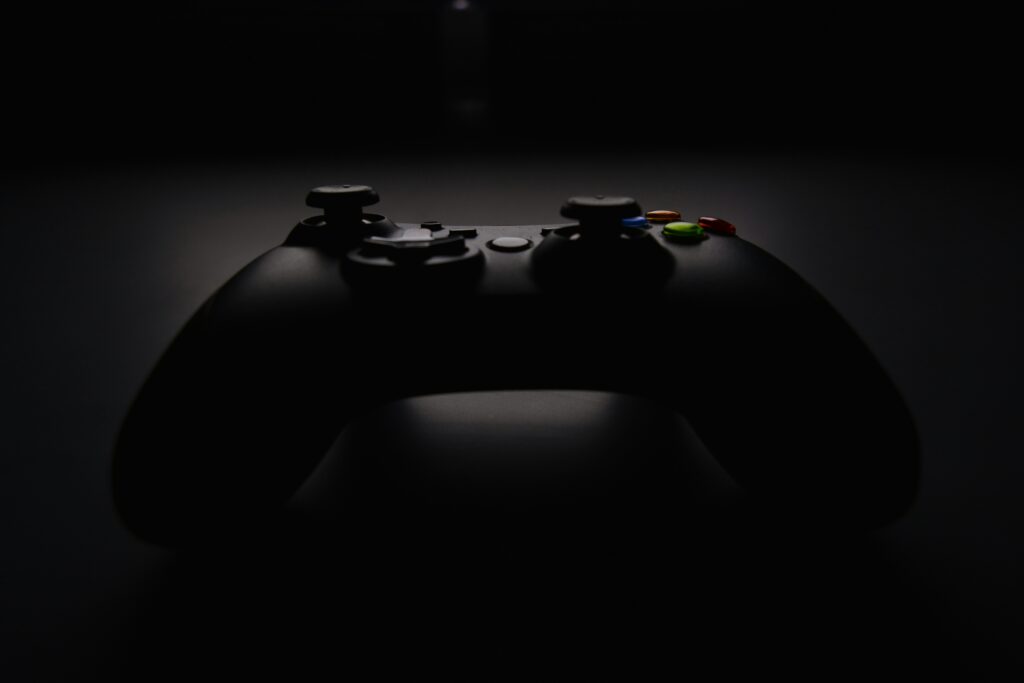
チート行為は、その手口や使用する道具によっていくつかの種類に分けられます。中でも代表的なのが以下の3つです。
- ソフトウェア型チート(aimbot、wallhack、マクロツールなど)
- ハードウェア型チート(改造コントローラー、入力遅延軽減デバイス)
- アカウント不正利用型(乗っ取り、代行プレイ)
いずれもゲームの公平性を損ない、発覚すればアカウント停止や大会出場禁止など厳しい処分が下されます。ここからは、それぞれの特徴や仕組み、発覚リスクについて詳しく見ていきましょう。
ソフトウェア型チート
ソフトウェア型チートは、外部プログラムや改造データを使ってゲーム内の挙動を不正に操作する手法です。代表的な例としては、敵を自動で照準に捉える「aimbot」、壁越しに敵の位置や動きを表示する「wallhack」、複雑な操作をワンタッチで実行できる「マクロツール」などがあります。
これらはゲームデータや描画情報を直接改ざんするため、アンチチートシステムによって検出されやすく、発覚した場合は即時アカウント永久停止となるケースが大半です。また、近年はAIを用いた自動検出技術が進化しており、以前よりも発覚リスクは格段に高まっています。
ハードウェア型チート(改造コントローラー、入力遅延軽減デバイス)
ハードウェア型チートは、物理的な機器や周辺機器を改造・追加することで不正な有利性を得る方法です。例えば、連射機能や自動入力機能を搭載した改造コントローラー、入力信号の遅延を限りなく減らす専用デバイスなどが該当します。
これらはソフトウェアのようにプログラムで検出することが難しく、一見すると正規のプレイと区別がつきにくい点が特徴です。しかし、大会や公式イベントでは機器検査が行われることが多く、発覚すれば失格処分や賞金剥奪といった厳しい措置が取られます。
アカウント不正利用型(乗っ取り、代行プレイ)
アカウント不正利用型は、自分以外の第三者が不正にアカウントを使用してゲームをプレイする行為です。代表的なのは、ハッキングやフィッシング詐欺によるアカウント乗っ取り、そして高ランク帯への昇格やイベント報酬獲得を目的とした「代行プレイ」です。
この手口はプレイヤー本人が直接チートツールを使わなくても成立するため、気づかないうちに規約違反となる場合もあります。発覚すれば利用者と不正を行った第三者の両方が処分を受ける可能性が高く、さらに乗っ取りの場合はアイテムや課金データの消失、個人情報流出など二次被害にもつながります。
チート行為の具体的な例

チートにはさまざまなケースがありますが、大きく分類して以下の3つに分けられます。
ステータスを強化するチート
不正なソフトウェアなどを利用して、自分自身の操作するキャラクターのレベルを本来の仕様とは異なる方法でアップさせるチートがあります。
ステータスを上昇させる、武器や防具の規定攻撃値、防御値を変更するといったチートも見られます。
ゲーム内通貨を操作するチート
チートのなかには、不正な方法でゲーム内通貨を増やすものもあります。これによりレアなアイテムを獲得したり、ガチャを回したりする例も方向されています。特に、スマホゲームでは「複製技」と呼ばれ、ゲーム内の課金通貨を不正に操作する悪質な行為です。
公平性を操作するチート
多くのゲームは、それぞれのプレイヤーが公平性を保ったうえで楽しめるようプログラムされています。プレイヤーの技術や戦略を除き、キャラクターや武器の性能などを調整し公平な条件でゲームを楽しめるようにさまざまな工夫が行われ、尚且つアップデートによって改善されているのです。
チートでは、オートエイム(自動標準)やウォールハック(壁やオブジェクトの影に隠れており、本来なら見えない相手を見えるようにすること)などを不正に機能させてゲームの公平性を損なうものがあります。コンピューターゲームの不正改造とされ、法律に抵触する可能性もあるチートのひとつです。
チートと勘違いされているスキル

チート行為とよく似ているようで、実際にはチートではないプレイ手法も存在します。
ここでは、プレイヤーの間で混同されやすい代表的なスキル「グリッチ」「リセマラ」「スナイプ」を取り上げ、それぞれの特徴やチートとの違いを解説します。誤解を避け、正しいゲームプレイの理解を深めましょう。
チート行為とグリッチの違い
バグ技(グリッチ)とは、ゲームシステムにおいて製作者が想定していないバグを利用した技を指します。バグ技を用いてプレイすることで、ゲームを有利に進められることもあるため、ある意味ではチートと非常によく似た性質を持っていると言えます。
しかし、バグ技はあくまで製作者が用意したコンピューターソフトのなかで発生している現象であるため、基本的に利用の有無はプレイヤーの判断で行われます。製作者の意図しない現象であることから、フリーズする、データが消える、などのイレギュラーなトラブルが起こることも考えて利用する必要があるでしょう。
一方、チートは外部ツールを用いてシステムを改ざんして行う不正行為なので、バグ技と違い、ゲーム運営から大きなペナルティを受ける可能性が高いです。場合によっては、不正アクセス禁止法など、法律に抵触する可能性も少なくありません。
グリッチに関しては下記の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
ゲーム用語の「グリッチ」を徹底解説!あり?なし?有名なグリッチ技も紹介
チート行為とリセマラの違い
リセマラ(リセットマラソン)は、スマートフォンゲームなどで初回ガチャやキャラクター抽選の結果に満足できない場合、アプリをアンインストールして再度やり直す行為を指します。
多くのゲームでは仕様として想定されており、リセマラ自体はチートではありません。
しかし、外部ツールや自動操作プログラムを使ってリセマラを繰り返す行為は、チートとみなされる可能性があります。
「ゲーム内で用意された範囲でのやり直し」か「外部プログラムによる不正操作」かが、チートとの明確な線引きです。
リセマラについては下記で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
リセマラ(リセットマラソン)とは?意味ややり方、おすすめのゲームについても解説
チート行為とスナップの違い
スナイプとは、特定の配信者やプレイヤーと同じマッチに参加するために、タイミングを合わせて意図的にマッチングを狙う行為を指します。
仕組み上はチートツールを使用しないため、スナイプそのものはチートではありません。
ただし、スナイプを悪用して配信を妨害したり、相手の位置情報を配信から特定して不正に有利を取る「ゴースティング行為」に発展した場合は、明確な規約違反になります。
スナイプはマナーを守って行う分には問題ありませんが、他プレイヤーの体験を損なう行為に変わる瞬間があるため、倫理観を持ったプレイが求められます。
スナイプやゴースティングについては下記で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
ゲームの「スナイプ」とは?ゴースティングの意味やマナー違反と言われる理由も解説
チート行為と呼ばれる「グレーゾーン」のプレイとは?

チートツールの使用やデータ改ざんのように明確な不正ではないものの、「これはチートでは?」と議論されるグレーゾーンのプレイスタイルも存在します。
特に位置情報ゲームやスマホゲームでは、クライアントに手を加えずとも不正ができる手段がいくつかあります。以下に代表的なものを紹介します。
GPS改ざんツールによる位置偽装(位置情報ゲーム)
ポケモンGOやドラクエウォークといった位置情報ゲームでは、本来であれば実際に移動しなければならない距離を、GPSの位置情報を改ざんするアプリなどでテレポートしてしまう手法があります。
これはゲームクライアントには手を加えていないため、使っている本人は「改造していないからOK」と認識している場合もありますが、公式には明確に不正行為として禁止されており、BANや警告対象となります。
検出はOSのログや通信挙動から行われることが多く、特に移動速度・位置変化の不自然さが判断材料になります。
マルチエミュレーターや仮想環境でのプレイ
スマホアプリをPC上でプレイできるエミュレーター(例:BlueStacks、NoxPlayerなど)や仮想環境上でのプレイも、一部ゲームでは利用規約で禁止されています。
これによりPCでマウス&キーボード操作が可能になり、本来の想定デバイスとは異なる操作性で有利に立ち回れることがあります。
ただし、公式が明示的に「PC利用OK」としているゲームもあり、ルールの明確化が曖昧なことから「グレー」と呼ばれることが多いのです。
VPNや時間改ざんで特定イベントを強制発生させる
ゲーム内イベントが「特定の国・地域・時刻」で発生する場合、VPNで接続地域を偽装したり、スマホの時刻設定を変更することで、通常アクセスできないコンテンツを強制的に発生させる行為もあります。
これも技術的にはチートツールではありませんが、多くのゲームでは利用規約で禁止されているため、発覚すればアカウント停止の可能性があります。
サブアカウント作成による有利プレイ
同じゲームで複数のアカウントを作成し、本来のメインアカウントとは別の立場からプレイする行為です。
位置情報ゲームやオンライン対戦ゲームでは、低ランク帯で初心者と対戦して勝率を稼ぐ「スマーフ行為」や、イベント報酬を複数アカウントで獲得するなど、ゲームバランスを崩す原因になる場合があります。
一部のゲームでは「サブアカウント作成は自由」としているものの、意図的に不公平なマッチングを作り出す行為や複数報酬の獲得は、規約違反やペナルティの対象となるケースが増えています。
また、サブアカ運用を続けることで管理負担や誤BANリスクも伴うため、安易に行うべきではありません。
スマーフ行為については下記で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
ゲームのマナー違反行為「スマーフ」とは?やってはいけない理由についても紹介
チート行為が禁止される理由

チートが禁止される背景には、さまざまな理由があります。
ゲームバランスが崩壊するから
ゲーム制作会社は、ゲームシステムに公平性を持たせることで多くのユーザーが長く楽しめるゲームを開発しています。自分ばかりが圧倒的に不利なゲームを長くプレイしたいと思う人は少ないでしょう。特にオンラインゲームでは、他のユーザーに勝ったり負けたりすることで、「もっと上手くプレイできるようになりたい」「勝ち続けたい」という意欲が沸き、ユーザーに長くプレイしてもらえる作品になります。
そんななか、チートによって不正に勝利するプレイヤーと対峙したユーザーはどう思うでしょうか。不公平な状況で理不尽に負けを繰り返すゲームを長くプレイしたいと思わないでしょう。
チートによってゲームの公平性が損なわれることは、ユーザー離れを加速させる大きな要因となります。やがて、ユーザー数が減ってしまったゲームはインターネットサービスとして衰退していき、最悪の場合サービス終了に追い込まれてしまう可能性があります。
法的な問題があるから
ゲーム会社が開発したゲームを不正に改造することは、著作権侵害にあたります。また、不正改造したチートプログラムを配布、販売すると、前述したようにゲームバランスの崩壊からユーザー離れが加速してしまうリスクなどが発生するため、業務妨害罪に該当する可能性もあるでしょう。
オンラインゲームでチート行為をするために不正にアクセスしてシステムの書き換えをしようとした場合には、不正アクセス禁止法に抵触します。
このように、チート行為そのものが法律に違反する可能性が高いです。過去にはチートプログラムを配布、販売した者に対し、ゲーム会社が訴訟を起こした例もあります。
RMTを加速させるから
RMTとはリアルマネートレードの略称で、ゲーム内のキャラクターやアイテム、もしくはアカウントなどをリアルマネーで取引することを言います。現在、日本にはRMTを規制する法律はありませんが、詐欺組織などの犯罪の温床になっていることもあります。
RMT自体は違反ではないものの、過去にはチート行為によってゲーム内通貨を増やし、レアキャラクターやレアアイテムを獲得してRMTにより現金化する事件が起きています。こういったケースでは、チートによる不正アクセス禁止法や営業妨害、場合によっては詐欺罪などで刑事告訴される可能性も少なくありません。
現在、国内外でゲーム会社もRMT対策を進めており、法律で規制できなくても、ゲーム会社独自の規約でRMTを禁止するケースが増えてきました。
マルウェアに感染する可能性があるから
チートプログラムを配布する人も見られます。チート用に設計されたプログラムをインストールすることで、専門的な知識がない人でもチート行為ができるようになるのです。
一方で、このようなチートプログラムにマルウェアを仕込む事例も報告されています。マルウェアとは、パソコンに対して悪意のあるウイルスソフトを指します。有名なものなら、トロイの木馬やワームなど、何となく名前を聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。
マルウェアに感染することで、パソコンの情報を抜き取られたり、システムを破壊されてしまったりするリスクがあります。元々、チート行為は世間一般に不正行為とされているため、チートプログラムをダウンロードしたことが原因でマルウェアに感染したことを誰にも言えずに、泣き寝入り状態になってしまっている人もいるでしょう。
個人で配布、販売されているチートプログラムを入手するということは、マルウェア感染のリスクがあるということを理解する必要があります。
チート行為をするとどうなる?

チート行為をしてはいけないと分かっているものの、実際にどのようなペナルティを受けるのかはあまり知られていません。チート行為を行うことで受ける可能性のあるペナルティについてもみていきましょう。
アカウントを停止される
ゲーム開発会社の多くは、チート行為を利用規約で禁止しています。そのため、チート行為が認められたアカウントに対しては厳重な処罰を行い、多くの場合アカウントの永久停止などゲーム規約のなかで最も重いペナルティを課しているケースが見られます。
訴訟される可能性がある
ゲームのなかでも、近年主流となりつつある基本無料プレイが可能なオンラインゲームでは、チートによる被害が甚大なものになるケースが少なくありません。そのため、運営会社側もチートに対する法的措置を検討する可能性が高く、場合によっては民事訴訟などを起こされる可能性があります。
運営会社が受けた被害を弁済するため、損害賠償請求がされるなど、実生活に大きな影響を与える可能性も少なくはありません。「ゲームだから」と気軽に行ったチート行為が原因で、自分自身のリアルな生活がめちゃくちゃになってしまう可能性をしっかりと理解しておきましょう。
なぜチートはバレるのか?

「少しくらいならバレないだろう」と思ってチート行為に手を出す人もいますが、実際には多くのケースで短期間のうちに発覚しています。
ゲーム運営会社は、不正プレイを検知するための高度なシステムを常に稼働させており、人間の手による確認も並行して行われています。
ここでは、チートがどのような仕組みで見抜かれるのか、その代表的な3つの理由を解説します。
システムによる自動検知
オンラインゲームの多くでは、アンチチートツールと呼ばれる検知プログラムが常時作動しています。
これらのツールは、ゲームの挙動を監視し、不自然なデータや動きをリアルタイムで検出します。
たとえば、人間では反応できない速度での照準合わせ、異常な移動速度、サーバー側と一致しないパラメータ変更などが見つかると、自動的にアカウントがフラグ管理されます。
代表的なものには「VALORANT」のVanguardや「PUBG」のBattlEyeなどがあり、OSレベルでの監視を行うことで、改造ツールの使用を未然に防いでいます。
通報とリプレイ検証
もうひとつの重要な検知ルートが、プレイヤーによる通報システムです。
他プレイヤーが「不自然」「怪しい」と感じた行動を通報すると、そのプレイヤーのリプレイ映像やログが運営によって確認されます。
特に、照準が常に頭部に吸い付くような動きや、壁越しに敵の位置を正確に追うような挙動は、AI検知よりも先に人間の目で見抜かれるケースが多くなっています。
また、一定数以上の通報が集まると自動的に審査優先対象となり、1件の通報からアカウント停止に至ることも珍しくありません。
サーバーログの照合
サーバーには全プレイヤーの行動ログが詳細に記録されており、これを定期的にAIが分析しています。
過去のプレイデータと比較して、命中率や行動パターンが極端に変化している場合や、アイテムデータの改ざんが疑われる場合には、自動的に調査対象となります。
このような監視は24時間体制で行われているため、チートはその場でバレないだけであり、後日まとめて検知されるケースも多いのです。
つまり、「今は問題ない」と感じていても、いずれ必ず履歴から不正は見抜かれます。
チート行為の法的見地

チート行為はゲーム規約の違反にとどまらず、日本の法律に触れる可能性があります。具体的には、以下のような法律が関係する場合があります。
- 不正アクセス禁止法
- 著作権法違反
- 不正競争防止法
- 刑法(詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪)
ここではこれらの法律との関係を解説するだけではなく、場合によっては刑事罰や高額な罰金が科されることを明らかにします。
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法は、許可なく他人のアカウントやサーバーへ侵入する行為を禁止しています。チート行為の中でも、他人のアカウントを乗っ取ってプレイする、IDやパスワードを不正取得してランキングを荒らす、サーバー側のデータを直接改ざんするといった行為は、この法律に該当します。
違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され、悪質な場合は両方が併科されることもあります。実際に、人気オンラインゲームで高ランクアカウントを乗っ取ったプレイヤーがこの法律で逮捕された事例があります。
参考:ベリーベスト法律事務所岡山オフィス・SNSアカウント乗っ取りは犯罪? 不正アクセス禁止法違反の罰則
著作権法違反
ゲームのプログラムやデータは著作権法で保護されており、勝手に改ざんすることは翻案権や同一性保持権の侵害になります。チートツールの使用はもちろん、改造データの作成や配布、他人が作った改造データをゲーム内で使うことも違法です。
刑罰は5年以下の懲役または500万円以下の罰金で、悪質な場合はさらに重くなります。過去には、家庭用ゲーム機の改造プログラムを販売していた業者が、この法律違反で有罪判決を受けたケースもあります。
参照:弁護士法人ユア・エース presents ゆっきーのCan Can do it! ・ゲームのチートは犯罪?未成年でも罪に問われる?法律と罰則
不正競争防止法
不正競争防止法は、ゲーム開発者が設けた「技術的制限手段」(コピー防止やアクセス制御など)を回避する装置やプログラムの提供を禁止しています。営利目的でチートツールを販売する行為や、無料で広く配布して利用者を集める行為も対象です。
違反すると5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科され、販売者はもちろん、改造を請け負っただけでも処罰対象となります。特にチート販売は警察が積極的に摘発しており、SNSやフリマアプリ経由での販売でも逮捕事例があります。
参照:Alliance of Valiant Arms・不正プログラム(チートツール)の販売者に対する有罪判決について
刑法(詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪)
ゲーム内通貨やアイテムを不正に入手した場合、それが課金価値を持つものであれば刑法の詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪に該当することがあります。例えば、イベント報酬を位置偽装で取得する、チートで課金アイテムを増殖するなどの行為です。
刑罰は10年以下の懲役が科される可能性があり、実際にオンラインゲームで不正にアイテムを生成し、現金化していたプレイヤーが逮捕された例もあります。こうした事例では、ゲーム内の不正が「現実世界の金銭被害」として扱われるため、刑事事件として非常に重く見られます。
参考:ベリーベスト法律事務所大宮オフィス・チート行為は犯罪! 逮捕事例から問われうる罪、罰則について解説
チート行為の見分け方

オンラインゲームをプレイしている時に、明らかに人間では不可能ではないかと思われるプレイを見かけることがあります。「もしかしてチート?」と思う人もいるでしょう。
一方で、YouTubeなどのゲーム配信を見ていると、驚くべきゲームスキルを持つ人もいるため「チートのように思えるけれど、もしかしたら単純に凄くゲームが上手い人なのかも」と考える人も少なくありません。
その時には以下の点に注目して相手がチート行為をしているかどうか判断してみてください。
- エイムが異常な速さで合っている
- 壁越にエイムが合わされている
- 効率が良すぎる
- 毎回同じプレイで勝利し続けている
チート行為の違和感は、共にプレイした人なら何となく感じるという意見がよく聞かれます。「もしかしてチート?」と思った時には、取り敢えずサポートに通報するのがよいでしょう。本当にチートなのかどうかは、運営会社の方で調査してもらえます。
チートはなぜバレる? よくある質問(FAQ)

ここでは、チート行為に関して多く寄せられる疑問をまとめました。
「どんな場合にバレるのか」「グリッチやリセマラはセーフなのか」など、プレイヤーが誤解しやすいポイントを分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、安心・安全にゲームを楽しみましょう。
Q1:チートを使うと必ずアカウント停止になりますか?
A:多くのオンラインゲームでは、不正検知システムが常時稼働しており、チート行為が確認されると即座にアカウント停止(BAN)となります。
一時的にバレなかったとしても、運営によるサーバーログの照合で後から検知されるケースが大半です。結果的に、チートを使ったアカウントはほぼ確実に処分対象になります。
Q2:チートを使っただけで逮捕されることはありますか?
A:プレイヤー個人がチートを「使用しただけ」で逮捕される例は少ないですが、可能性としては「0」ではありません。また、チートツールを販売・配布する行為は違法です。
日本では「不正競争防止法」や「著作権法」に違反する可能性があり、実際にチートツール提供者が摘発された事例も存在します。使用者も運営から永久BANなどの重い処分を受ける場合があります。
Q3:グリッチ(バグ技)もチートと同じ扱いになりますか?
A:グリッチはゲーム内部の不具合を利用するもので、外部ツールを使用しない限りチートではありません。
ただし、運営が明確に禁止している場合や、対戦の公平性を損なう行為と判断される場合は規約違反として処分されることがあります。
バグを発見した場合は、利用せずに運営へ報告するのが安全です。
Q4:チートをしてもバレない方法はありますか?
A:ありません。近年のオンラインゲームはAIによる検知精度が非常に高く、バレないチートは存在しません。
また、ゲームのバージョン更新によって過去のチートログも照合されるため、一時的に逃れたとしても後から処分される可能性があります。
チートを使わないことだけが、唯一のリスク回避策です。
Q5:もし誤ってチートツールをインストールしてしまったら?
A:まずは即座に削除し、セキュリティソフトでウイルススキャンを行いましょう。
チートツールの多くはマルウェアや情報窃取プログラムを含む危険なファイルです。
また、ログイン情報を盗まれてアカウントが乗っ取られるケースもあるため、パスワードの変更と運営への報告も忘れずに行いましょう。
チート行為は絶対に禁止!スキルを磨くならアフラスの無料体験へ
今回はゲームのチート行為について紹介してきました。不正に自分が有利な状況を作り出すチートは、ゲームを面白くする所かユーザーを減らし、サービスの衰退を招く悪質なものです。気軽に手を出すと、大きなペナルティを受ける場合もあるため、絶対に控えましょう。
また、チート行為をみかけた際には積極的にサポートへ通報し、ゲーム会社がチート対策できるようにすることも重要です。
AFRAS(アフラス)はゲームについて学べるゲーミングスクールです。ゲームは、チート行為をして不正に勝っても面白くありません。スキルや知略を磨いて自分の力で勝利を掴むからこそ楽しめます。ぜひ、AFRASでチートにも負けないスキルや知略を獲得してみませんか。ゲームが圧倒的に上手くなりたい人は、AFRASをチェックしてみてください。