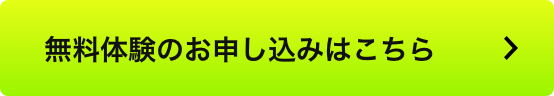コンピューターゲームで勝敗を競うeスポーツ。高度なスキルと知略を必要とするテーブルスポーツですが、eスポーツをよく知らない人からすると「普通のゲームとeスポーツは何が違うの?」という疑問が浮かぶこともあるでしょう。
この記事では、eスポーツと普通のゲームの違いについて紹介します。
eスポーツについて知りたい人やeスポーツプレイヤーを目指している人は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
eスポーツとは何のこと?

eスポーツとは、Electronic Sports(エレクトロニックスポーツ)の略称です。コンピューターゲームを用いて勝敗を競技として国内外で人気が高まっています。
ゲームのプラットフォームは、パソコン、テレビゲーム、スマートフォン、タブレットなど多岐にわたり、それぞれのゲームタイトルごとに明確にルールを定めて競技を行うのが特徴です。
一般社団法人日本eスポーツ協会では、eスポーツの定義を以下として紹介しています。
“「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦スポーツ競技として捉える際の名称”
引用元・一般社団法人eスポーツ協会
娯楽のひとつとして誕生したゲームですが、対戦スポーツとして行うことで新たなジャンルを生み出す事に成功しました。eスポーツは、最新のスポーツと言えます。
eスポーツの歴史

コンピューターゲームが開発されたのは1900年代半ばと言われています。現在のeスポーツの原点となる世界発のゲーム大会は1970年代にアメリカで行われた「スペースウォー!」というゲームタイトルの競技会であるという説が有力です。
続いて、世界的にスペースインベーダーが大流行し、1980年代に行われた同タイトルの大会では全米から1万人近い参加者・観戦者が集まったと言われています。インベーダーブームは日本にも到来し、第一次ゲームブームが始まりました。
1990年代にはストリートファイターシリーズを初めとした、格闘ゲームが流行し、日本でも大規模なゲーム大会が行われ始まます。
2000年頃、韓国でeスポーツという造語が誕生して以降、世界中でeスポーツ大会が盛んに行われるようになりました。2011年には「第1回eスポーツJAPAN CUP」開催、2015年には一般社団法人日本eスポーツ協会設立など、日本でも徐々にeスポーツが浸透し始めます。
2024年にはeスポーツワールドカップが開催され、2026年にはアジア競技会でeスポーツが正式種目として行われる事も決定済です。eスポーツは世界各国で盛り上がりを見せ、徐々に一種のスポーツとして認められ始めています。
eスポーツの競技人口

eスポーツは年齢や男女の性差などの影響を受けにくく同じ条件で競える数少ないスポーツです。そのため、世界中で続々と競技人口を増やしており世界のeスポーツ競技人口は1億人を超えているとも言われています。
国内のeスポーツ人口は約390万人と試算されており、国内のバスケットボール実施人口である504万人※を追いかける形になっています。
eスポーツは歴史が浅いながらも着々と国内外で競技人口を増やしています。
※笹川スポーツ団体による調査結果より、20代以上の競技人口と10代の競技人口を合計した数値
eスポーツは普通のゲームと何が違うの?
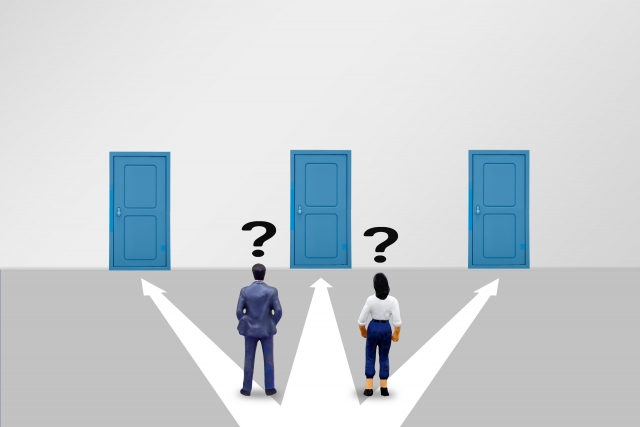
eスポーツはコンピューターゲームを用いて競うスポーツですが、一般的に流通しているゲームならどんなタイトルでも使用できる訳ではありません。
続いては、eスポーツと普通のゲームの違いについて解説します。
eスポーツは競技要素が高い
eスポーツで扱われるゲームタイトルは必ず勝敗のつくものです。そのため、シュミレーションゲームやRPG(ロールプレイングゲーム)などがタイトルに採用されることは、ほとんどありません。 何らかの要素によって勝敗がつくことで、スポーツ競技として成り立っています。
eスポーツはエンターテイメント性が高い
一般的に普通のゲームは家庭内でプレイする事が多いでしょう。近年はオンラインゲームが流行していることもあり、家庭内でも友人や見知らぬ人と対戦する事ができます。
しかし、eスポーツは主に会場に足を運んで大会に出場するのが一般的です。地区予選などは、オンラインで開催される事もありますがeスポーツの大会の多くはスポンサーに出資を募り、会場で大々的に開催されます。
これは、eスポーツが収益の発生するエンターテイメントであるからです。
これまで家庭内で行っていたゲームを、eスポーツに昇華することで、エンターテイメント性を向上させています。
大きな大会を開催して注目を集める事でスポンサーが集まり、出資によってプロプレイヤーの育成や海外大会への遠征など、業界を盛り上げていくのがプロスポーツの基本的構造です。野球やサッカーなどと同じように、eスポーツもプロリーグが発足され、多くのスポンサーに注目される興行となっています。
高額の賞金がでる
eスポーツと普通のゲームの最も大きな違いは高額の賞金が設定されていることでしょう。
世界中で人気を博しているDota2は、これまで国際大会の賞金総額が約536億を超えたと言われています。eスポーツの中でも特に高い賞金が設定されるタイトルとして知られており、2021年に行われた世界チャンピオンシップ大会では1つの大会における賞金総額が約53億円であった事も話題になりました。
2019年に行われたフォートナイトの世界大会では16歳の少年が優勝し、賞金約3億円を獲得したこともニュースに取り上げられました。
年齢に関わらず莫大な賞金をかけて競うことができるeスポーツは、夢があると言えます。
eスポーツとゲームの4つの違い

eスポーツとゲームの違い4つを解説していきます。eスポーツもゲームの1種ですが、eスポーツ以外のゲームとは明確な違いがあります。ここでは、その4つの違いについて詳しく解説をしていきます。
- 対人戦かどうかが違う
- ゲームジャンルが違う
- 運の要素が少ない
- プレイの目的が違う
対人戦かどうかが違う
eスポーツとゲームの違いは、対人戦かどうかです。eスポーツは相手と競うことを主としているため、対人戦のゲームでなければいけません。自分1人でプレイをするゲームはeスポーツにならないことがほとんどです。例えば、有名なeスポーツである、VALORANTやLoL、FORTNITEなどは全て対人ゲームです。
1人でプレイするゲームがeスポーツになる事がないわけではありません。しかし、eスポーツとして競い合う際には、対人のモードが採用されることが多いです。例えば、1人でプレイできる太鼓の達人や、パズル&ドラゴンズなどは、eスポーツになっています。しかし、eスポーツとして、競い合う際には、マルチプレイの対戦機能を使っています。eスポーツとゲームの違いは対人戦で行えるかどうかです。
ゲームジャンルが違う
eスポーツとゲームの違いは、ゲームジャンルにあります。対人戦かどうかという事に、つながりますが、1人でプレイをするRPGのようなゲームジャンルはeスポーツになりにくいです。逆に言うと、シューティングゲームやMOBAと言ったゲームジャンルは、対人戦でeスポーツの側面が強いです。
ゲームのプレイ人口がそこまで多くなくても、ゲームジャンルが適していれば、eスポーツとして、大会が行われる場合があります。FPSやレーシングゲームなど、eスポーツに適したジャンルは、eスポーツになりやすいです。eスポーツとゲームの違いは、ゲームジャンルがeスポーツに適しているかどうかにあります。
運の要素が少ない
eスポーツとゲームの違いは、勝敗に運の要素が少ないかどうかです。プレイヤーのスキルが勝敗に反映されにくいゲームは、eスポーツになりにくいです。運の要素が強いと、初心者とプロの実力差が無くなってしまいます。
しかし、運の要素が強いゲームでも、実力が反映できるゲームであれば、eスポーツになることはあります。例えば、オンライントレーディングカードゲームは運要素が強いですが、細かい所で実力が反映されるため、eスポーツとして成り立っています。実際には、素人がプロに勝ててしまうゲームですが、それでも、プロの方が勝率は高くなります。稀に運要素が強いeスポーツがありますが、実際にはeスポーツとゲームの違いは、運要素の少なさにあるのです。
プレイの目的が違う
eスポーツとゲームはプレイの目的が違います。ゲームは楽しむためにストーリーやコンピューターとの対戦を楽しみますが、eスポーツは対人戦での勝利を目的にします。試合に勝つためにプレイや練習をしていくのがeスポーツなのです。
eスポーツはゲームとは違い、勝つことが目的になっています。そのため、ゲーム内にストーリーがないことがほとんどで、ストーリーがあってもプレイヤーのほとんどは気にしていません。eスポーツをプレイしている多くのプレイヤーが、ストーリーなどを楽しむ事よりも、対戦で勝つことを目的にしているが、eスポーツとゲームの明確な違いです。
eスポーツ競技に使われるタイトル

ゲームにはさまざまなジャンルがあります。なかには、特定のジャンルのゲームしかプレイした事がないという人もいるのではないでしょうか。
eスポーツと普通のゲームには、競技タイトルに指定されるジャンルにも違いがあります。
どのようなジャンルのゲームでもeスポーツができる訳ではありません。eスポーツでは、一般的に以下のジャンルが競技タイトルとして採用されることが多いです。
| MOBA (マルチプレイヤーオンラインバトルエリア) | 主にチーム戦で競い、敵の陣形などを崩しながら勝利条件を満たす事を目的としたゲーム |
| RTS (リアスタイムストラテジー) | 第三者の視点で、コマンドに沿って動く複数のキャラクターに指示を出して相手の陣地を攻略する戦略型ゲーム |
| FPS (ファーストパーソンシューティング) | 自分の視点で行うシューティングゲーム |
| TPS (サードパーソンシューティング) | 第三者目線の視点で行うシューティングゲーム |
| スポーツ | 野球、サッカーなど実在するスポーツをモチーフにしたゲーム |
| 格闘 | キャラクターを操り、相手の体力ゲージを0にすることを勝利条件として対戦するゲーム |
| OGC (オンラインカードゲーム) | ゲーム上でプレイするカードゲーム |
スポーツじゃないとは言わせない!eスポーツプレイヤーに求められるスキル

eスポーツプレイヤーには、普通にゲームをしている人とは違う次元のスキルが求められます。続いては、eスポーツがスポーツとして扱われるようになった由縁とも言えるスキルについて紹介します。
高度なゲームスキル
eスポーツで世界のプロプレイヤーと競うために、高度なゲームスキルは欠かせません。卓越したエイム力やアクションコマンドの入力スキルなど、何十時間、何百時間、何千時間とかけて磨き上げた技術で競い合うのがeスポーツの醍醐味です。
ゲームを熟知した戦略
eスポーツでは単純なゲームスキルが高いだけでは上位プレイヤーと競い合えません。そこに必要なのは戦略です。どのように相手を攻撃すれば効率良く勝つ事ができるのかを、日頃から分析して何通りもの戦略を立てます。
また、ゲーム特有のルールをどう活かすのかや、フィールドの地形を覚えて攻撃を組み立てるなど、スキルと同等以上に知略が求められるのもeスポーツの特徴です。
瞬間的に選択ができる判断力
eスポーツでは刻一刻と戦況が変化します。その際に瞬時に判断して最善の選択をできるプレイヤーが勝ち残ると言ってもよいでしょう。
eスポーツにはリアクションタイムという言葉があります。これは、ゲーム中に何らかの動きがあるのに対し、自分が反応するまでの時間を指す言葉です。特に格闘ゲーム、FPS、TPS、レーシングゲームなど、スピード感を重視するゲームジャンルではリアクションタイムの短さが求められます。
何らかの状況変化に対して、いかに短時間で行動を起こすのかによって勝敗が分かれるからです。
リアクションタイムは、年齢、遺伝子、経験などで培われるものだと言われており、eスポーツプレイヤーはリアクションタイムを縮めるためのトレーニングに励んでいます。
長くゲームを続けられるフィジカル
ゲームと聞くと、空調の効いた室内でお菓子やジュースを食べながらのんびりとプレイするイメージを持っている人も多いでしょう。普通のゲームであればそうかもしれません。
しかし、eスポーツプレイヤーは違います。長くゲームを続けるために、腰痛対策や視力の低下を抑える工夫など、今後もプレイヤーとして最前線で戦い続けるための体作りにも取り組んでいるケースがほとんどです。
eスポーツはプロライセンスもある

日本eスポーツ連合では、eスポーツのプロライセンスも発行しています。必ずしもプロライセンスが必要という訳ではありませんが、ライセンス保持者のみを対象とした大会などもあるため、近年eスポーツプレイヤーのなかでもライセンスを取得する人が増えています。
プロライセンスは、大会などでの実績を加味して発行されます。そのため、ライセンスを所持しているだけでもある程度の実力を持つeスポーツプレイヤーである事が分かるでしょう。
eスポーツプレイヤーとして普通にゲームをしている人との区別をするためにも、ライセンスは良い目安になると言えます。
eスポーツはゲーム学習に役立つ?

eスポーツはゲーム学習に役立ちます。ここでは、eスポーツがゲーム学習にどのような役立つのかを詳しく解説していきます。
- eスポーツは特にゲーム学習に効果的
- 思考力や創造力が身につく
- コミュニケーション能力やネットリテラシーも身につく
- eスポーツのゲーム学習にはAFRASがおすすめ
- eスポーツによって身につく力が変わる
eスポーツは特にゲーム学習に効果的
eスポーツはゲームの中でも特にゲーム学習に効果的です。eスポーツは普通のゲームに比べて、考えることが多いです。eスポーツをプレイしていると、思考力や創造力が身についていきます。また、eスポーツでゲーム学習をすると、コミュニケーション能力やネットリテラシーも身につきます。ゲームで学習をしたい場合は、eスポーツをプレイしてみてください。
思考力や創造力が身につく
eスポーツをすることで、思考力や創造力が身につきます。特に、FORTNITEやマインクラフトのように、物を組み立てるようなeスポーツはゲーム学習に最適です。ゲームで遊びながら、考える力が身についていきます。
eスポーツでどのようにして、相手に勝つかを考えることも、思考力や創造力の向上に役立ちます。また、問題解決のために考える能力や物事を改善する能力も身につきます。思考力や創造力を養えるのが、eスポーツでゲーム学習をするポイントです。
コミュニケーション能力やネットリテラシーも身につく
eスポーツをゲーム学習として行う事で、コミュニケーション能力や、ネットリテラシーが身につきます。eスポーツは基本的にオンラインで行うため、他の人とコミュニケーションを取る機会があります。eスポーツを行っていくことで、コミュニケーション能力が養われていきます。
ただし、ネット上でのコミュニケーション能力がない状態でeスポーツをする際には注意が必要です。つい、暴言や過激な発言をしてしまうと、ゲーム内でペナルティが与えられたり、問題になったりします。味方だけではなく、相手にもリスペクトを持ちつつ、eスポーツをプレイすることが大切です。
eスポーツのゲーム学習にはAFRASがおすすめ
eスポーツのゲーム学習をするには、AFRASがおすすめです。AFRASはプロがレクチャーをしてくれるeスポーツスクールです。AFRASでeスポーツが上手くなりながら、ゲーム学習が行えます。AFRASでeスポーツをすることで、ネットリテラシーやコミュニケーション能力、創造性などが身についていきます。
AFRASでは無料レッスンや入会金無料などのキャンペーンが行われています。キャンペーンを上手く活用することで、お得にAFRASに通えます。また、自分のレベルに合わせて丁寧なコーチングを受けられるので、eスポーツが上達します。eスポーツでゲーム学習をしたい人は、ぜひAFRASをチェックしてみてください。
eスポーツによって身につく力が変わる
プレイするeスポーツによって、身につく力が変わってきます。シューティング系のeスポーツを行えば、判断力やコミュニケーション能力、思考力などが養われます。MOBA系のeスポーツをプレイすれば、コミュニケーション能力はもちろん、物事の全体を考える能力や、問題解決能力などが養われていきます。
ゲーム学習の目的に合わせて、eスポーツのタイトルを考えてみてください。コミュニケーション能力を養いたいのに、ソロで行うeスポーツをプレイしていては意味がありません。適切なeスポーツを選択して、ゲーム学習を行っていきましょう。
eスポーツはただのゲームとは違う!まずはアフラスの無料体験へ
野球やサッカーなどにもプロ野球とアマチュア野球、プロサッカーとアマチュアサッカーなどがあるように、ゲームでもアマチュアとプロには大きな違いがあります。
自己研鑽を詰み、莫大な時間をかけて作り上げたスキルや知略を駆使して競うeスポーツは、座上のスポーツと言えるでしょう。日本ではまだ馴染みが薄く勘違いされてしまう事もありますが、世界的に盛り上がりを見せているeスポーツの認知度は今後ますます上昇していくでしょう。
eスポーツが多くの人に正しく理解されるよう、eスポーツ業界の取り組みが期待されます。
AFRAS(アフラス)はeスポーツプレイヤーを目指す人におすすめのゲーミングスクールです。習い事のようにeスポーツを学ぶ事ができ、授業ではプロeスポーツプレイヤーの講師によるマンツーマン授業を受けられます。
eスポーツについて学びたい方やeスポーツが上手くなりたい方は、ぜひAFRASをチェックしてみてください。